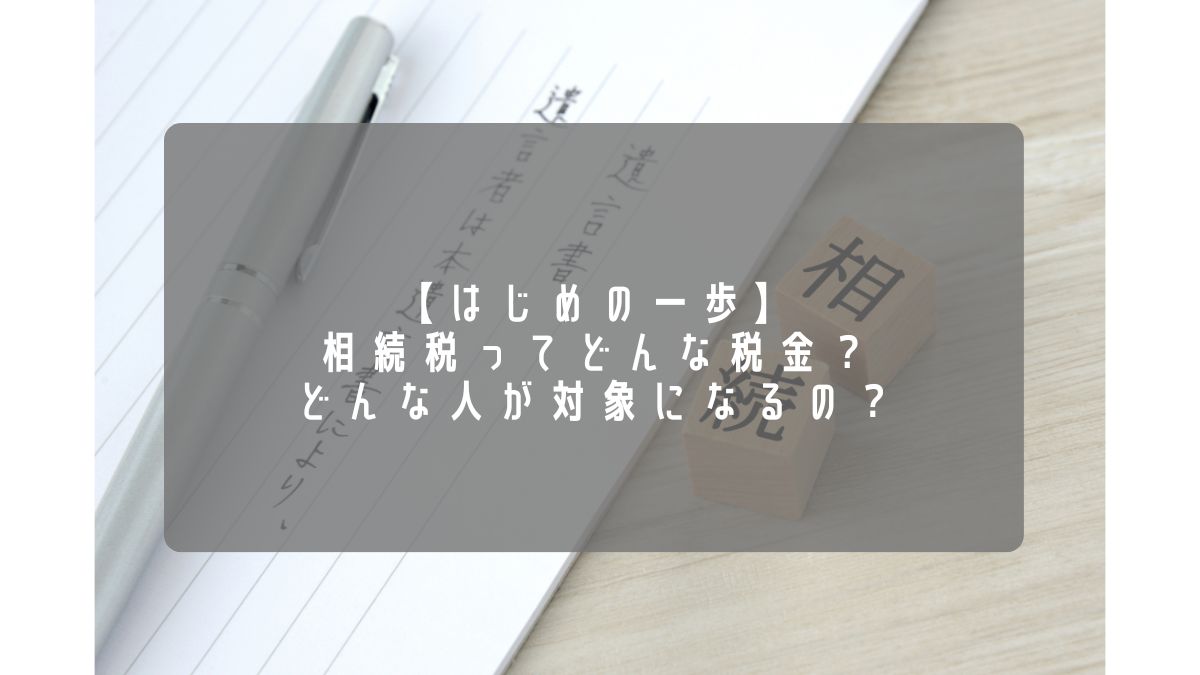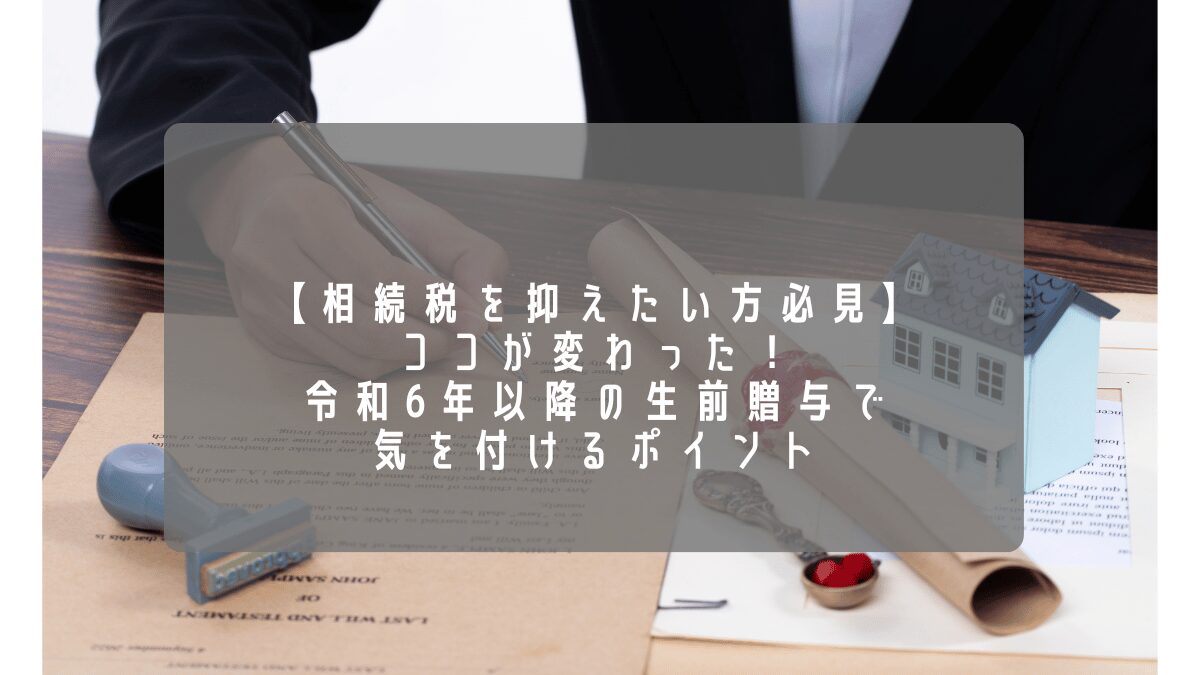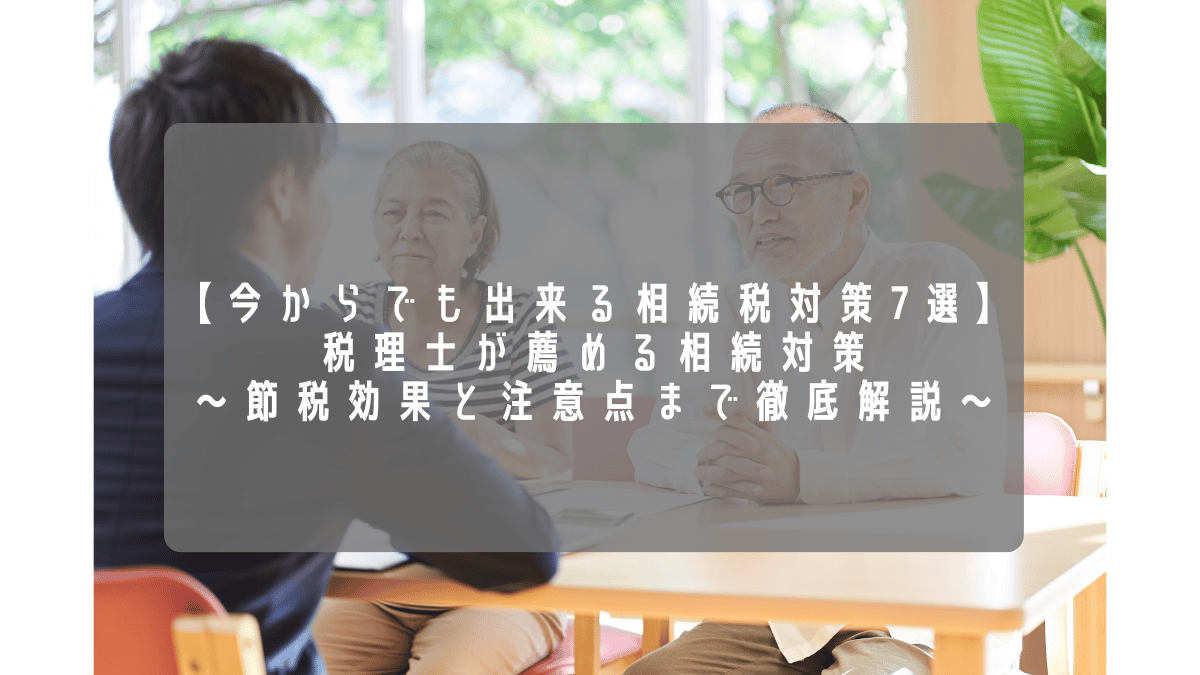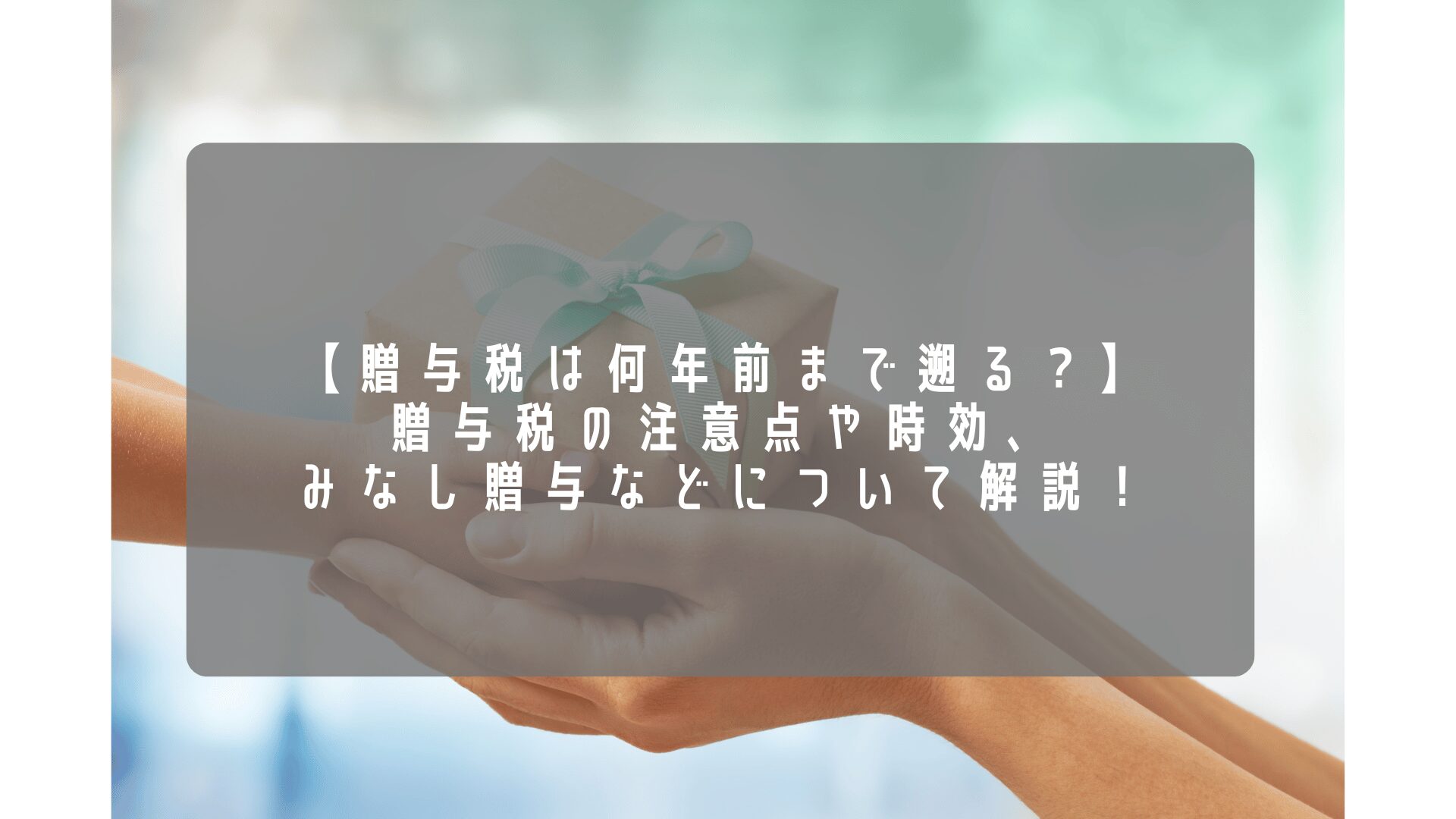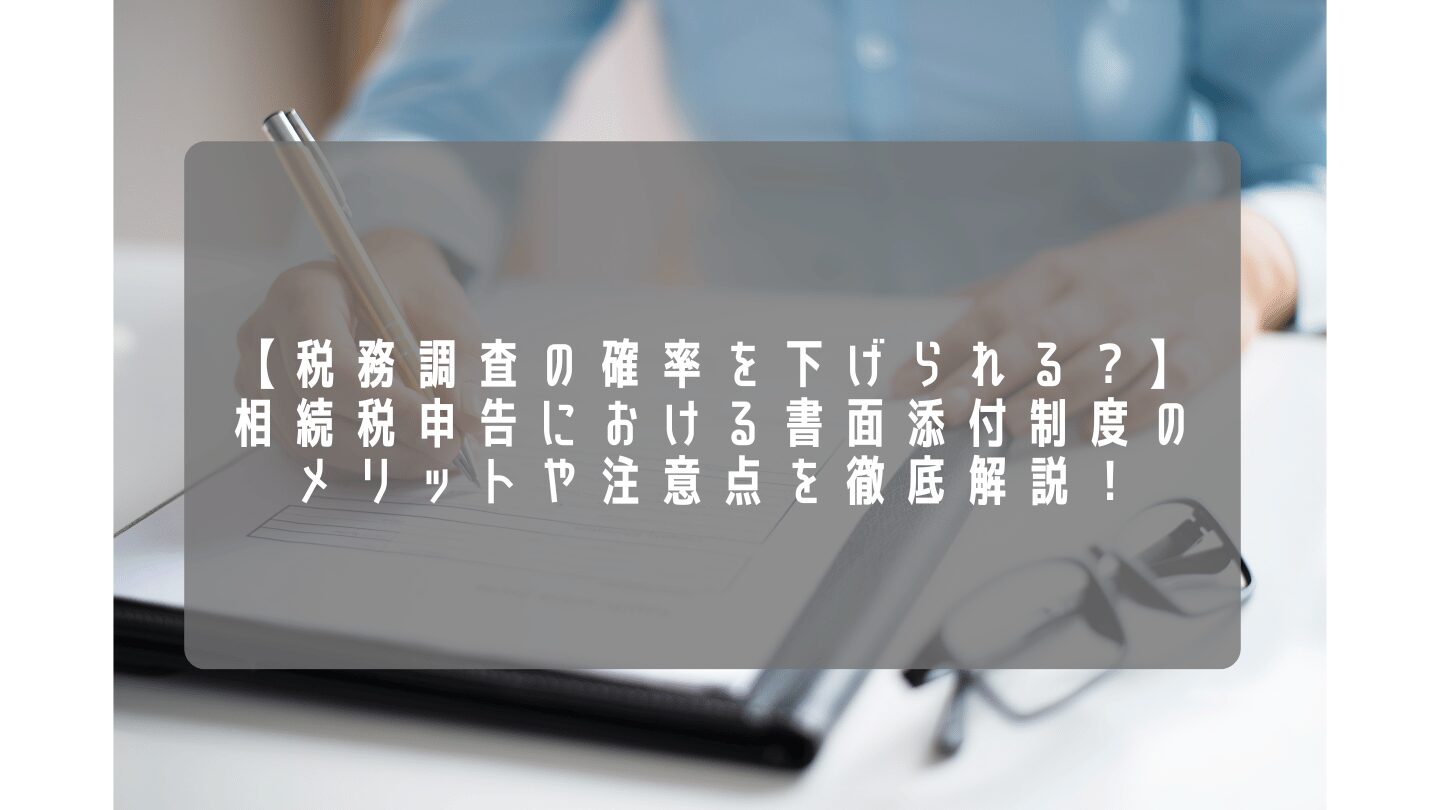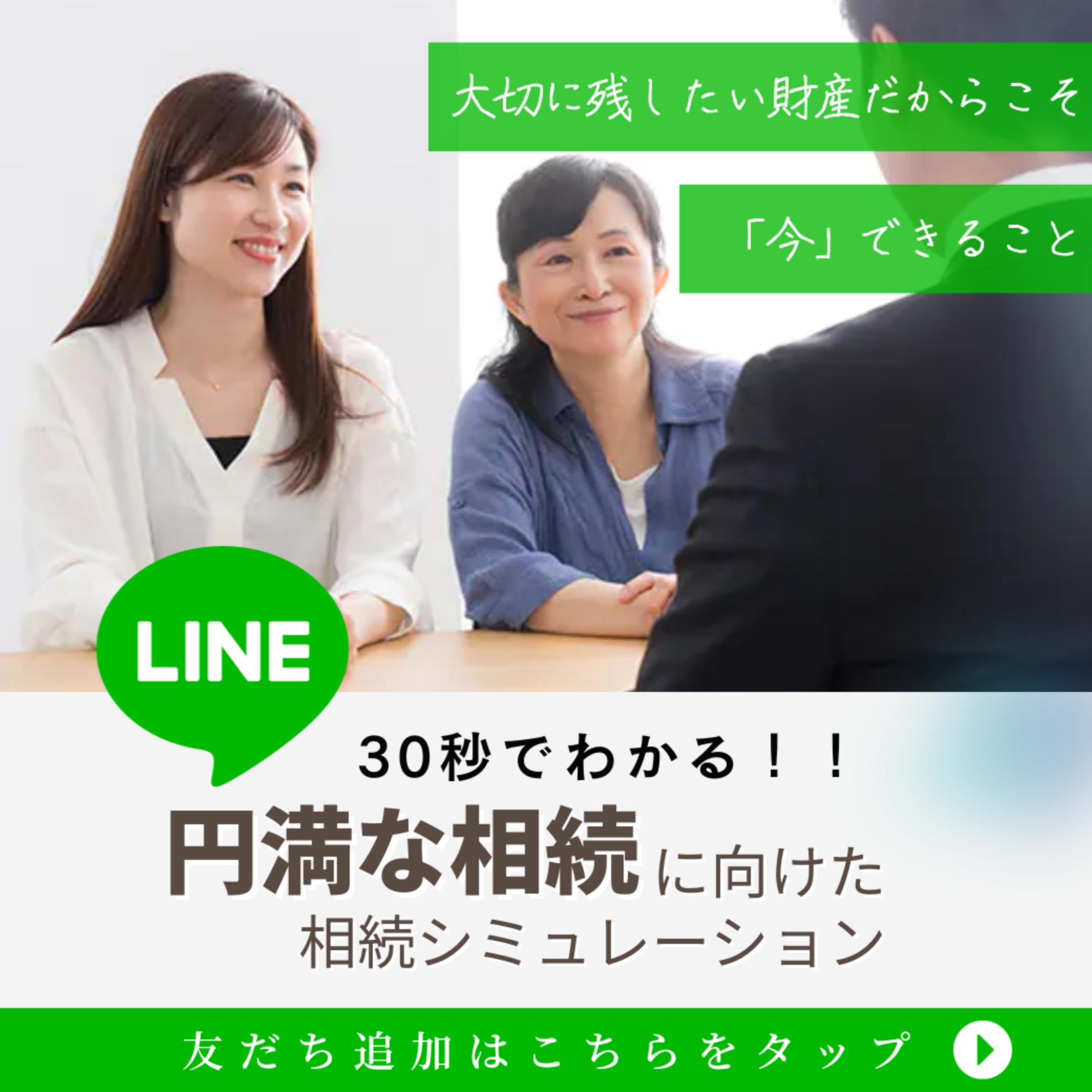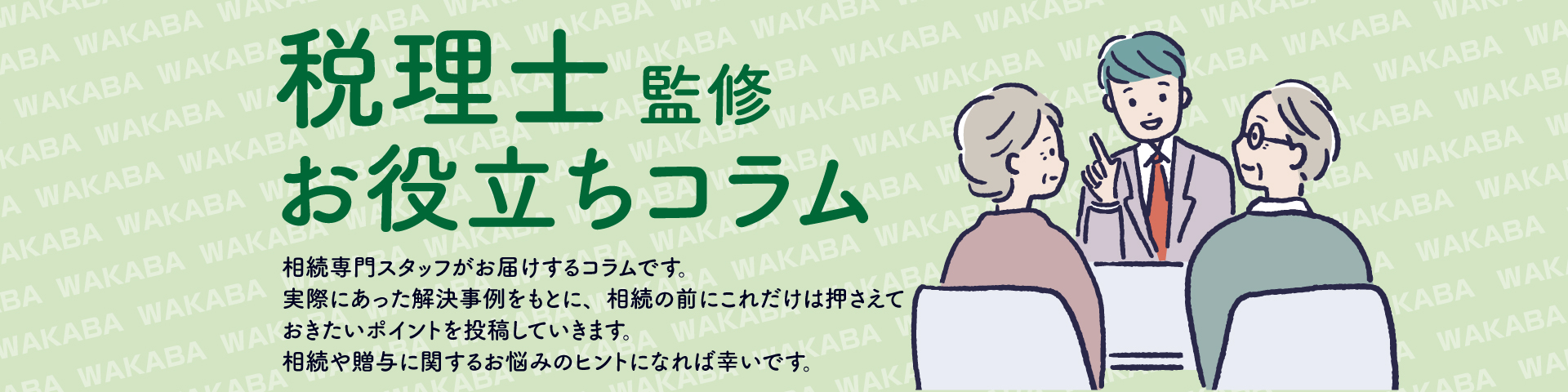
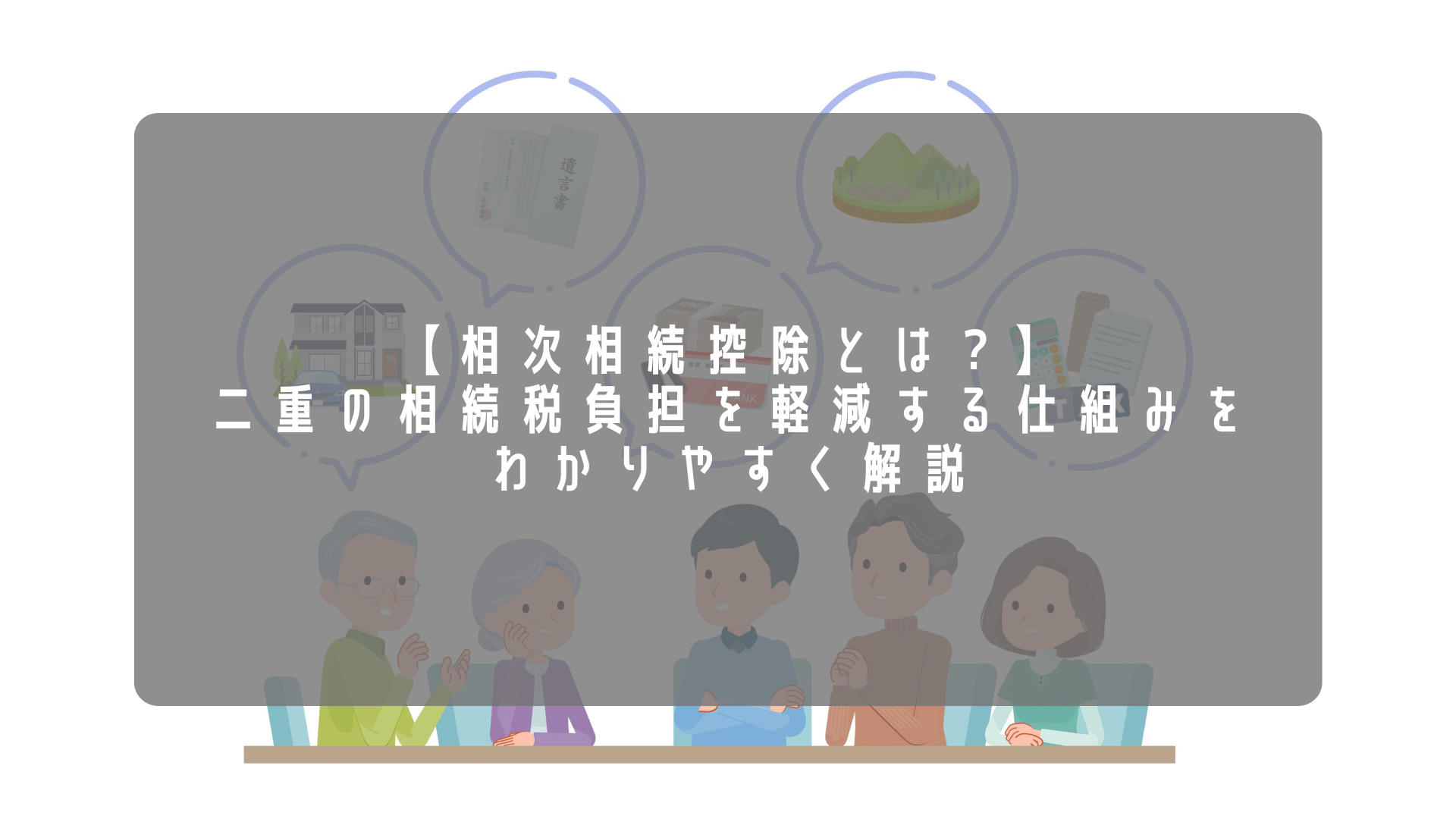
相続税は、財産を受け継ぐ際に課される税金で、通常は一世代に一度の相続が想定されています。
ですが、家族の高齢化などにより、短期間に相続が連続して発生するケースが増えています。
例えば、母が父の財産を相続した直後、母も亡くなってその財産を子どもが引き継ぐ場合などです。
このような場合、母が相続時に相続税を支払っているにもかかわらず、同じ財産に再び相続税が課税されてしまうことになります。
こうした不公平を調整するために設けられているのが、「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」です。
一定の条件を満たすことで、二次相続における相続税額の一部を控除することができる制度です。
短期間で同じ財産に二度課税される「二重課税」の負担を軽減することが目的で、相続税法第20条に基づいています。
この記事では、相次相続控除の基本的な仕組みや適用される条件、注意点などについて具体例を交えて解説していきます。
いざという時に制度を適切に活用できるよう、参考にしてみてください。
Contents
相次相続控除とは?
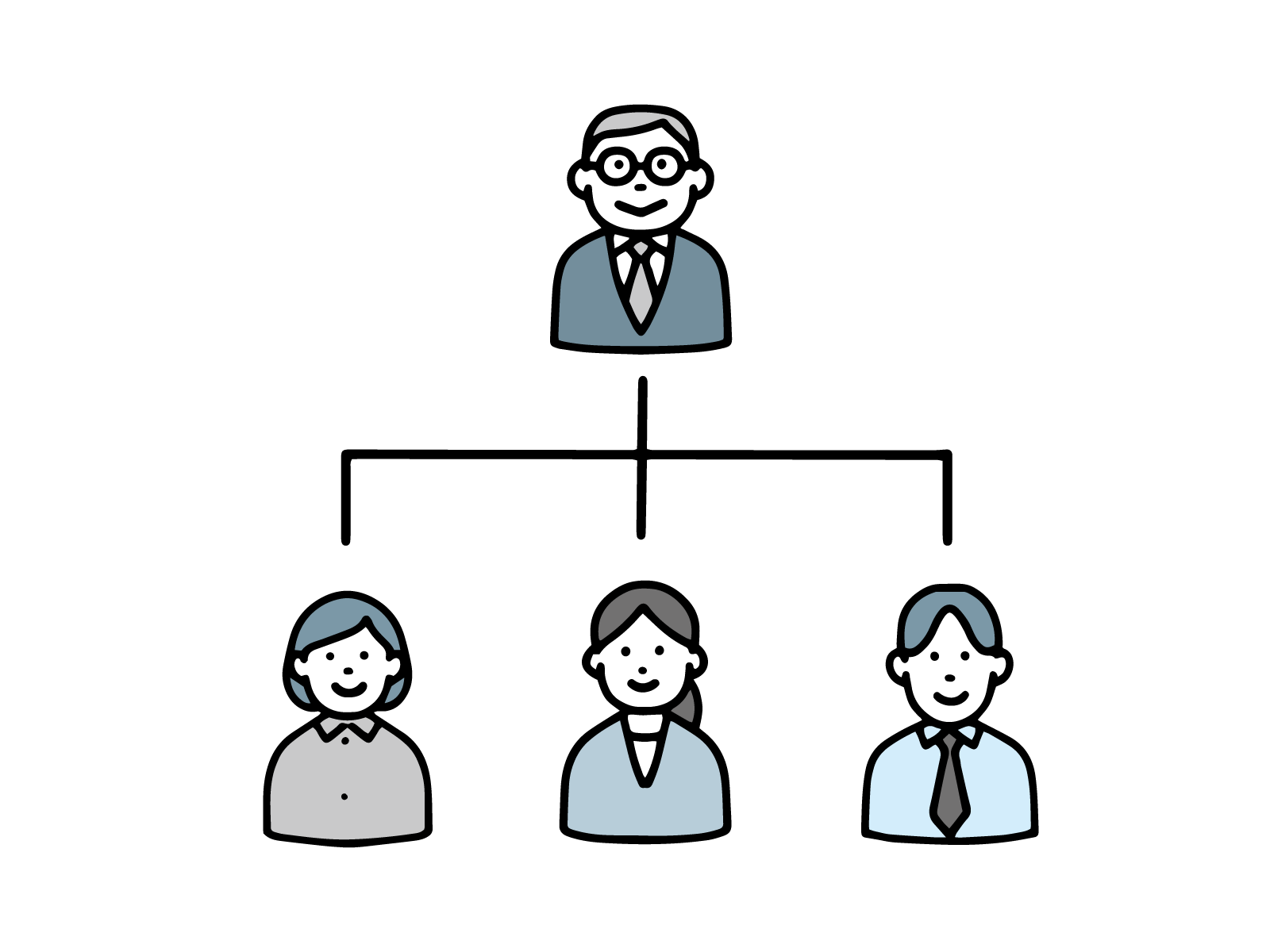
相次相続控除とは、一次相続・二次相続が連続で発生した場合に、二次相続の相続税から一部を控除できる制度です。
前回の相続からの経過年数が短く、支払った税額が多いほど、控除額が大きくなる仕組みになっています。
この控除が適用されるのは、前回の相続開始日から10年以内に次の相続が発生した場合のみです。
10年を超えると、経過に伴って財産状況が変わる可能性が高いことから、控除が適用できなくなります。
相次相続控除の目的
昨今の高齢化社会では、次のような状況が増えています。
●高齢の夫婦が続けて亡くなる
●親が亡くなった直後に子も高齢で亡くなる
●祖父母から親、親から子へと短期間で財産が移転する
例えば、父の財産を母が相続し、母が亡くなった時点では「父の財産+母自身の財産」の合計に相続税が課税されます。
つまり、父由来の財産にも再び課税されてしまうことになるのです。
この不公平を是正するため、前回相続で支払った税額を考慮し、二次相続の税負担を軽減できるようにしたのが相次相続控除です。
相次相続控除が適用される条件

相次相続控除は通常の相続だけではなく、相続時精算課税制度の生前贈与などでも適用することができます。
ただし、相次相続控除を適用するには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
●相続人であること
●一次相続から10年以内に二次相続が発生していること
●二次相続の被相続人が一次相続で財産を取得し、相続税を納付していること
1. 相続人であること
財産を取得する人が法定相続人であることが条件です。
そのため、相続放棄をした人や欠格や廃除で相続権を失った人は対象外になります。
相続人以外の人が遺贈で財産を取得した場合も対象になりません。
2. 一次相続から10年以内に二次相続が発生していること
前回の相続(一次相続)から10年以内に次の相続(二次相続)が発生している必要があります。
10年は一次相続開始日(被相続人が亡くなった日)から数えます。
一次相続における相続税の申告期限(相続開始の翌日から10ヶ月以内)とは開始日が異なるため、注意しましょう。
3. 二次相続の被相続人が一次相続で財産を取得し、相続税を納付していること
二次相続における被相続人が、一次相続の際に相続人として相続財産を取得し、相続税が課税されている必要があります。
相続財産は、被相続人名義の不動産(土地や建物)、有価証券、銀行預貯金や現金などが該当します。
また、一次相続で相続財産を取得していても、相続税を納税していなければ相次相続控除を適用することはできません。
そのため、基礎控除や配偶者控除により一次相続の相続税がゼロだった場合も対象外になります。
相次相続控除の計算方法
相続人1人あたりの相次相続控除の計算式は、次の通りです。
「A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10」=「相次相続控除の控除額」
A:二次相続の被相続人が、一次相続で取得した財産に課税された相続税額
相続時精算課税制度による、納付済の贈与税額を控除した後の金額です。
B:一次相続の純資産価額
相続によって取得した財産の価額に相続時精算課税制度を適用した財産の価額を足し、借金・未払い金・葬式費用等を差し引いた後の金額です。
C:二次相続の純資産総額
今回の二次相続におけるすべての相続財産の合計額です。
遺贈した財産や、相続時精算課税制度を適用した財産、相続開始前3年以内(※令和9年以降の相続から段階的に「7年以内」まで延長)の贈与財産も含めた合計額になります。
今回の二次相続でそれぞれの相続人が相続した財産額です。
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
上記の式は複雑でわかりにくいため、ステップに分けて計算するのがおすすめです。
①二次相続の純資産総額÷(一次相続の純資産総額―一次相続の相続税額)を計算
※100/100を超えるときは100/100(=1)にする
②二次相続人が一次相続で取得した財産額÷二次相続の課税財産総額を計算
③(10年-経過年数)÷10を計算
④「一次相続の相続税額×①×②×③」=「相次相続控除の控除額」となります。
実際に具体例を用いて計算してみます。
・一次相続で母が純資産価額1億3,000万円を相続し、相続税額1,000万円を納税
・二次相続の相続税の純資産価額は1億6,000万円
・二次相続で子2人が相続する純資産価額は1人8,000万円
・一次相続から二次相続までの経過年数は5年5か月
①1億6,000万円÷(1億3,000万円―1,000万円)=4/3→100/100を超えるので1
②8,000万円÷1億6,000万円=1/2
③(10年-5年)÷10=1/2
④1,000万円×1×1/2×1/2=「相次相続控除の控除額250万円 」
相次相続控除の申告方法
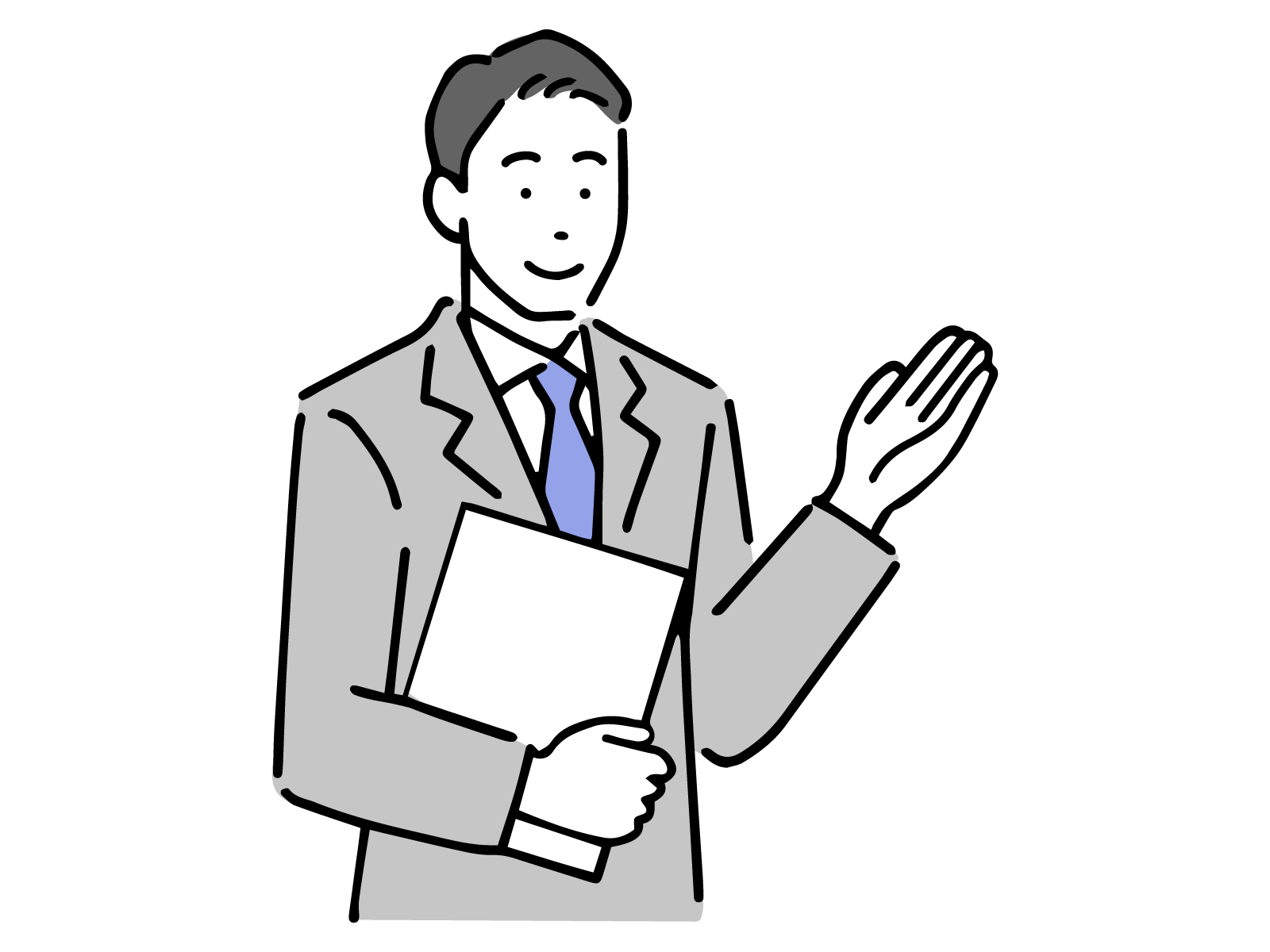
相次相続控除を適用するためには、相続税の申告書に適用する旨を記載する必要があります。
適用要件をすべて満たしていても、申告書に記載がなければ控除されない点には注意しましょう。
相続税の申告書は第1表か第15表までありますが、相次相続控除に関する書類は第7表(相次相続控除額の計算書)と第8表の8(税額控除額及び納税猶予税額の内訳書)になります。
その他の添付書類
一次相続で提出した相続税申告書控のコピーを添付しましょう。
●相続税の申告書第1表(相続税の申告書)
●相続税の申告書第11表(相続税がかかる財産の明細書)
●相続税の申告書第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書)
●相続税の申告書第14表(純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額の明細書)
●相続税の申告書第15表(相続財産の種類別価額表)
相次相続控除の注意点・ポイント
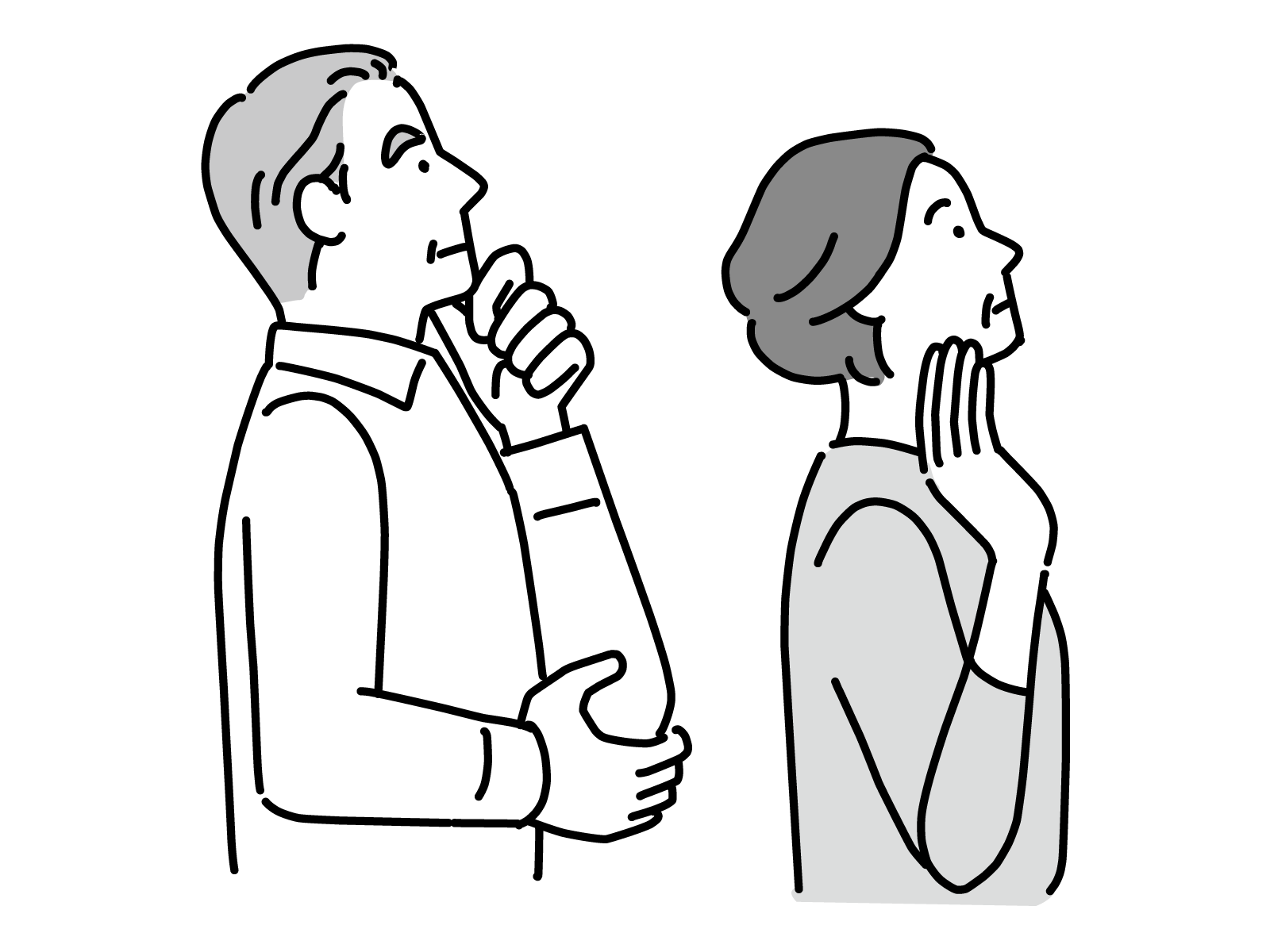
相次相続控除を正しく活用するためには、制度の仕組みだけでなく注意点やポイントを理解しておくことも重要です。
① 計算が複雑なため、専門家への相談がおすすめ
相次相続控除の計算は、前回相続での相続税額・取得割合・経過年数など、複数の要素を組み合わせて行うため非常に複雑です。
計算ミスにより、本来受けられる控除額を申告できないケースもあるため、相続税に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
② 前回の相続で相続税が課税されていない場合は適用できない
相次相続控除は、前回の相続で被相続人が実際に相続税を納めている場合に限り適用されます。
例えば、父の相続時に母が配偶者控除(配偶者の税額軽減)を利用して相続税が発生しなかった場合、母の相続(=二次相続)では相次相続控除を受けることはできません。
重要なのは、二次相続における被相続人が納税したかどうかで、二次相続の相続人が一次相続で税金を支払ったかは関係ない点には注意しましょう。
③ 兄弟姉妹間の相続でも適用可能
相次相続控除は、親から子への世代間相続に限らず、兄弟姉妹間の相続でも要件を満たせば適用可能です。
子がいない被相続人の財産を兄弟姉妹が相続する場合でも、兄弟姉妹が法定相続人となれば控除対象になります。
④ 相続税申告後でも適用できる
当初の相続税申告時に相次相続控除を申請し忘れていても、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」により適用を受けることが可能です。
控除を失念したまま申告してしまった場合でも、慌てず専門家に相談しましょう。
⑤ 未分割の状態でも適用可能
遺産分割協議が相続開始から10か月以内にまとまらず、未分割のまま申告する場合でも相次相続控除は適用できます。
ただし、申告後に分割が確定した際には申告内容を修正する必要があります。
小規模宅地等の特例や配偶者控除などの特例のように、遺産分割が成立していないと適用できない特例とは違い、相次相続控除は未分割でも適用できるという点が大きな違いと言えます。
⑥ 3回目以降の相続でも適用可能
相次相続控除は、3回目以降の相続でも適用できます。
ただし、今回亡くなった被相続人が前回および前々回の相続で相続人として相続税を納めていることなど、過去の相続で納税実績があることが条件です。
まとめ

相次相続控除は、短期間に続けて相続が発生したときに、負担を軽減できる重要な制度です。
相続は突然起こることが多く、気持ちが追いつかないまま手続きを進めなければならない場面も少なくありません。
特に、家族が立て続けに亡くなる状況では、経済的な不安だけでなく精神的にも大きな負担を抱えることになります。
そのような中で、この制度は遺族にとって大きな支えとなるでしょう。
ただし、相次相続控除は申請しなければ活用できない制度です。
相続が発生した際に冷静に状況を整理し、適用できる可能性があるかを早い段階で確認することが大切です。
また、この控除を確実に利用するためには、専門的な知識が必要になります。
適用できるにもかかわらず申告を忘れてしまうケースや、計算の誤りで控除額が過少申告となるケースも決して少なくありません。
相続が続く可能性があると感じた時点で、専門家に相談しておくことが、トラブルや後悔の防止に繋がります。
いざというときに適切に活用できるよう、あらかじめできる準備をしておきましょう。
制度に関してご不明点やご相談がある場合は、遠慮なくお問い合わせください!