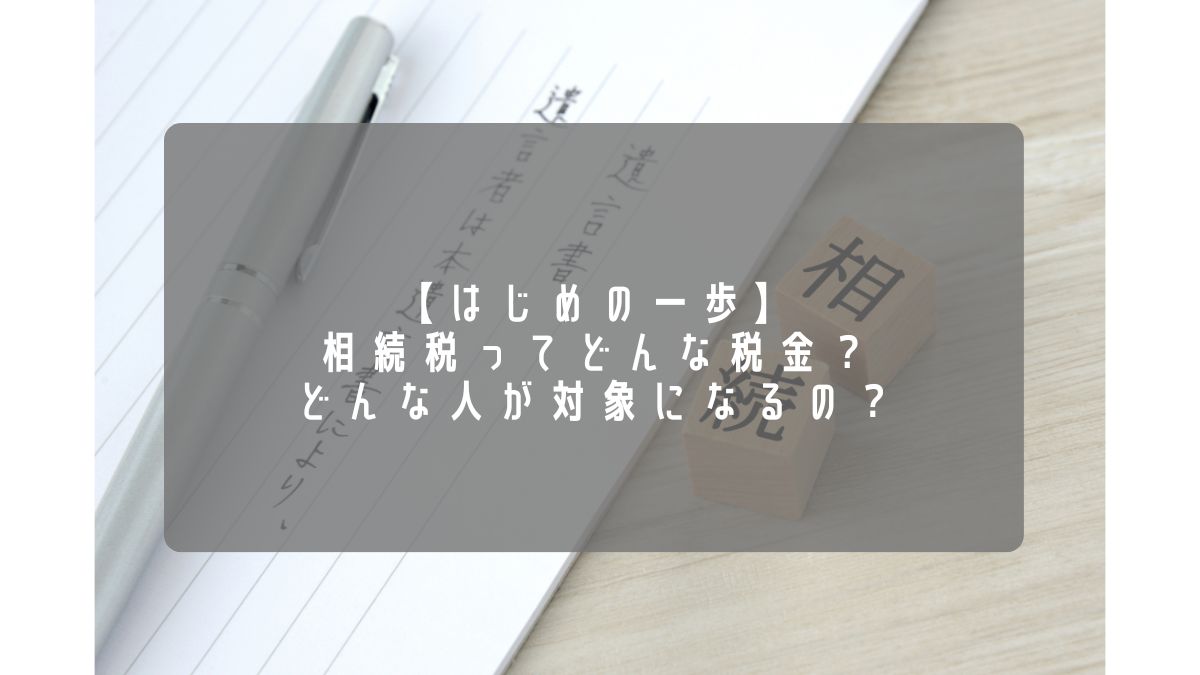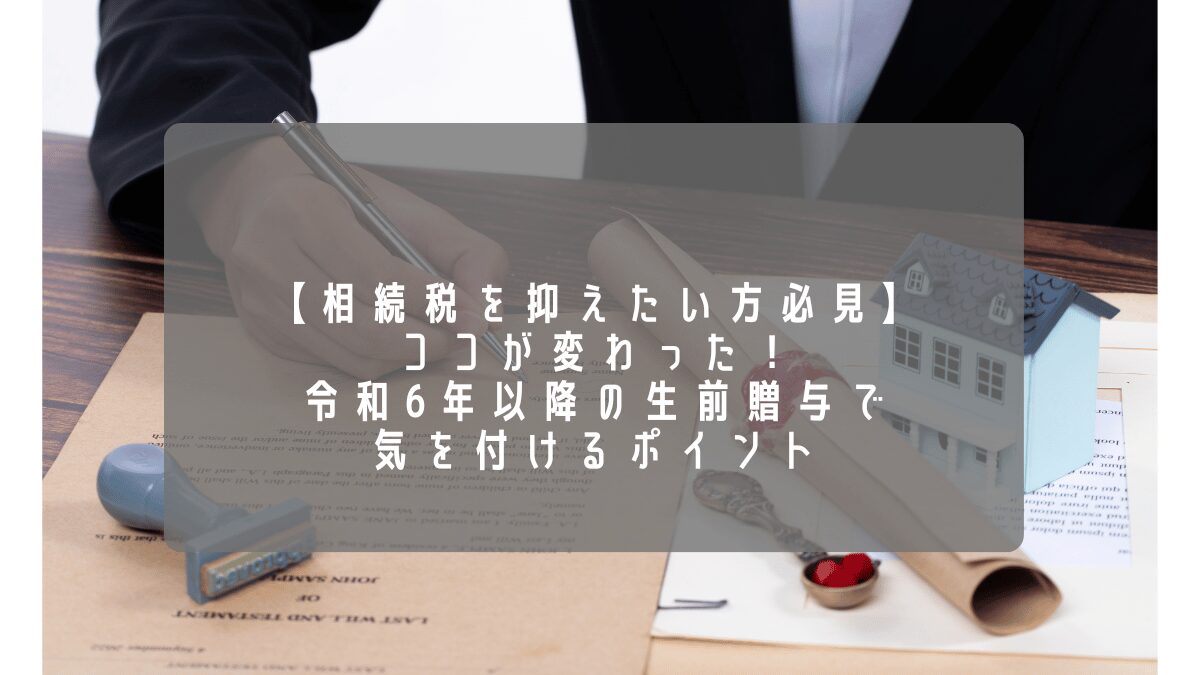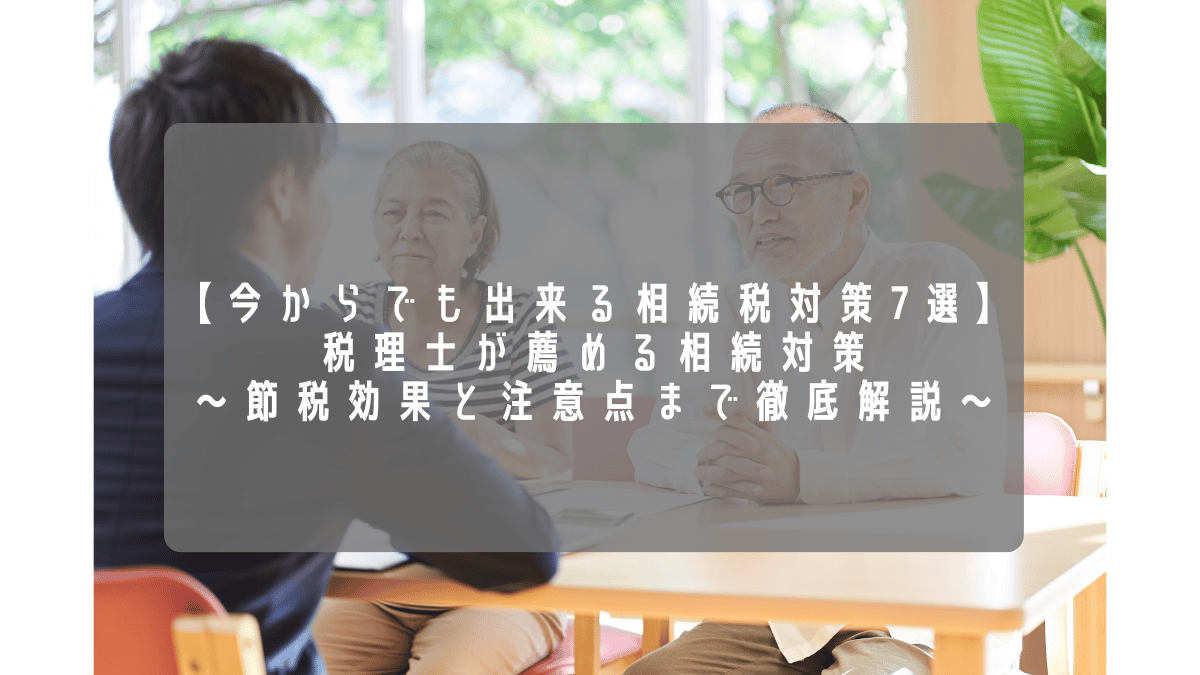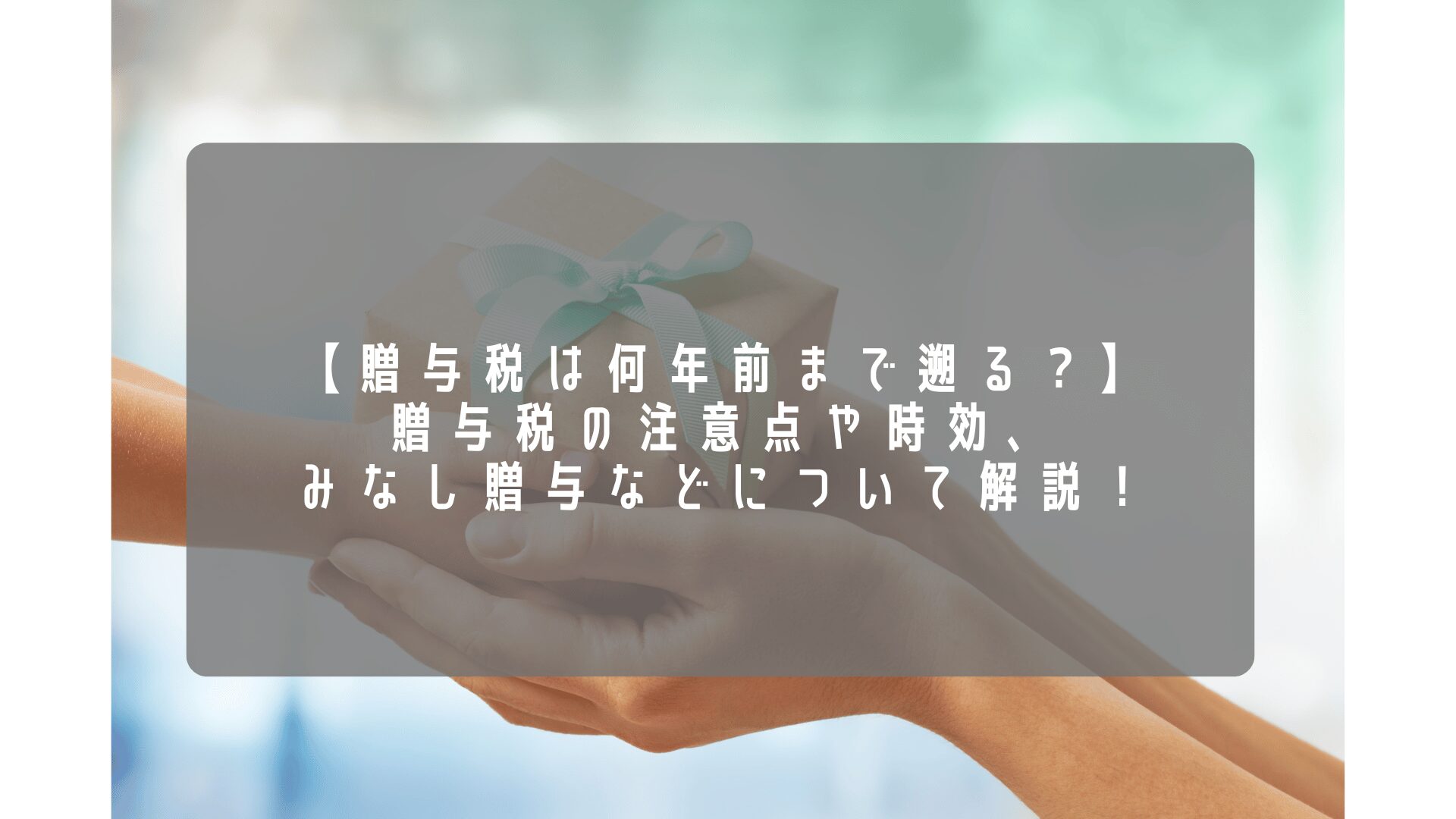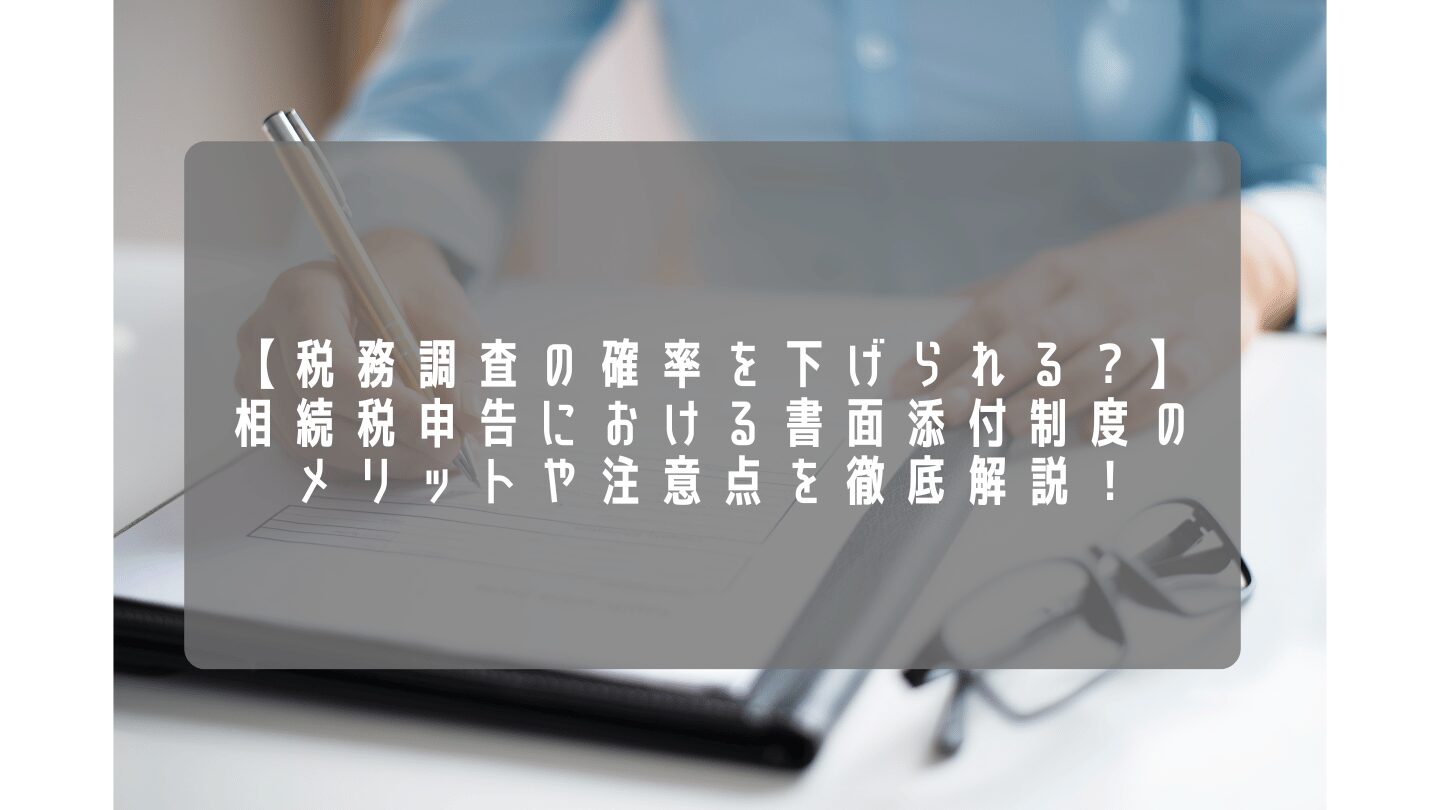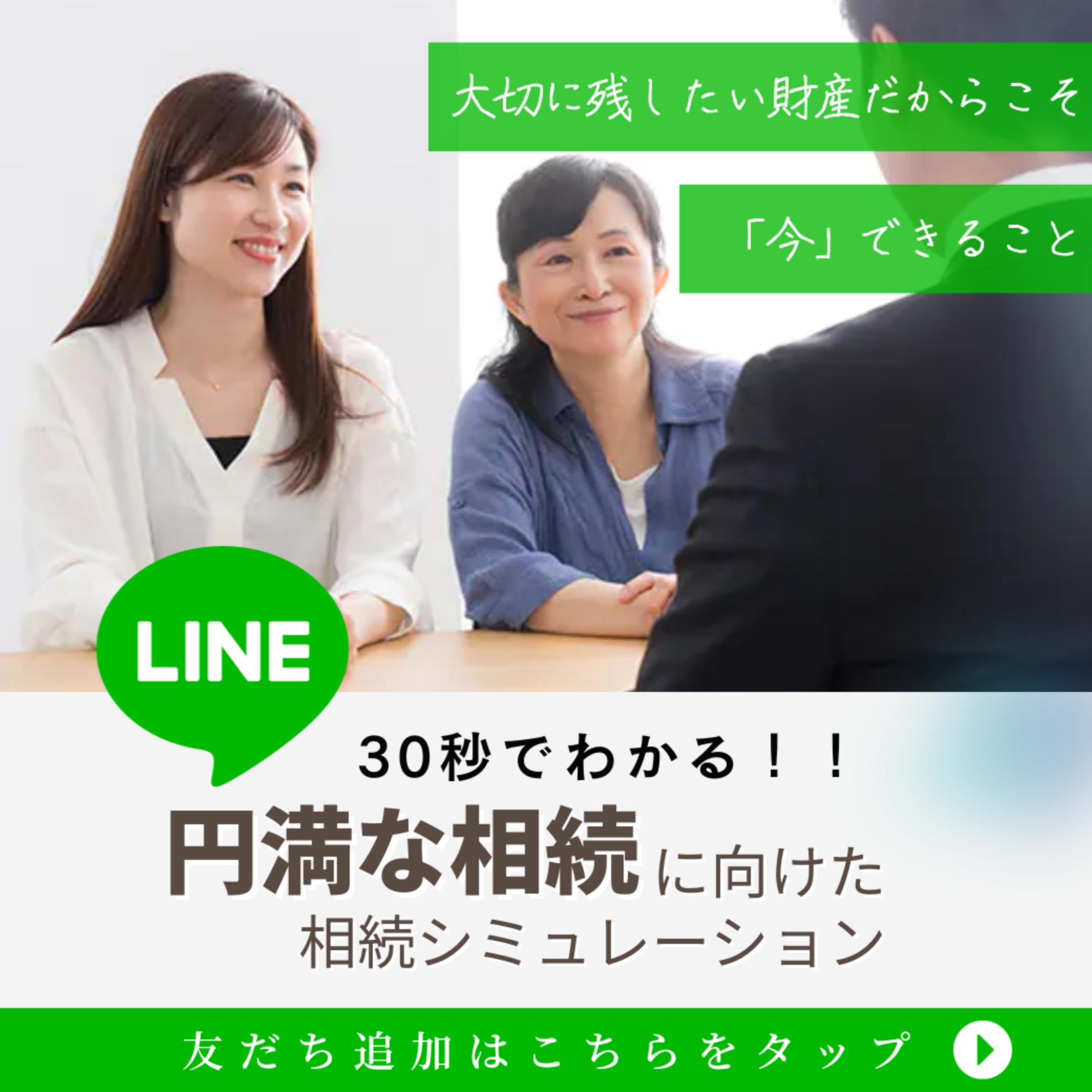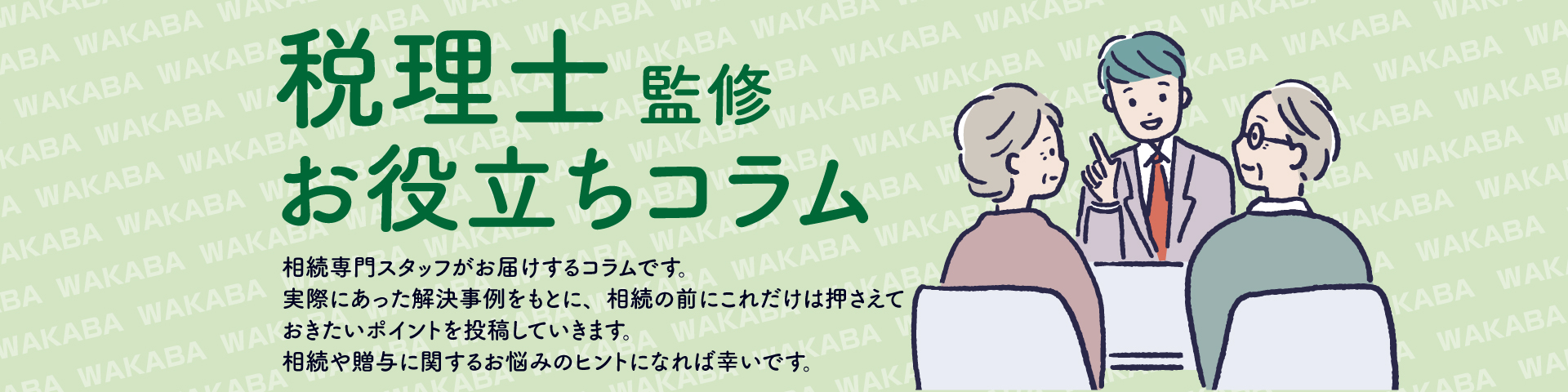
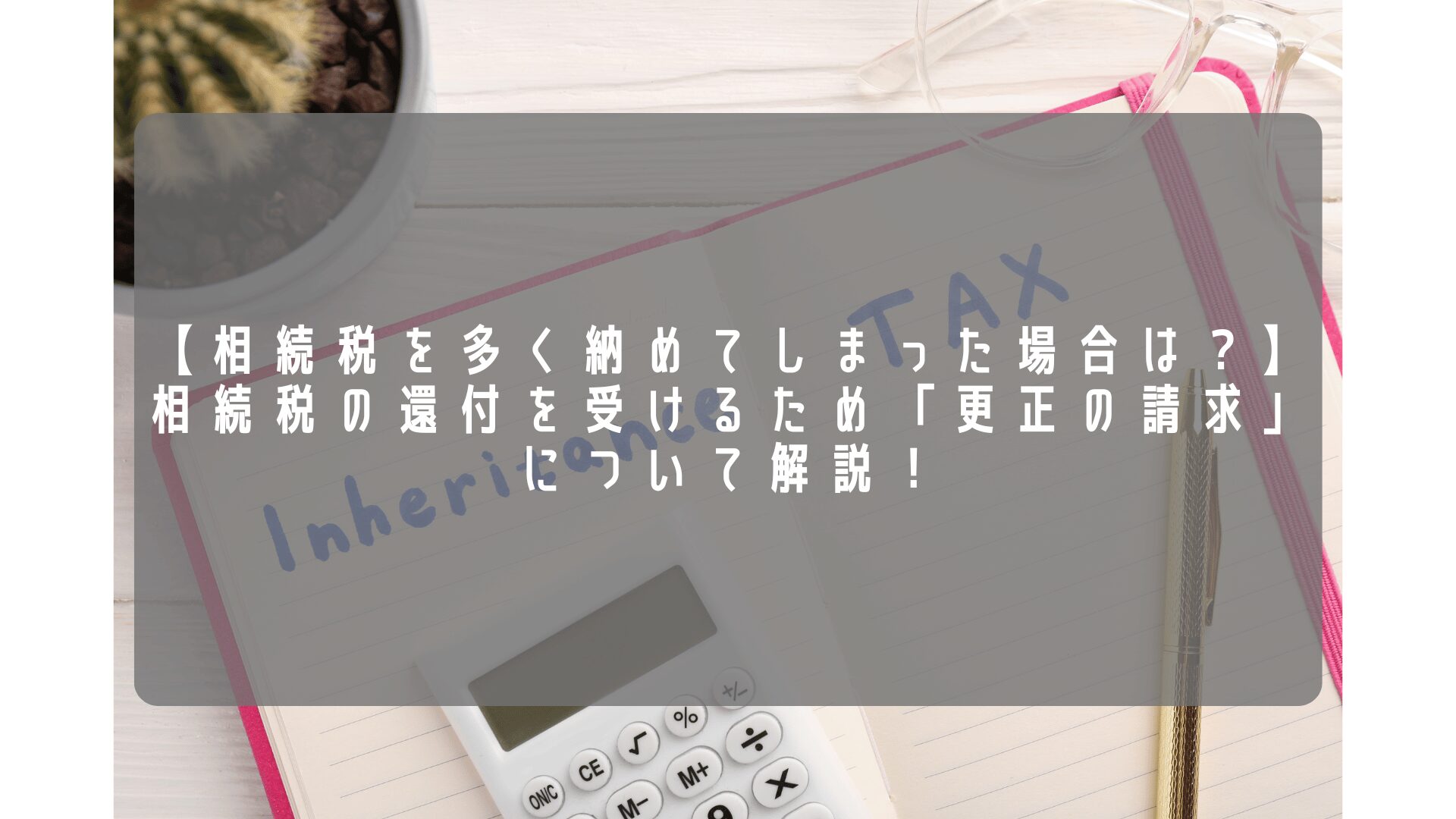
相続税は手続きが複雑なうえ、経験する機会は人生の中でも数えるほどしかありません。
そのため、相続税は非常にミスが起こりやすい税金です。
もしも、相続税の計算や相続財産の評価額を間違えて納付した場合は、修正申告が必要になります。
少ない額で納めてしまった場合は、延滞税などのペナルティと一緒に不足分を追加で納めます。
反対に、本来納めるべき金額よりも多く納めてしまっていた場合は、税金を還付してもらうことが可能です。
還付を受けるためには、「更正の請求」の手続きを行う必要があります。
ただし、更正の請求を行える期限は、相続税の申告期限から原則5年と決まっています。
今回の記事では、相続税の還付を受けるための手続き、流れ、必要な書類、注意点などを詳しく解説します。
Contents
相続税の更正の請求とは?
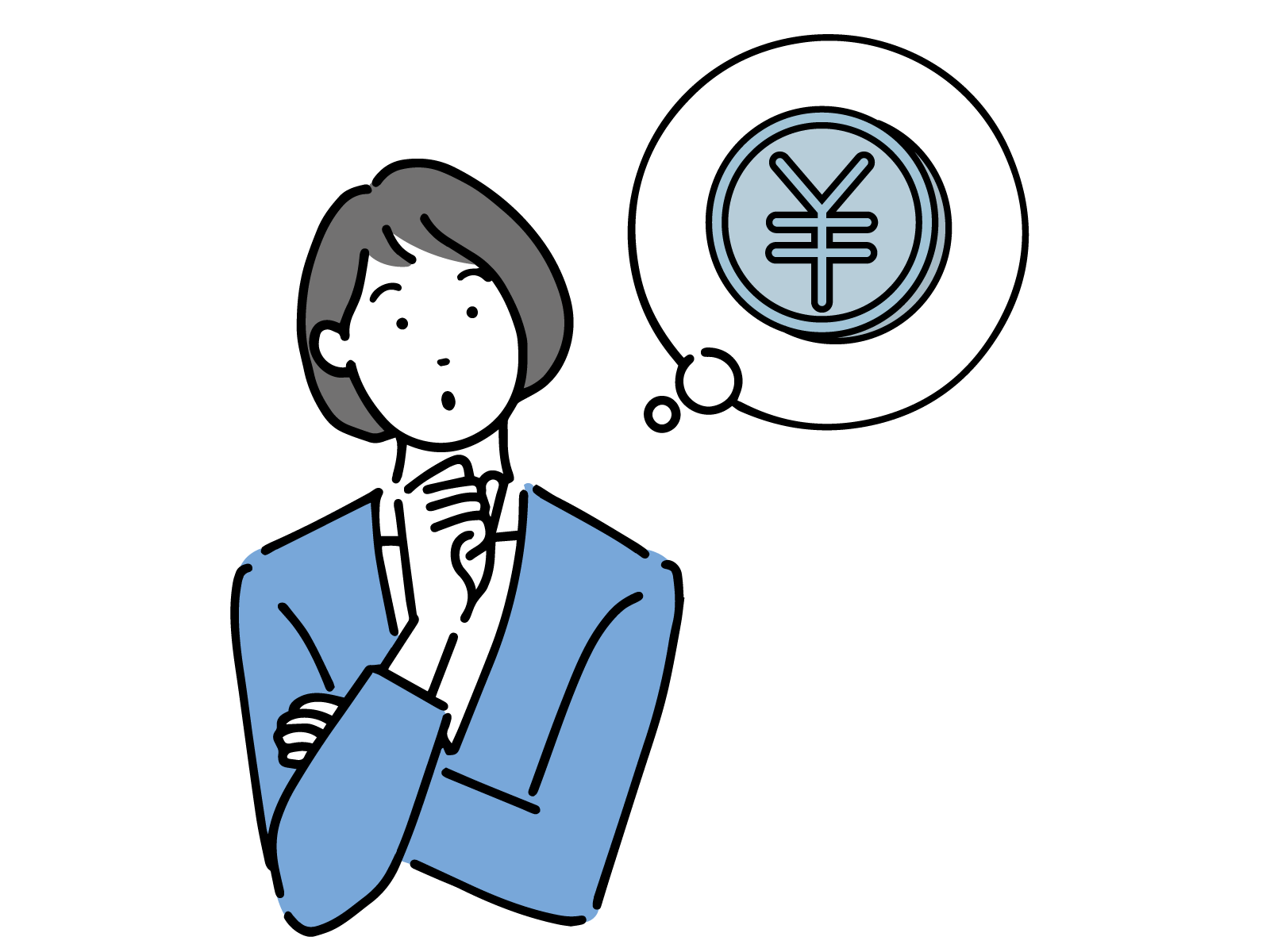
相続税の「更正の請求」とは、相続税申告後に支払った税金が過剰であった場合に、その差額を戻してもらう手続きのことです。
相続税の計算には、不動産や株式の評価、生命保険金の取り扱いなど、非常に多くの要素が関与します。
そのため、申告後に税額の過剰支払いが判明することも珍しくありません。
具体的な要因としては、評価額の誤り、特例の適用漏れ、申告後の状況の変化などがあります。
相続税の還付が発生しやすい要因
①評価額の誤りや見積もり違い
相続税の申告において、最も発生しやすいのが財産評価に関するミスです。
特に、不動産の評価額は専門家でも判断に迷うことが多く、誤って評価額を高く見積もってしまいがちです。
不動産は金額も大きいので、数百万円以上の単位で相続税が変わることもあります。
例えば、土地の評価に際して、近隣の土地価格や市場の動向を反映しきれていないケースなどがあります。
このような場合は、不動産評価額の再評価を行うことで、過剰に納税していた税額を還付してもらうことができます。
②特例の適用漏れ
相続税にはいくつかの税額軽減措置や特例が存在します。
これらの特例は効果も大きい分、適用し忘れてしまうと相続税の額が大幅に上がってしまいます。
期限内であれば、特例の適用に合わせて相続税が減額され、過剰に支払った分が還付されます。
控除や特例の利用漏れが心配な場合は、専門家に依頼して確認してみるのも有効です。
<相続税で使える主な控除や特例の例>
●借家権控除
●未成年者の税額控除
●障がい者の税額控除
●外国税額控除
●贈与税額控除
●相次相続控除
●小規模宅地等の特例※
●配偶者の税額軽減※
※この2つの特例は当初申告時に別途書類を提出してある場合のみ、特例を適用することができます。
③相続税に詳しくない税理士に依頼した
税理士によって得意な分野は異なります。
法人税や所得税などをメインに扱っている場合、相続税はほとんど経験がないというケースも少なくありません。
相続税に詳しくない税理士に依頼した場合、相続財産として計上する必要がない項目を計上したり、財産を過大に評価したりしてしまうことがあります。
税理士に依頼する場合は、しっかり実績や得意分野などを確認するようにしましょう。
④遺産分割が変更された場合
遺言書がない場合などは、相続税の申告に「遺産分割協議」が必要です。
相続税申告は相続発生から10カ月以内に行わなくてはなりませんが、期限内に協議がまとまらないケースもあるでしょう。
その場合、一旦法定相続分で分割したものと仮定して相続税申告をしなくてはなりません。
その後、分割協議してまとまった内容と、当初一旦法定相続分で申告した内容とが違うのであれば、当然税額も変わることになります。
また、未分割の場合には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」といった特例も適用することができません。
但し、申告期限から3年以内に分割協議がまとまり、特例を適用して相続税の再計算を行った結果、相続税の払い過ぎが判明した場合、払い過ぎた税金を還付してもらうことができます。
更正の請求の手続き
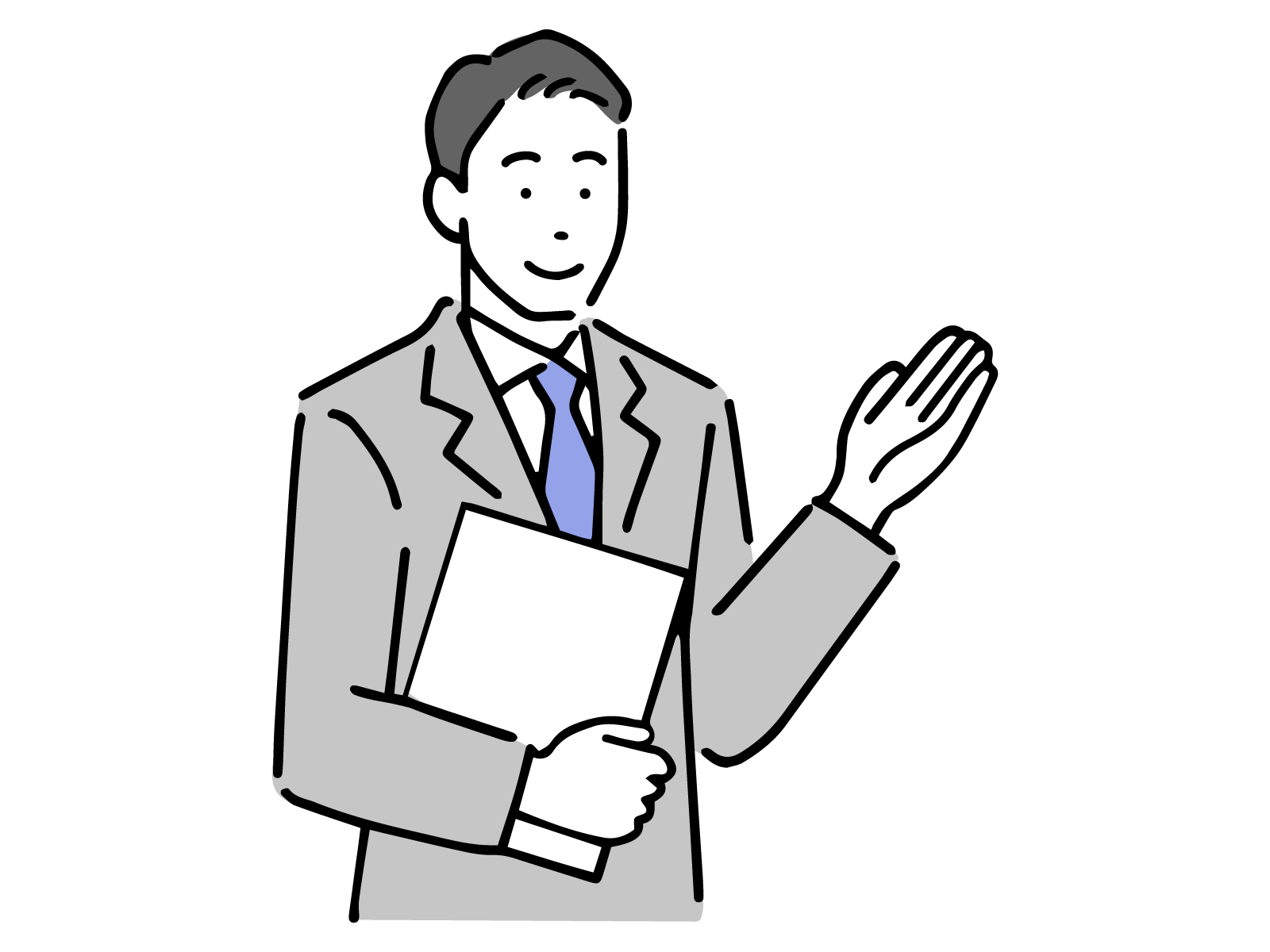
相続税の還付を受けるためには、一定の手続きを踏む必要があります。
以下で、具体的な還付申請の流れと必要な書類について詳しく説明していきます。
①必要な書類を準備する
過剰納税が発覚した場合には、還付申請を行うために準備しなければならない書類がいくつかあります。
スムーズに申請を進められるよう、必要な書類を事前に確認しておきましょう。
| 相続税申告書(過去に提出したもの) | 申告書の内容を見直し、間違いや誤記がないか確認します。 |
| 相続税の更正の請求書と次葉 | 書式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。 更正の請求書やその次葉は、還付を受ける相続人ごとに作成する必要があります。 |
| 更正の請求の必要性を証拠する書類 | 遺産分割協議書や遺言書などの請求する理由を説明するための書類も添付する必要があります。 必要な添付書類が分からない場合は、税務署に問い合わせて確認すると良いでしょう。 |
| 修正申告書 | 参考資料として、当初の申告とどこが変わったかがわかる修正申告書を添付します。 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードなどの本人確認書類も必要です。 |
②必要書類を税務署へ提出
相続税の更正の請求に必要な書類を揃えたら税務署に提出します。
③税務署による審査
税務署は提出された書類を基に再調査を行います。
審査期間の目安は、2〜3か月程度です。
なお審査期間中は、税務署から面談や電話で不明点を確認されることがあります。
追加の情報を求められる場合もありますので、その際は、要求された書類を速やかに提出しましょう。
④「更正通知書」と「国税還付振込通知書」が届き、還付金が振り込まれる
審査の結果、請求が認められると「相続税の更正通知書」が送付されます。
続いて「国税還付金振込通知書」が発送され、指定された口座に還付金が振り込まれます。
国税還付金振込通知書が届いた後は、2週間以内に指定の金融機関口座に還付金が振り込まれます。
⑤更正の請求が認められなかった場合
税務署の審査にて更正の請求が認められなかった場合は「更正すべき理由がない旨の通知書」が税務署から届きます。
もしも結果に納得がいかない場合は、国税不服申立制度を利用することができます。
その際は、税務署への「再調査の請求」または国税不服審判所※への「審査請求」いずれかを選択して申立てを行います。
(※国税に関する処分について審査請求に対する裁決を行う機関)
申立ての期限は、通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内です。
相続税における更正の請求の注意点
①更正の請求を申請できる期限がある
更正の請求には期限があり、相続税の申告期限から5年以内に申請しなければなりません。
相続税の申告期限が10ヶ月なので、相続開始から5年10カ月が請求期限ということになります。
期限を過ぎると還付が受けられなくなるため、相続税の払い過ぎに気がついた場合は、早めに申請手続きを進めましょう。
②申請期限後でも更正の請求を申請できるケースがある
上記の通り、更正の請求には「相続税の申告期限から5年以内」という期限があります。
ですが、後発的に特別な事情が発生した場合は、期限を過ぎていても更正の請求を行うことが可能です。
その場合の期限は、特別な事情が発生した日の翌日から4カ月以内です。
<特別な事情の例>
●分割されていない財産が分割された場合
●分割されていない財産が分割されたことにより軽減や特例が適用される場合
●認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった場合
●遺留分侵害額の請求により支払うべき金額が確定した場合
●遺言書が発見され、または遺贈の放棄があった場合
③税務署は基本的に税金の払い過ぎを教えてくれない
相続税を本来納めるべき額より少なく申告・納税していた場合は、税務署からの指摘を受けることがあります。
ですが、税金を多く納め過ぎていた場合に、税務署からその旨の連絡が来ることはありません。
そのため、自分で確認しなければ、気付かずに多く納め過ぎたままとなってしまいます。
下記のいずれかに当てはまる場合は、一度確認してみると良いでしょう。
●自分で相続税を申告した
●土地や不動産の相続が多かった
●相続税が予想よりも高かった
●依頼した税理士が、どちらかというと「会計」の専門である
●依頼した税理士があまり不動産に詳しくなかった
●土地について、現地調査または役所調査が行われていなかった
●土地を測量した時期が古い
●申告書に公図、路線価図、住宅地図などの付属書類がついていなかった
●遺留分侵害額の請求が発生した
④相続した土地が特徴的だった場合は、評価額に注意する
相続した土地の特徴によっては、評価額を減額することができます。
建物を建てるのに問題がある土地や使い方に困るような土地を相続した場合は、減額できる可能性があるかを確認してみましょう。
<減額できる可能性のある土地の例>
●形がいびつな土地●私道に面している土地
●市街地の田んぼ・畑・山林
●道路に面していない土地
●建物の建築が難しい土地
●傾斜のある土地
●周辺環境が悪い土地
●墓地が隣にある土地
⑤税理士への依頼を検討する
相続税還付を受けるための申請は、非常に複雑で専門的な知識が必要です。
税理士を依頼することで、より正確な申告内容の再調査と書類作成を行うことができます。
税務署とのやり取りも代行してくれるため、手続きにかかる時間や労力を大幅に減らすことができるでしょう。
また、税理士に依頼する際は、還付請求の申請書に税理士名を記載します。
そのため、税理士が再調査・再計算を行っていることで、内容に不備がある可能性が低いと判断されるケースもあります。
まとめ

相続税の還付を受けることで、過剰に支払った税金を取り戻すことができ、相続人の税負担を軽減することができます。
ただし、相続税の還付を受けるためには、過剰納税の発覚から申請手続き、税務署との対応まで、いくつかのステップが必要です。
申請期限も設けられているため、早めに準備を進めることが大切です。
「還付請求の手続きがよくわからない」「税務署とのやり取りが不安」という方は税理士に相談しましょう。
特に、相続税還付が発生する要因は、土地や不動産の相続評価額を実際より高く見積もってしまうことが多いです。
そのため、相談先は相続と不動産両方のノウハウを持つ専門家を選ぶことをおすすめします。
わかば税務会計事務所は、相続と不動産のプロフェッショナルが在籍する「相続手続きに強い」税理士事務所です。
相談から申請まで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。
「相続税を払い過ぎたかも」と気になる方は、お気軽にご相談下さい!