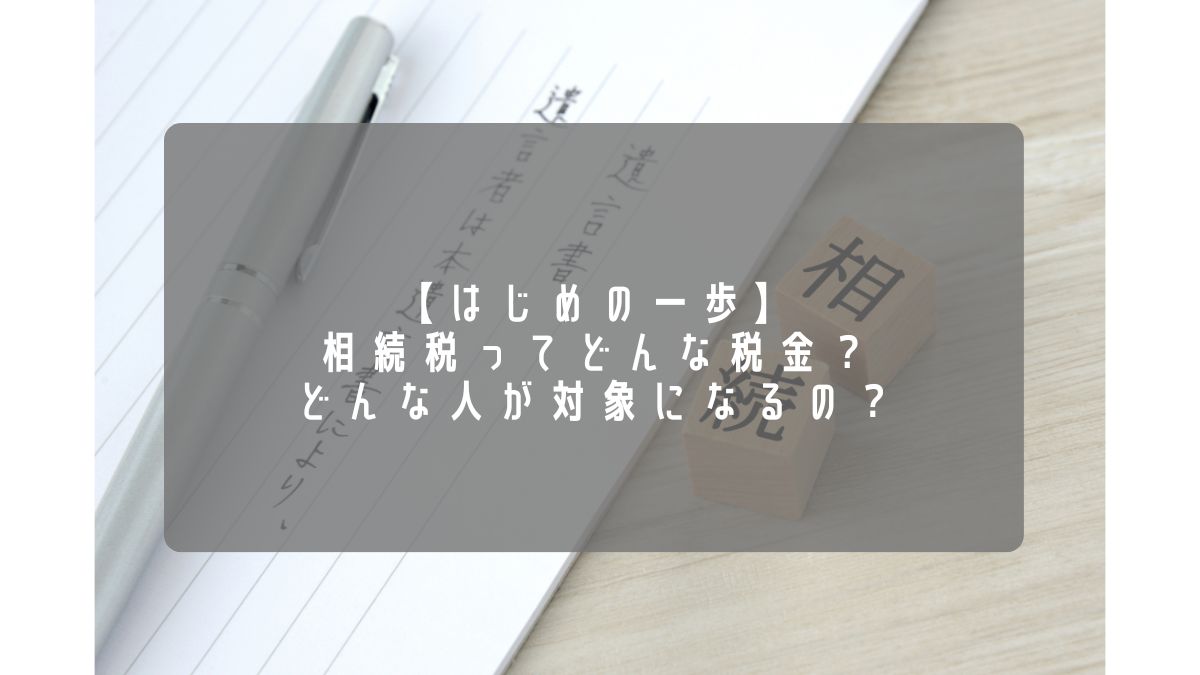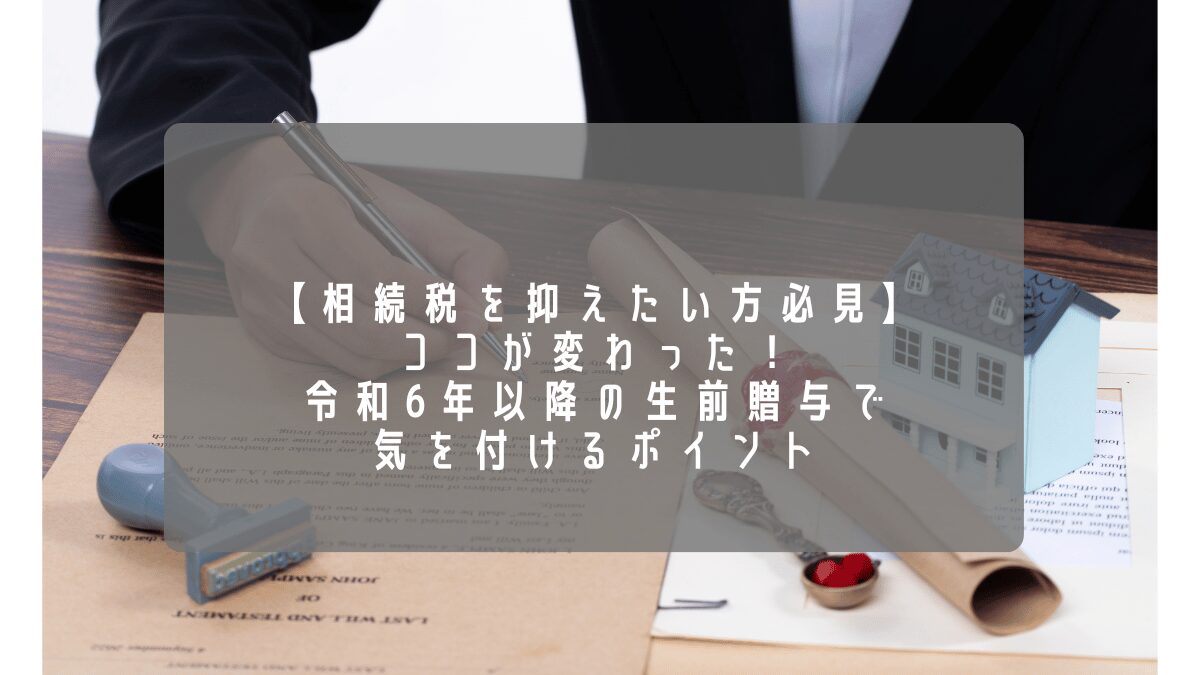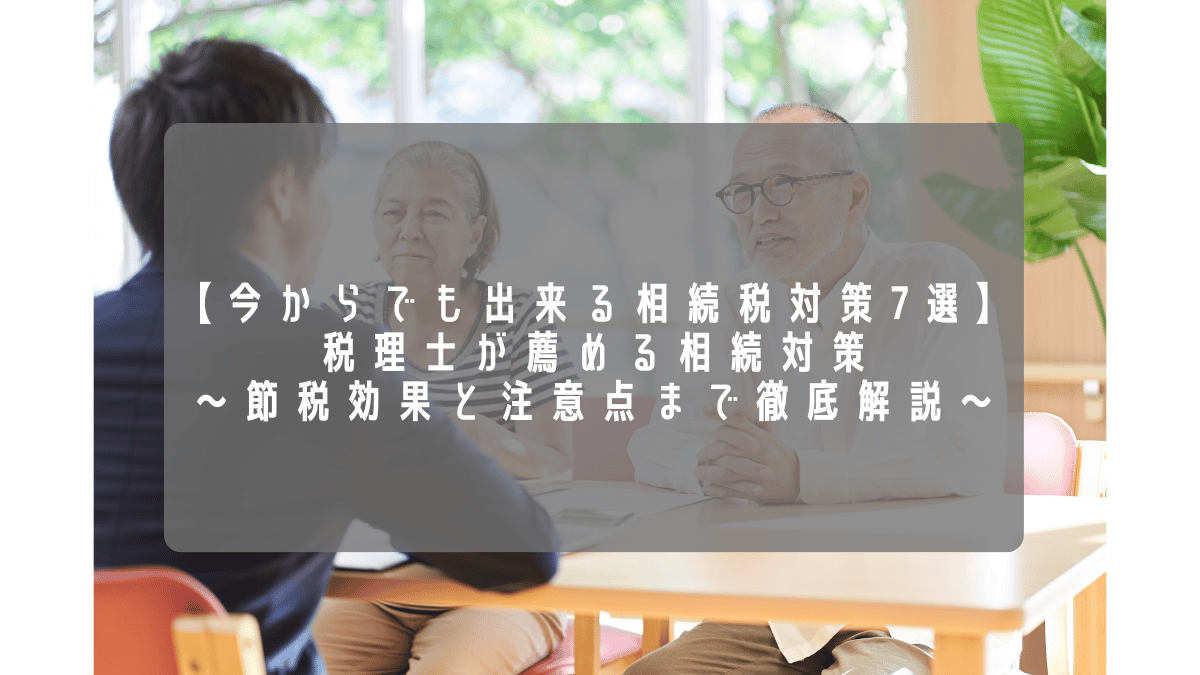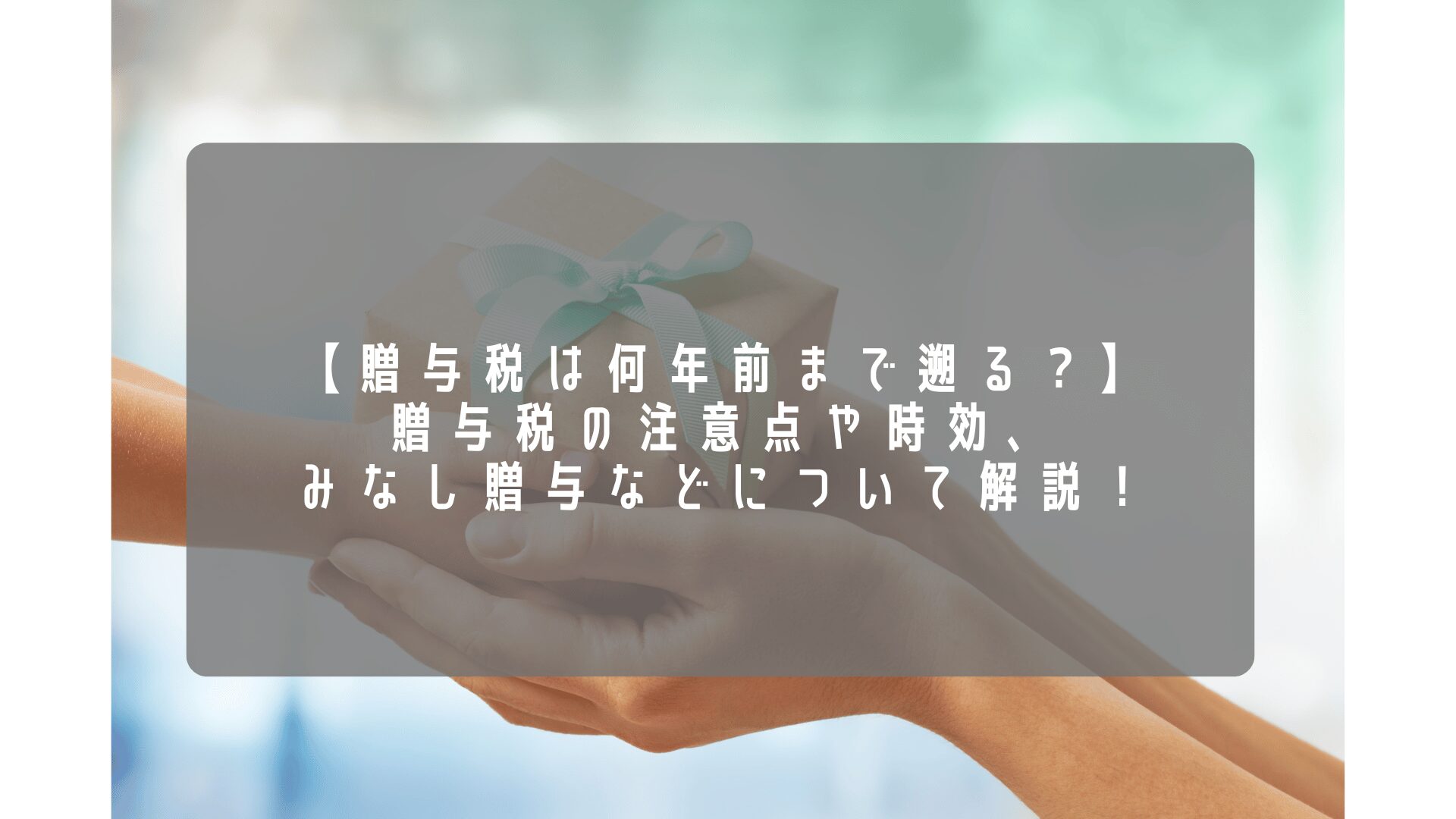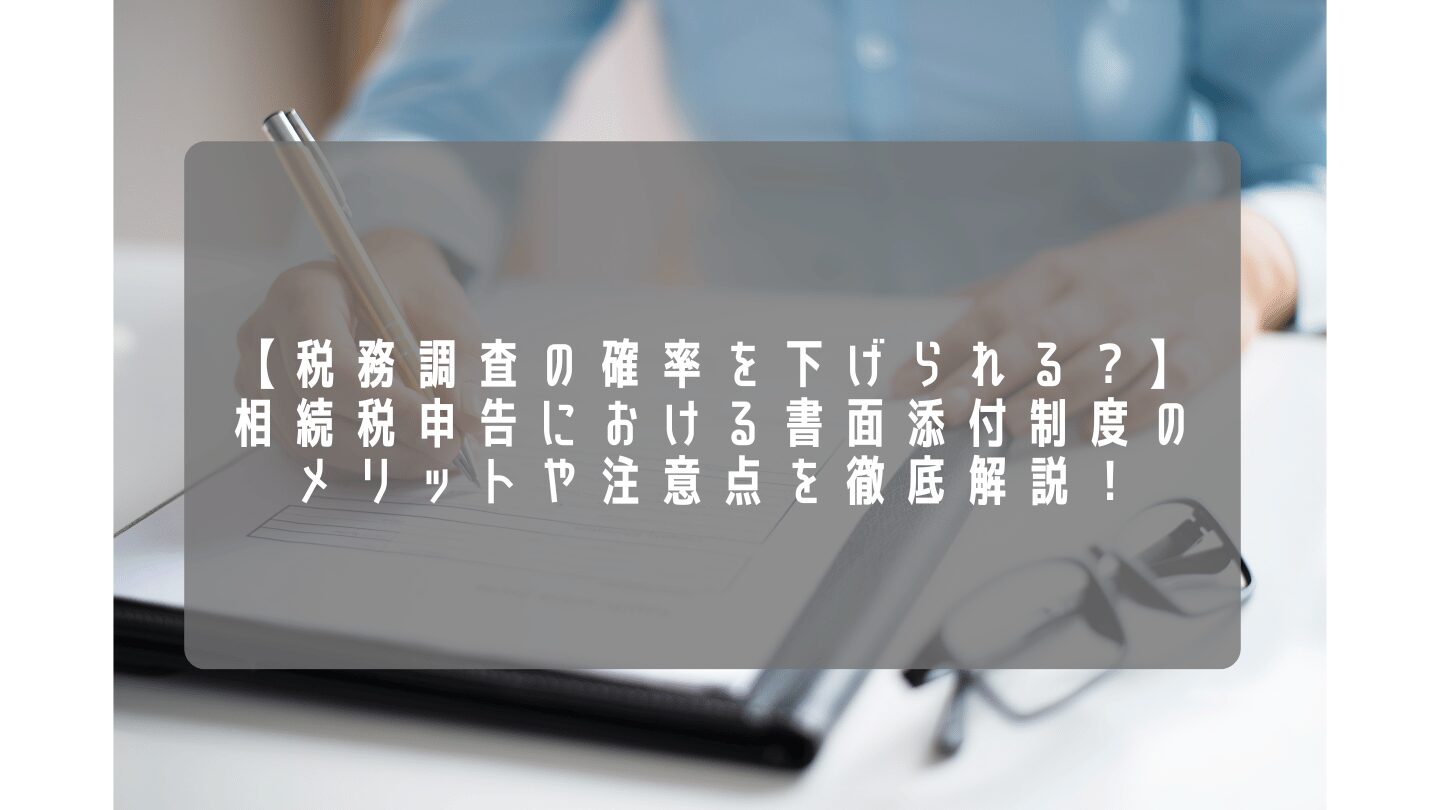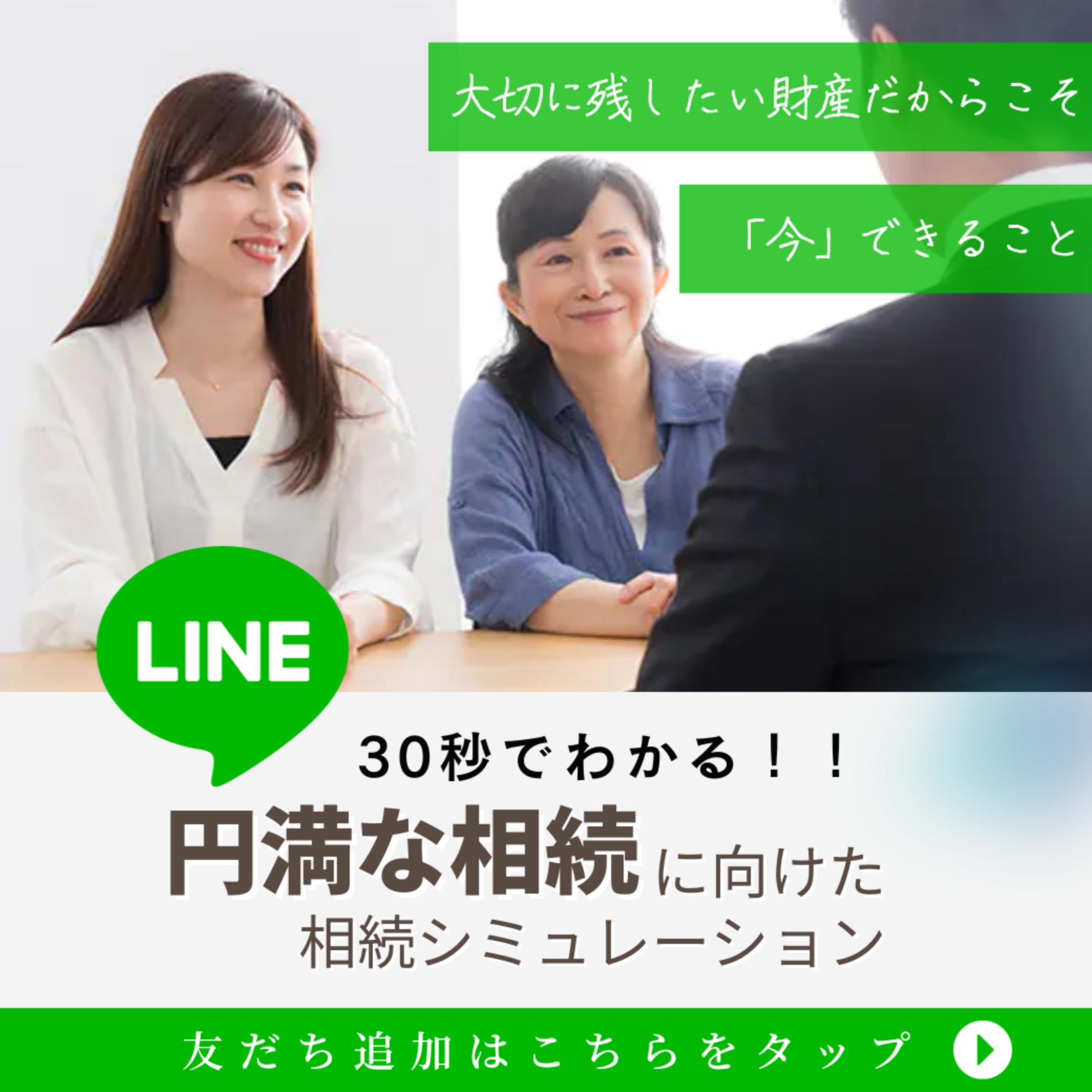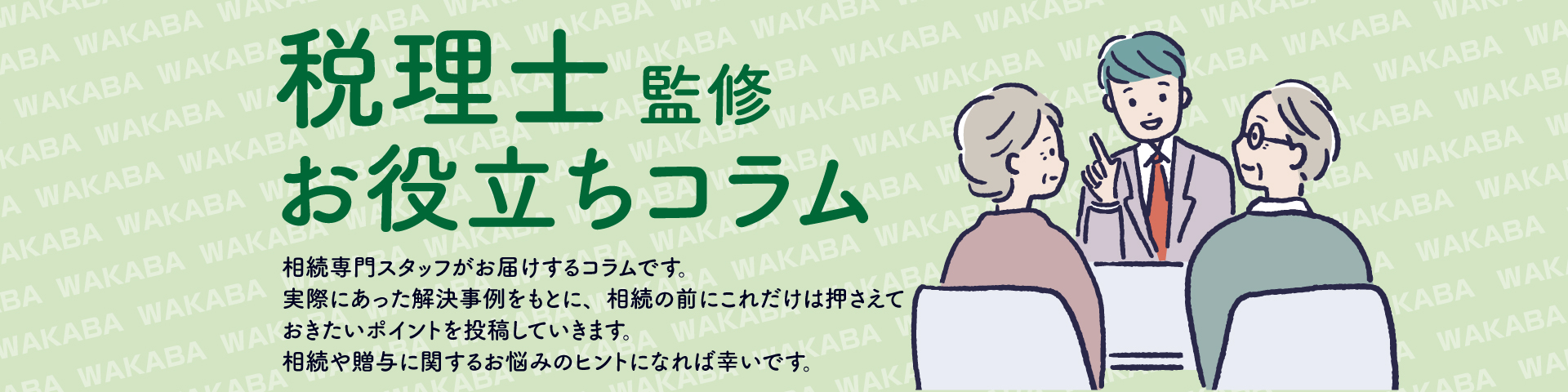
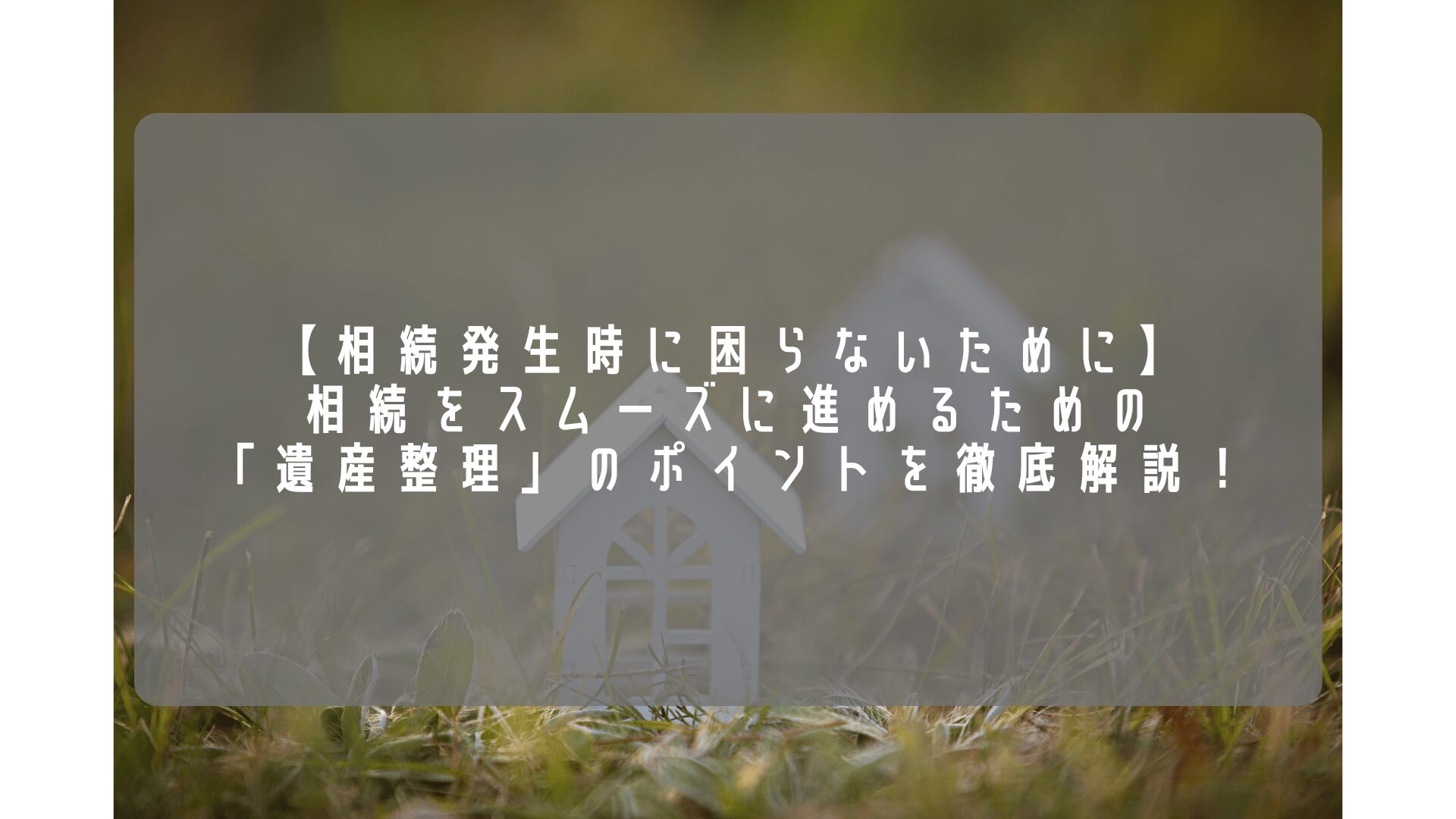
相続が発生した際に、まず行わなくてはならないのが「遺産整理」です。
遺産整理は単なる「財産の片づけ」ではなく、法律や税金なども関わってくる複雑な作業です。
手続きの期限に遅れてしまったり、相続トラブルに発展してしまったりしないよう、適切に進める必要があります。
スムーズかつ円満な遺産整理を行うには、正確な知識と早めの準備が大切です。
今回の記事では、遺産整理の基礎知識から実務の進め方、注意点などを解説していきます。
将来の備えとして、ぜひ確認しておいてください。
Contents
遺産整理とは?

遺産整理とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産や債務を明らかにし、相続人に適切に分配するための一連の手続きです。
単に財産を「分ける」作業ではなく、法的な手続きや税務申告、名義変更なども含まれます。
遺産整理はすべての相続で必要になりますが、特に不動産や金融資産が多い場合、また複数の相続人がいる場合などは重要性が増します。
相続財産に負債が含まれる場合や、遺言書の有無によって手続き内容も大きく変わるため、早期に全体像を把握することが大切です。
遺産整理に関わる主な手続き
主な手続きには、戸籍の収集、財産・債務の調査、遺産分割協議、相続登記、金融機関の解約、相続税の申告などがあります。
これらを抜け漏れなく進めることで、円滑な遺産整理が実現できます。
また、「相続税の申告は相続開始から10か月以内」など、遺産整理には明確な期限が定められているものもあります。
名義変更なども放置すると後のトラブルの元になりますので、可能な限り速やかに行うことが望ましいでしょう。
遺産整理の具体的な進め方
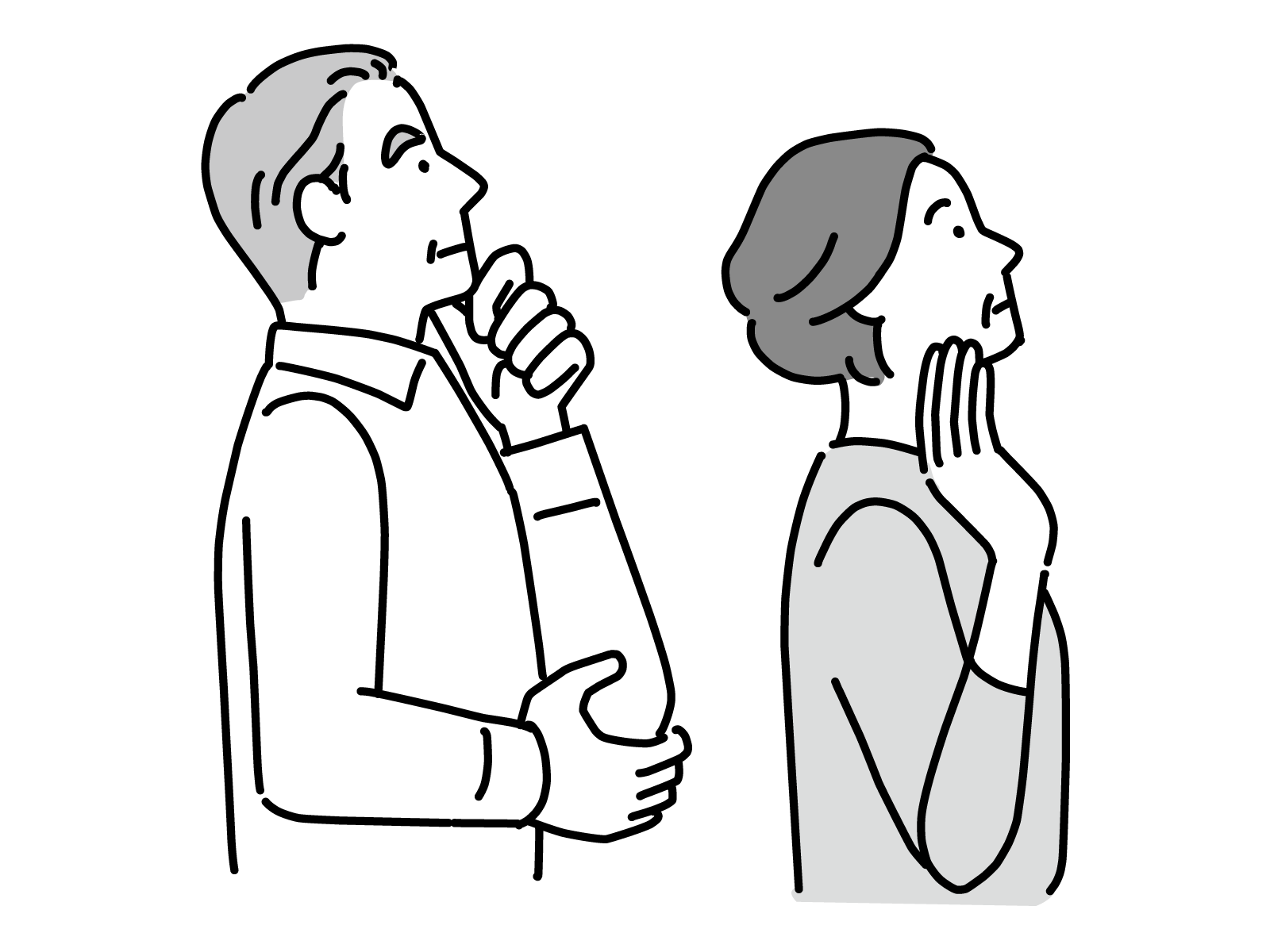
遺産整理は一般的に以下のような流れで進めていきます。
相続に関わる手続きは時間がかかるものも多いため、できるだけ早めに準備を進めるようにしましょう。
遺言書の有無の確認
↓
相続人の調査
↓
相続財産の調査
↓
遺産分割協議によって遺産分割協議書を作成(遺言書があれば、基本的には遺言書通りに)
↓
各種名義変更、遺産分割の手続き
↓
相続税の申告・納付
①遺言書の有無の確認
原則として、遺産相続は遺言書の通りに分割しなければならないため、遺言書の有無は遺産整理の方針に大きく影響します。
後から遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議がやり直しになってしまい、余計な負担が増加してしまいます。
見落としが無いよう、入念に確認しましょう。
また、遺言書は、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書の3種類があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続き(開封手続き)が必要です。
相続人が勝手に開封してしまうと、ペナルティが課せられてしまう可能性もあるため注意しましょう。
但し、自筆証書遺言であっても、遺言保管制度を利用して法務局で保管されている場合は検認手続きが不要となります。
公正証書遺言は公証役場で確認することができます。
②相続人の調査と確定
遺言書がない場合や遺言書の内容とは別の分け方にしたい場合は、相続財産を相続人全員でどう分割するかを話し合う「遺産分割協議」を開くことになります。
遺産分割協議は、法定相続人が1人でも欠けていると無効となってしまいます。
そのため、まずは誰が法定相続人なのかを確定させる必要があります。
相続人は、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を集めて確認します。
兄弟姉妹や代襲相続人が関与する場合は、より広範な戸籍調査が必要です。
③相続財産の調査
次に行うのが、相続財産の調査です。
被相続人の遺産を整理し、遺産目録を作成します。
預貯金、不動産、有価証券、保険、負債など、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も把握することが大切です。
全体像が明らかになることで、相続放棄の判断材料にもなります。
相続放棄は自分に相続権があることを知ってから3カ月以内に行う必要があるため、早めに行動しましょう。
具体的には、以下のような内容を確認していきます。
その他、郵便物なども大きな手掛かりとなります。
| 銀行 | 残高証明書の取得 取引履歴の確認 |
| 証券会社 | 保有資産明細書の確認 取引履歴の確認 |
| 生命保険 | 加入状況の確認 |
| 自動車 | 現在価格の査定 |
| 不動産 | 固定資産評価証明書の取得 路線価の確認 利用状況の把握 |
| その他の不動産、金融資産、出資金など | 現在価格の査定 残金、返戻金等の確認 |
④遺産分割協議の実施
相続人全員で話し合い、財産の分け方を決めるのが遺産分割協議です。
協議の結果は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員が署名押印する必要があります。
トラブルを防ぐためにも、事前にしっかりと調整を行いましょう。
協議中の争いを回避するため、専門家に同席を依頼することも有効です。
どうしても協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
遺産分割調停では、調停委員が相続人の間に入って協議を進めていきます。
それでも解決しない場合、自動的に「遺産分割審判」に移行します。
各相続人が主張や立証を行い、それに基づいて裁判所が下した審判内容に沿って相続手続きを進めることになります。
⑤名義変更や解約手続き
協議が成立したら、預貯金の解約や不動産の相続登記、株式の名義変更などの手続きを行います。
これにより、形式的にも相続財産が各相続人のものとなります。
株、証券、不動産などは分割のやり直しが難しいため、慎重に手続きを行いましょう。
また、不動産の場合は「相続登記」の手続きが必要になります。
放置すると売却などの手続きが複雑になり、後々トラブルになることもあるため早めに登記を行うことをおすすめします。
<相続登記に必要な書類>
●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本
●被相続人の住民票の除票
●相続人全員の印鑑証明書
●不動産を相続した相続人の住民票
●固定資産税の課税明細書または固定資産評価証明書
●遺言書、または遺産分割協議書
⑥相続税の申告・納付
相続財産の額によっては、相続税の申告・納付が必要になります。
相続税の支払いが発生するのは、葬儀費用や負債を差し引いた相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合です。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で計算できます。
(相続税の基本については、こちらの記事でも紹介しています:https://zeimu-wakaba.com/15/)
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。
加算税や延滞税などのペナルティが発生する恐れもあるため、申告手続きは期限内に正確に行いましょう。
相続の方法
相続が発生すると、相続人は財産をどう受け継ぐかを選択する必要があります。
相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
それぞれに特徴や注意点があり、後々のトラブルや負債の引き継ぎにも関わるため、内容を正しく理解して状況に合った方法を選びましょう。
| 単純承認 | 単純承認とは、被相続人の財産も負債もすべてを引き継ぐ方法です。 何も手続きをしなかった場合も、原則として単純承認したとみなされます。 預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続するため、事前にしっかりと財産内容を確認することが大切です。 |
| 限定承認 | 限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法です。 相続人全員の同意が必要で、家庭裁判所への申述も求められます。 プラスの財産の中からマイナスの財産を清算し、残れば相続人が取得する形です。 借金の有無が不明な場合に有効な選択肢となります。 |
| 相続放棄 | 相続放棄は、財産も負債も一切相続しない方法です。 相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 借金が多い場合に選ばれることが多く、一度放棄をすると撤回はできません。 判断に迷う場合は、早めに専門家に相談するのがおすすめです。 |
遺産整理に関わる手続き期限
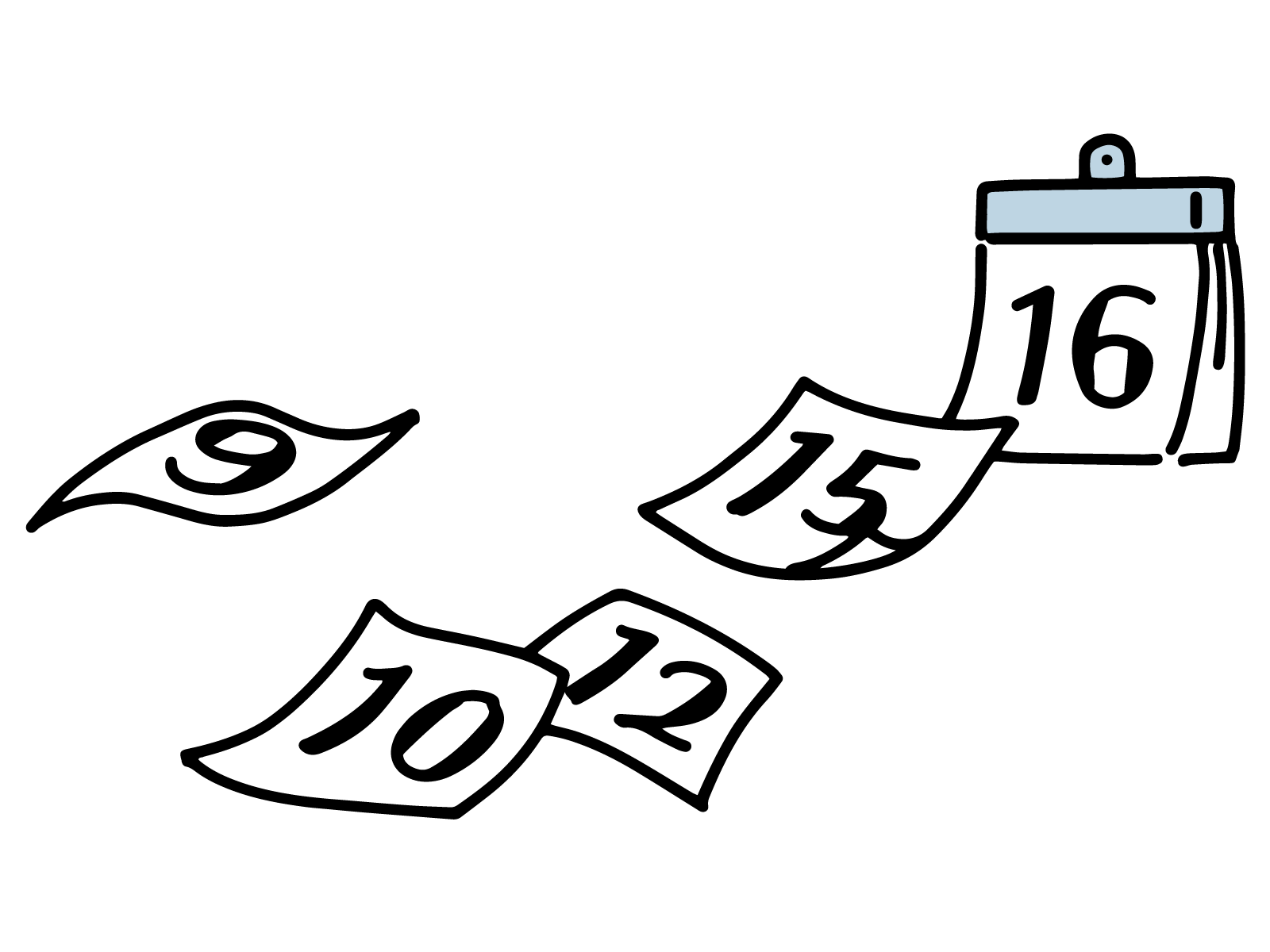
相続が発生すると、さまざまな手続きを進める必要がありますが、それぞれに期限が設けられているものも多くあります。
期限を過ぎてしまうと不利益を被る場合もあるため、早めの把握と行動が重要です。
例としては、以下のような手続きがあります。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は、被相続人の死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。
医師による死亡診断書または死体検案書と一緒に提出します。
死亡届を提出しなければ火葬許可証を発行できず、葬儀も行えないため、最優先で対応すべき手続きです。
相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄または限定承認の手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
期限を過ぎると単純承認とみなされてしまうため、負債の有無などを早めに確認することが重要です。
準確定申告(4か月以内)
被相続人が個人事業主だったり、不動産収入などを得ていたりした場合は、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を申告する「準確定申告」が必要です。
期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内となっており、相続人が連名で申告します。
相続税の申告・納付(10か月以内)
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
基礎控除額を超える相続財産がある場合は、税務署への申告が必要となります。
納付は原則現金一括納付ですが、条件により延納や物納も可能です。
遺留分侵害額請求(1年以内)
遺留分侵害請求は、遺言などで不公平な分配がされた場合などに活用される手段です。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に請求を行う必要があります。
また、相続開始から10年を経過すると請求権が時効により消滅します。
相続登記(3年以内)
不動産の相続登記は、2024年4月から義務化され、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。
正当な理由なく怠ると過料(最大10万円)の対象となります。
遺産整理をスムーズに進めるためのポイント
専門家に早期相談する
遺産整理には法律・税務・不動産など多岐にわたる専門知識が求められます。
専門家に早期に相談することで、スムーズでトラブルの少ない相続を実現できます。
相続人同士の信頼関係を大切にする
相続における大きなリスクの一つは、相続人同士の感情的対立です。
公平さに欠ける分割案、財産の偏り、意思疎通不足が原因になるケースは多いでしょう。
相手の立場や気持ちに配慮し、冷静に協議を進める姿勢が大切です。
事前に「生前整理」を行っておく
被相続人が元気なうちに、生前整理を行っておくことは非常に有効です。
財産の一覧作成、不要な資産の整理、遺言書の作成などにより、遺族の手間を大幅に軽減することができます。
また、早期に財産調査と証拠の保全を行えることで、一部の相続人が財産を勝手に引き出したりするトラブルの回避にもつながります。
財産目録をしっかり作成する
資産評価や税額試算のベースになる財産目録は、相続手続きを進める上での基本資料です。
網羅性と正確性の高い目録があれば、協議も税務対応も円滑に進みます。
また、相続税申告における申告漏れや評価誤りは、税務調査の対象になる可能性があります。
正確な財産評価と根拠資料の整備、専門家によるチェックも交えながら丁寧に作成しましょう。
まとめ

遺産整理というと「手続き」「申告」「名義変更」といった事務的な側面に目が向きがちですが、本質的には“家族の歴史を振り返る作業”です。
財産を整理する過程で、家族が顔を合わせ、これからについて話し合える機会も遺産整理の大切な副産物といえるでしょう。
ただし、相続は感情と法律が入り混じる複雑な領域です。
トラブルを未然に防ぐためにも、事前準備が非常に大切です。
問題が顕在化する前に対応しておくことで、いざという時に冷静かつ適切に行動できるようになります。
「うちはまだ早い」と思わずに、できることから着実に進めておきましょう。
また、不安や疑問を感じている場合は、信頼できる専門家に「事前相談」してみることも有効です。
当事務所では、実務経験豊富な専門家が不安な気持ちに寄り添いながら、確実かつ丁寧に相続のサポートを行います。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」という些細なことでも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。