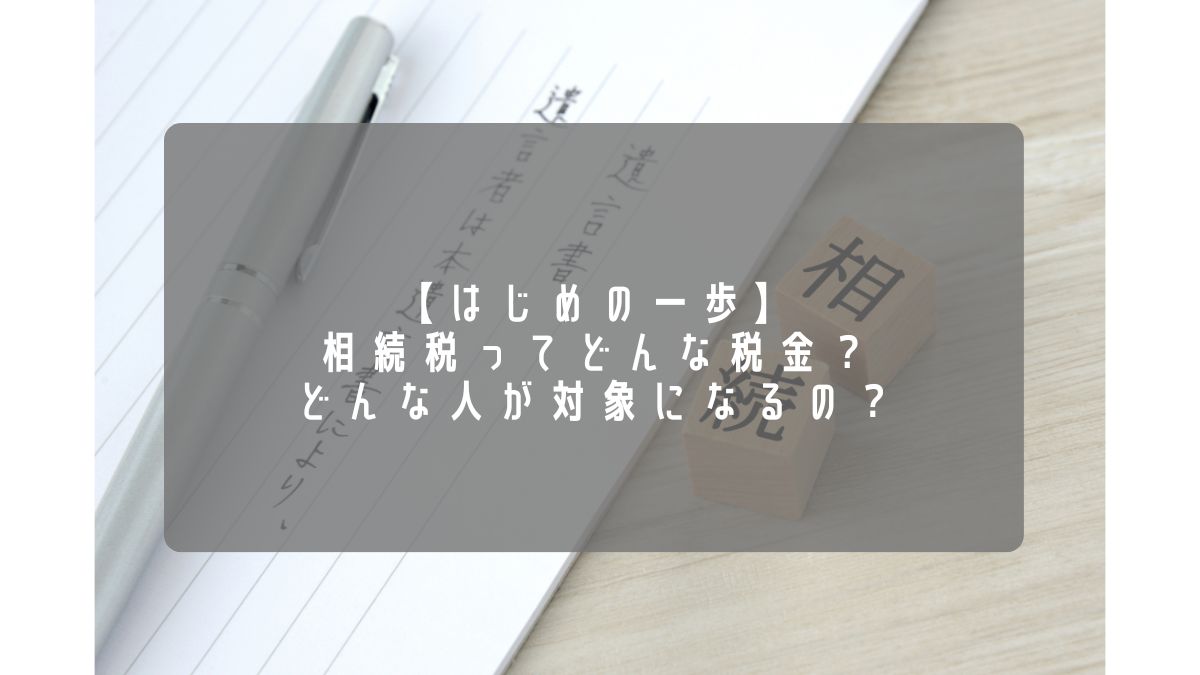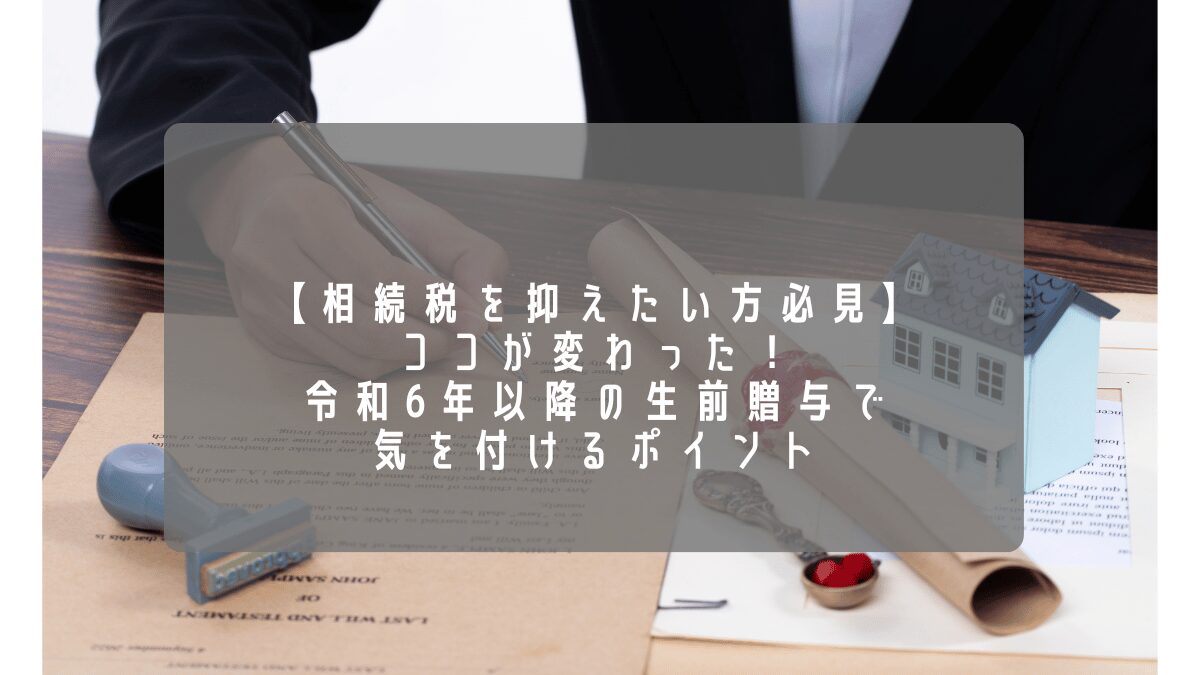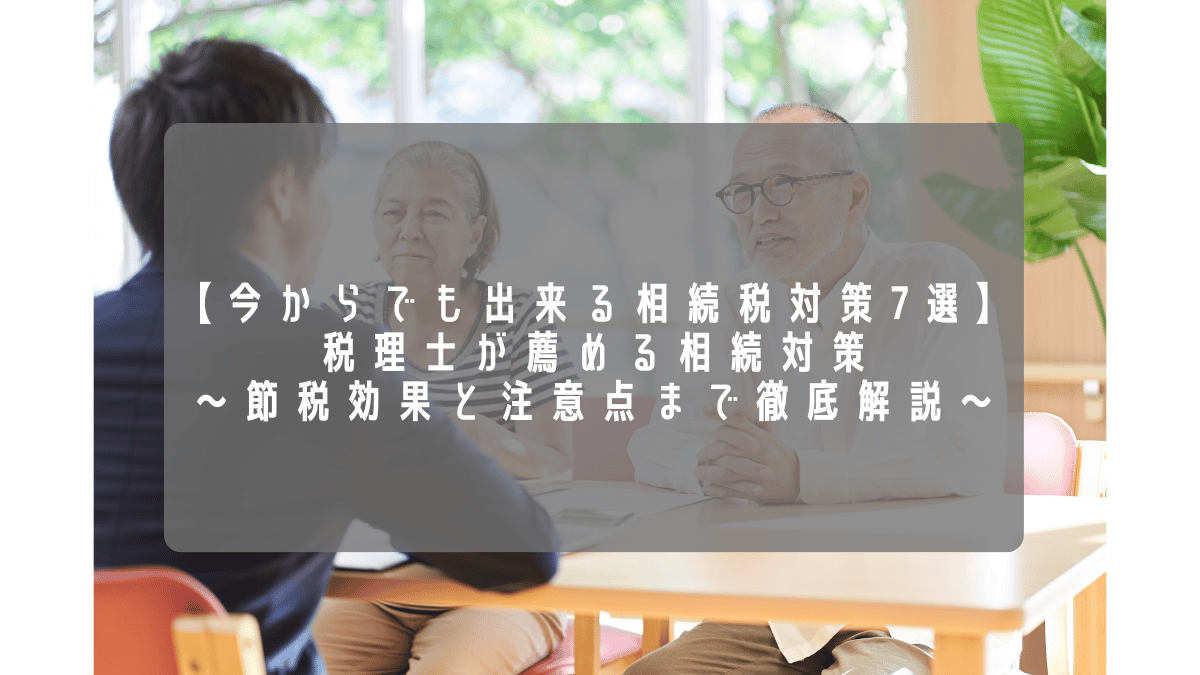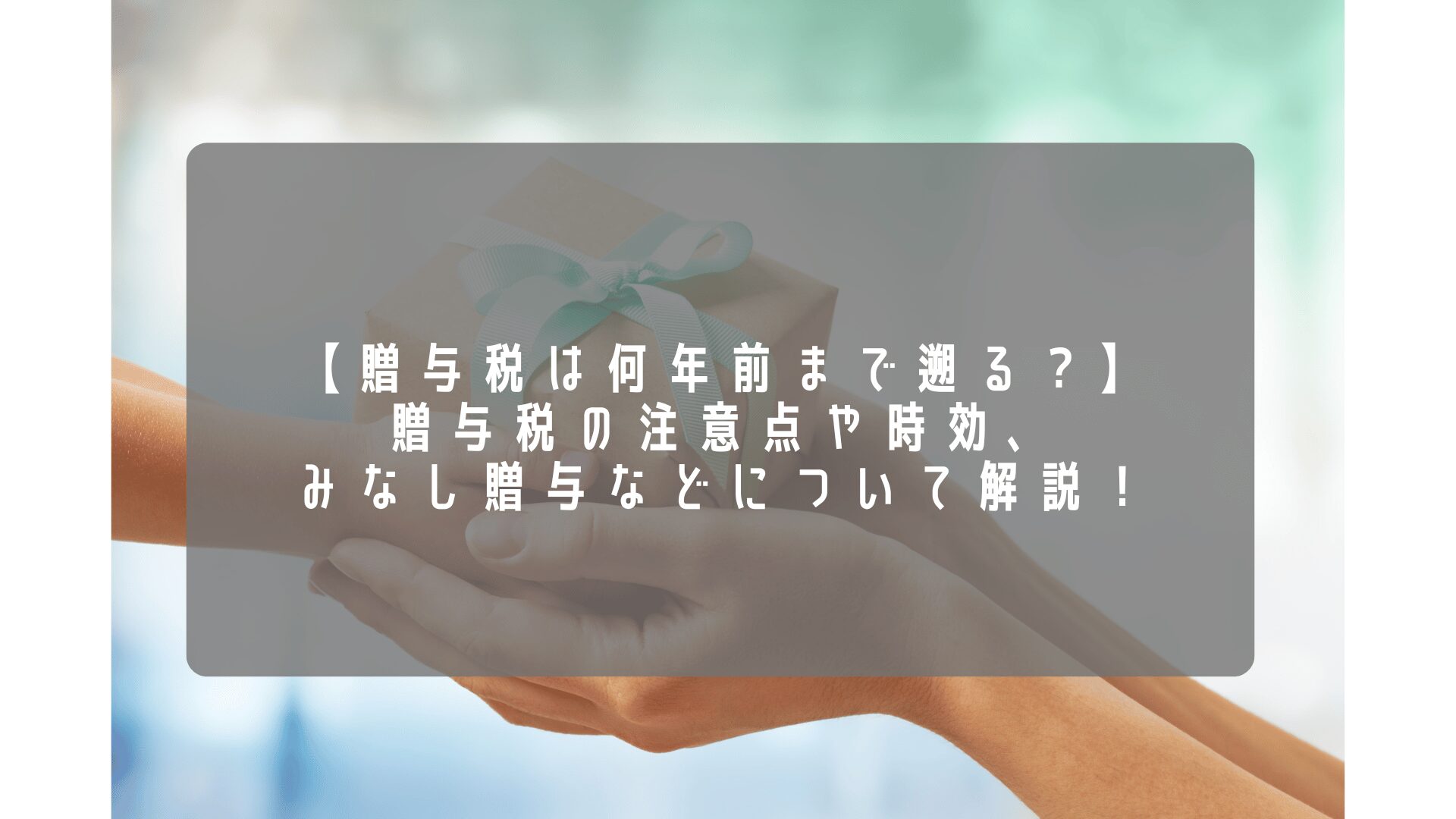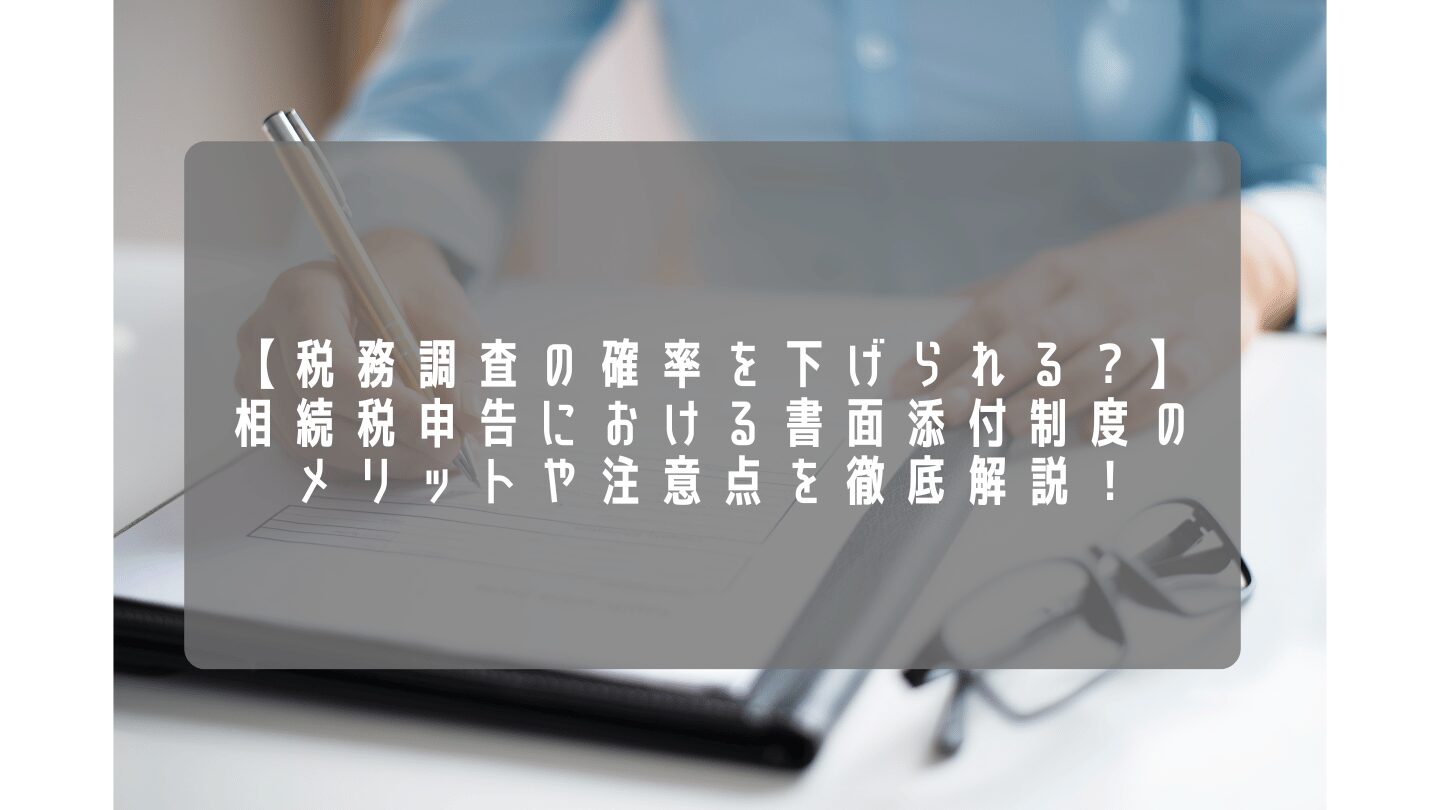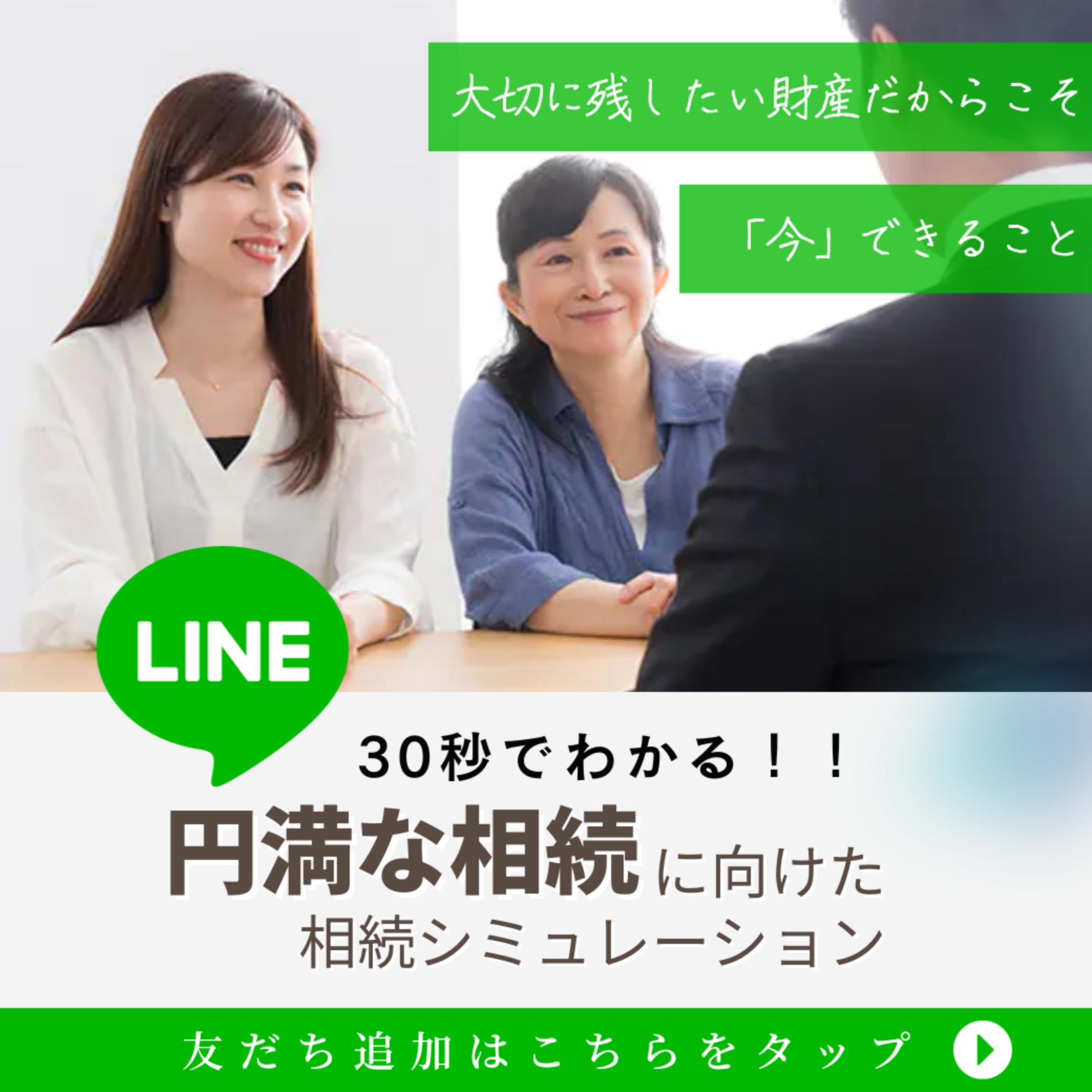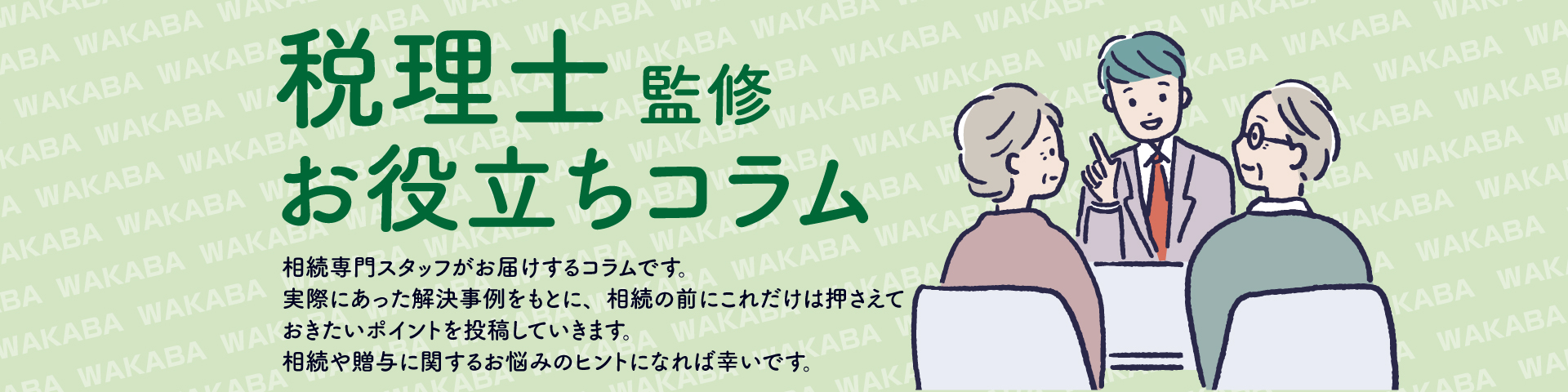
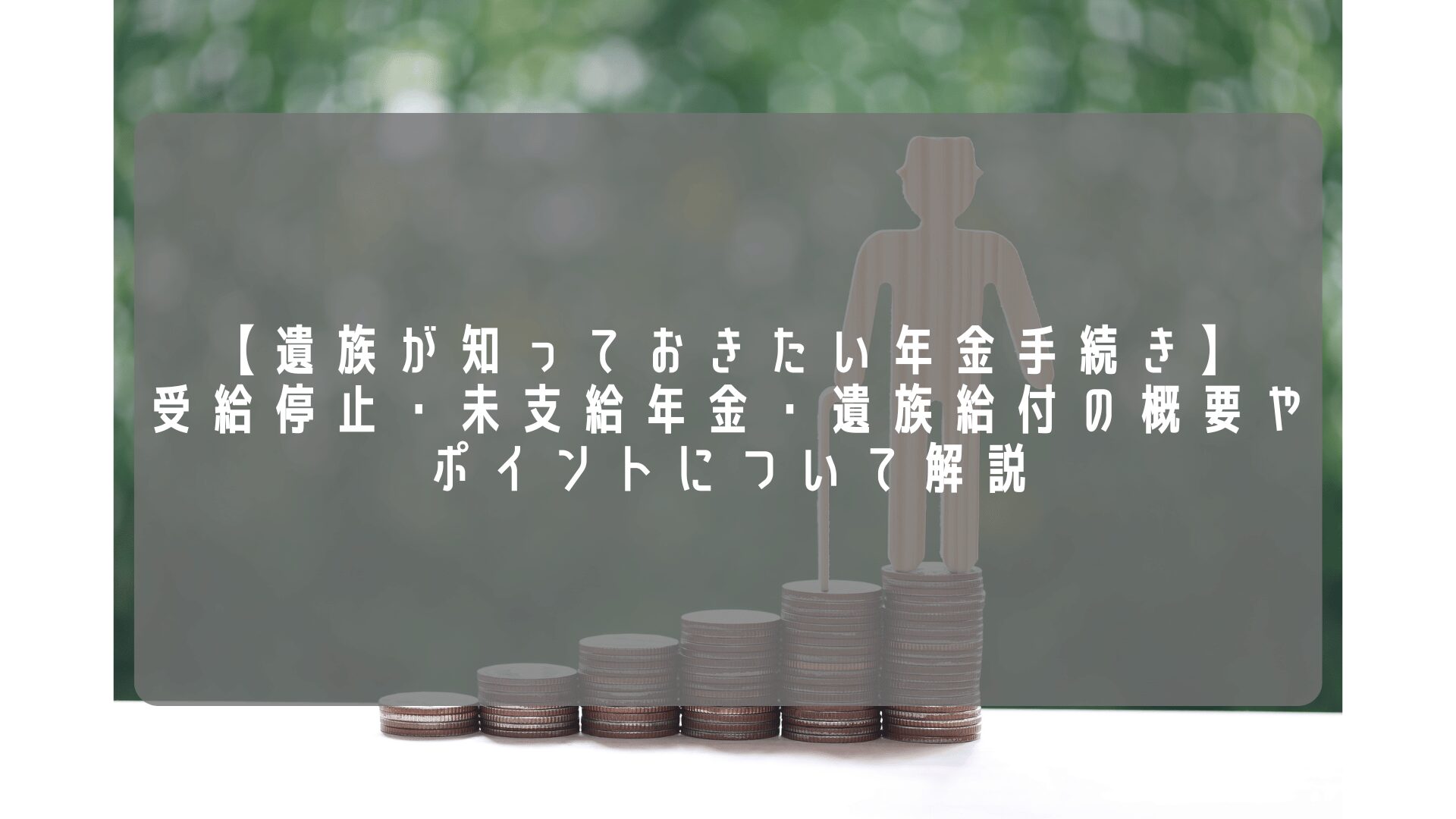
相続が発生すると、短期間で多くの手続きを進めなければならなくなります。
遺産分割や税金の申告、名義変更など、必要な手続きは多岐にわたります。
そのなかでも「年金受給の停止手続き」は、忘れてしまいがちなものの一つです。
亡くなった方が公的年金を受給していた場合、死亡の事実を届け出て支給を止める必要があります。
この手続きを怠ると、死亡後も年金が振り込まれ続けることがあり、それは「過払い」として後日返還請求を受けることになります。
場合によっては、加算金や利息を求められることもあるため、早めの対応が欠かせません。
一方で、故人が受給できたはずの年金のうち、未支給分を遺族が請求できる「未支給年金」や、条件を満たせば受け取れる「遺族年金」など、プラスの側面もあります。
正しく手続きを行えば、遺族の生活を支える大切な資金を受け取ることが可能です。
本記事では、「年金受給停止の手続き」を中心に、期限・方法・注意点などを詳しく解説します。
併せて、未支給年金や遺族年金など、相続後に知っておきたい制度のポイントも整理しますので、参考にしてみてください。
Contents
年金受給停止とは

年金受給者が亡くなった際には「年金受給終了の手続き」を行い、年金受給を停止する必要があります。
日本の公的年金制度は受給者本人の生存を前提としており、死亡により受給権は消滅します。
ですが、年金記録にマイナンバーが登録されていない場合や、自治体から日本年金機構への情報連携が遅れた場合など、死亡後も年金が振り込まれるケースがあります。
※マイナンバーが登録されているかは、「ねんきんネット」で確認できるほか、お近くの年金事務所で確認できます。
死亡後に振り込まれた年金は「不正受給」とみなされ、返還の対象となります。
死亡後に年金が自動的に停止されると誤解されがちですが、原則は遺族が手続きを行う必要があるのです。
日本の公的年金には、以下の種類があります。
国民年金(老齢基礎年金・障害基礎年金など):自営業者や無職の方などが加入
厚生年金(老齢厚生年金・障害厚生年金など):会社員や公務員などが加入
共済年金(現行は厚生年金に統合):旧公務員制度
また、その他の厚生年金基金や確定給付企業年金などの私的年金制度も、契約や制度ごとに独自の規定があり、別途手続きが必要です。
年金受給停止の手続き方法
手続きの期限
公的年金の受給停止手続きには、期限が定められています。
国民年金は受給者の死亡日から14日以内、厚生年金(共済年金)は受給者の死亡日から10日以内です。
期限が非常に短いため、早めの確認と手続きが重要です。
手続きの期限を過ぎてしまい、過払いが発生した場合には返還請求を受ける可能性があります。
手続き先
公的年金における受給停止手続きは、日本年金機構の年金事務所または街角の年金相談センターで行います。
年金事務所の窓口は混雑していることがありますので、あらかじめ予約をしておくか、余裕を持って来所することをおすすめします。
また、年金事務所や年金相談センターが遠方である、または事情があり足を運べないなどの場合は郵送での手続きも可能です。
郵送での年金受給停止の手続きを希望する場合は、基礎年金番号を確認し「ねんきんダイヤル」まで問い合わせましょう。
手続きに関する不明点なども問い合わせることが可能です。
必要書類
年金受給停止のために必要となる主な書類は次のとおりです。
年金受給権者死亡届のフォーマットは、年金事務所もしくは日本年金機構のWebサイトから入手できます。
また、書類を準備する際に、基礎年金番号が必要になります。
被相続人の「年金証書」や「基礎年金番号通知書」、「年金手帳」、それらも見つからないときは、「年金振込通知書」や「改定通知書」から基礎年金番号を確認します。
それでも、基礎年金番号がわからない場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせてみましょう。
①亡くなった方の年金証書
②年金受給権者死亡届(報告書)
③死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
・住民票除票
・戸籍抄本
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
年金受給停止の手続きを省略できるケース
マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、日本年金機構が自動的に死亡情報を把握するため、原則として届出を省略することができます。
ただし、すべてのケースで自動停止が保証されるわけではないため、年金証書や通知書を確認し、念のため窓口に問い合わせると安心です。
また、この場合でも未支給年金や遺族年金の請求は別途行う必要がある点には注意しましょう。
未支給年金の請求
未支給年金とは

年金受給者が亡くなった時点までに本来支給されるはずだった未払いの年金を、生計を同一にしていた遺族が請求できる制度です。
公的年金の給付は、偶数月の15日に前月と前々月の分が振り込まれるようになっています。
後払いの形になっているため、受給者がいつ亡くなっても必ず未支給年金が発生します。
その未支給分は遺族が受け取って良いことになっています。
ただし、未支給年金は「相続財産」には含まれず、受取人の一時所得として扱われる点には注意が必要です。
未支給年金の請求手続き
未支給年金は、自動的に遺族に支給されるわけではありません。
年金事務所または街角の年金相談センターに、「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する必要があります。
<必要書類>
●亡くなった方の年金証書
●亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
●亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)
●受け取りを希望する金融機関の通帳
●亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
※戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
請求できる人の範囲と順位
亡くなった当時、生計を同じくしていた遺族に限られ、順位は次のとおりです。
先順位者がいる場合は、後順位者は請求を行うことができません。
同順位者が複数であれば、代表者が一括して請求を行います。
①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦上記以外の三親等内親族
未支給年金の請求期限
支払いを受ける権利は、原則5年で時効消滅します。
期限は比較的長いですが、油断していると請求手続きを忘れてしまう可能性もあります。
そのため、年金の受給停止申請のタイミングで一緒に手続きを済ますことがおすすめです。
その他の遺族給付
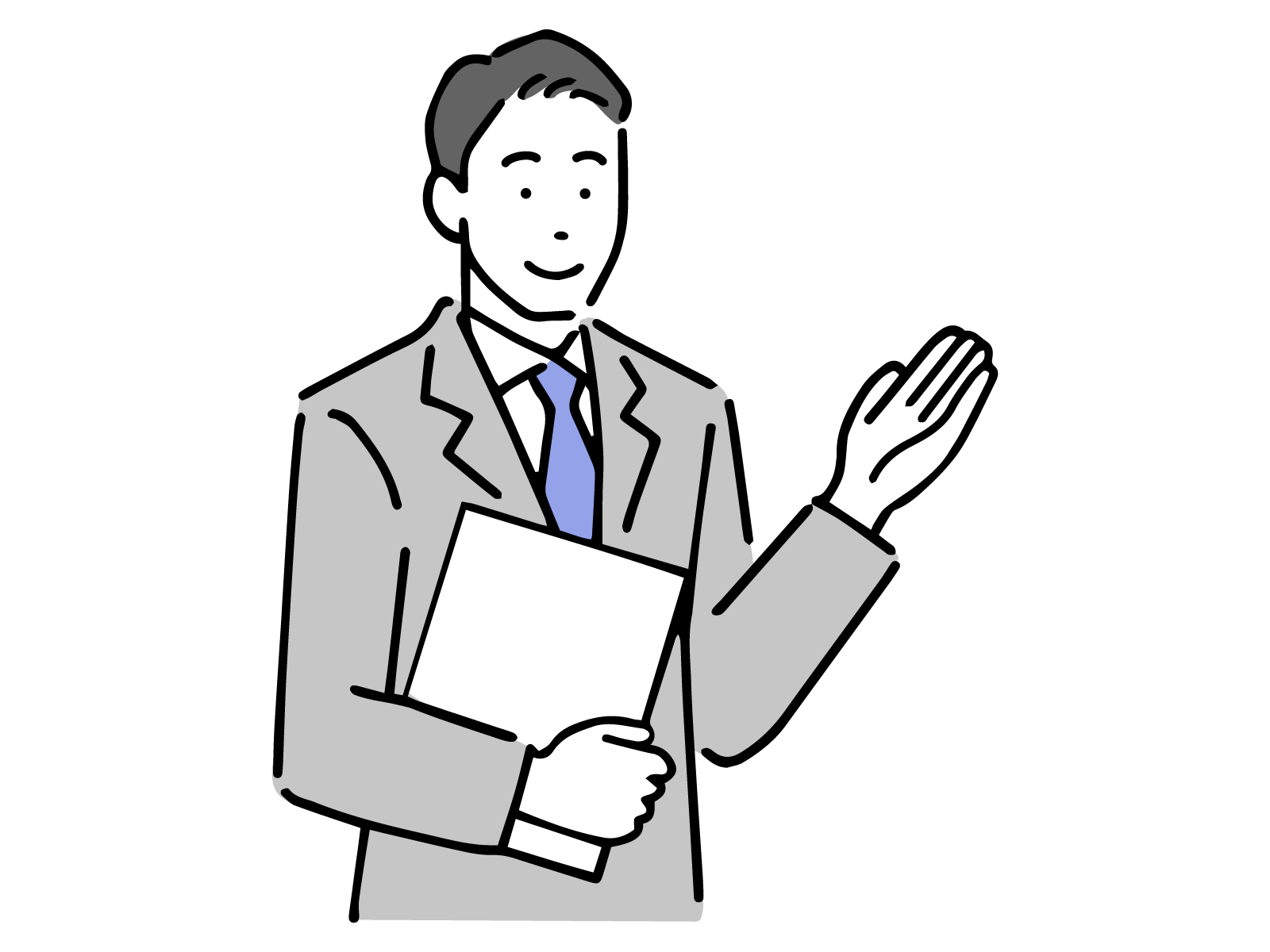
未支給年金以外にも、亡くなった方の加入歴や家族構成によって、遺族が受け取れる給付があります。
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金などが代表的です。
生活を支える大切な資金となるため、対象となる場合は漏れなく手続きするようにしましょう。
ただし、すべて同時に受け取れるわけではなく、制度によって「選択」や「併給調整」のルールがあります。
どの制度が最も有利かは、加入期間や家族構成によって変わるため、事前にしっかり確認するようにしましょう。
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
遺族年金は、亡くなった方が国民年金や厚生年金などに加入していた場合、一定の要件を満たした遺族に支給される年金です。
「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、年金の加入歴や家族構成により受給できる制度が異なります。
また、遺族年金は税法上非課税です。
| 遺族基礎年金 | 国民年金の被保険者が亡くなった場合に、子どもの養育のためのお金として受給することができます。 そのため、対象者は「18歳到達年度末まで、または20歳未満で1・2級の障害状態」の子供がいる配偶者、もしくは子供本人です。 年金額は「780,100円+子の加算」となっていて、子の加算は、第1子・第2子がそれぞれ224,500円、第3子以降はそれぞれ74,800円です。 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金の被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たしていた場合に受給できます。 年金額は、夫が受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3までです。 遺族厚生年金は、子供がいない配偶者や、父母・祖父母なども受給する資格がありますが、それぞれ要件が定められています。 また、一定の条件を満たしていることで、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」などの上乗せを受けることができる場合もあります。 |
遺族年金の手続き
遺族年金も自動ではなく、遺族が請求書を提出する必要があります。
届出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。
必要書類は、請求書・亡くなった方の年金証書・死亡診断書(または死亡届記載事項証明)・戸籍謄本や住民票・本人確認書類・振込先口座などです。
寡婦年金
寡婦年金は、亡くなった方が国民年金第1号被保険者として10年以上の納付期間を有し、10年以上婚姻(事実婚含む)していた妻に支給される制度です。
支給は妻が60歳から65歳までの期間に限られ、金額は夫の国民年金加入期間に基づく老齢基礎年金額の3/4です。
ただし、亡くなった夫がすでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合は支給対象外となります。
死亡一時金
死亡一時金は、亡くなった方が国民年金第1号被保険者として36か月以上納付していたにもかかわらず、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合に支給されます。
支給対象は生計同一関係にあった遺族(配偶者、子、父母など)です。
遺族基礎年金が受給できる場合は支給されず、寡婦年金とは選択制となります。
支給額は納付期間によって異なり、付加保険料を納めていた場合には付加金も加算されます。
請求期限は死亡日の翌日から2年以内です。
年金停止手続きに関する注意点・ポイント
手続きが遅れた場合の過払い・返還リスク
年金受給停止手続きを怠ると、死亡後も年金が振り込まれ続け「過払い」となります。
この場合、遺族が受け取ってしまった分を返還する必要があり、場合によっては加算金や延滞金が課されることもあります。
また、自治体や日本年金機構への情報連携の遅れにより、意図せず過払いになることもあるため注意が必要です。
「マイナンバー登録があるから大丈夫」と思い込まず、しっかり確認しておくようにしましょう。
不正受給とみなされるケース
故意に届け出をせずに過払い分を使い続けると、不正受給として扱われ、刑事告発の対象になる場合があります。
特に長期間にわたって放置した場合は悪質性が高いと判断されやすく、返還だけで済まない可能性もあるため、早めに対応しましょう。
書類がそろわない場合の対応
死亡診断書や年金証書などの必要書類の準備が難しい場合でも、まずは年金事務所やねんきんダイヤルに相談することが大切です。
場合によっては戸籍・住民票など別の書類で代替できることもあり、先に相談することでスムーズに手続きできます。
未支給年金・遺族給付の請求スケジュール
未支給年金の請求は5年以内、死亡一時金は2年以内など、給付ごとに時効が異なります。
請求期限を過ぎると受け取れなくなるため、早めに申請書を取り寄せ、必要書類を確認しておくことが大切です。
まとめ

相続発生後の年金手続きは、「年金受給停止」に加え、「未支給年金」「遺族年金」「寡婦年金」「死亡一時金」など、多岐にわたります。
どの制度が適用されるかは故人の加入歴や家族構成によって異なり、手続き先・必要書類・期限もそれぞれ違います。
放置すると過払い金の返還や不正受給のリスクがある一方、正しく請求すれば生活支援となる給付を受け取れる可能性があります。
まずは死亡届提出と同時に年金事務所や市区町村役場に相談し、必要書類をそろえて早めに手続きを進めましょう。
制度や条件が複雑な場合は、専門家に相談することで、漏れや誤りを防ぎ、スムーズに進められます。
わかば税務会計事務所では、経験豊富なスタッフが相続全般に関するご相談に広く対応致します。
ぜひお気軽にご相談ください。