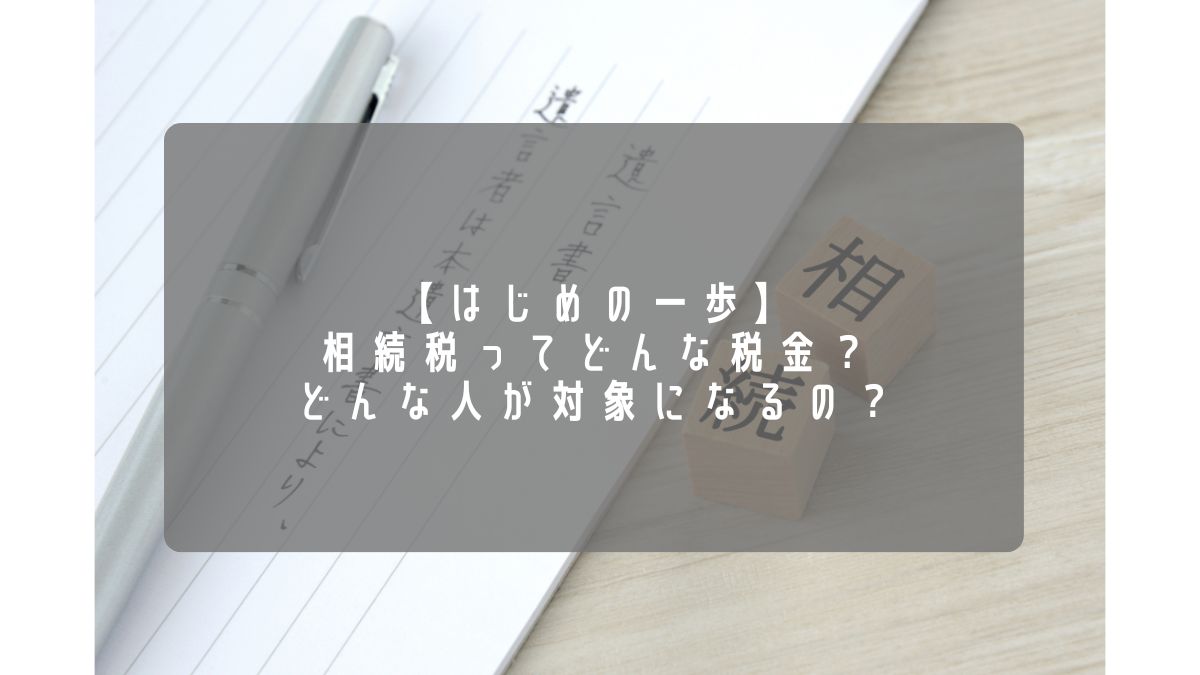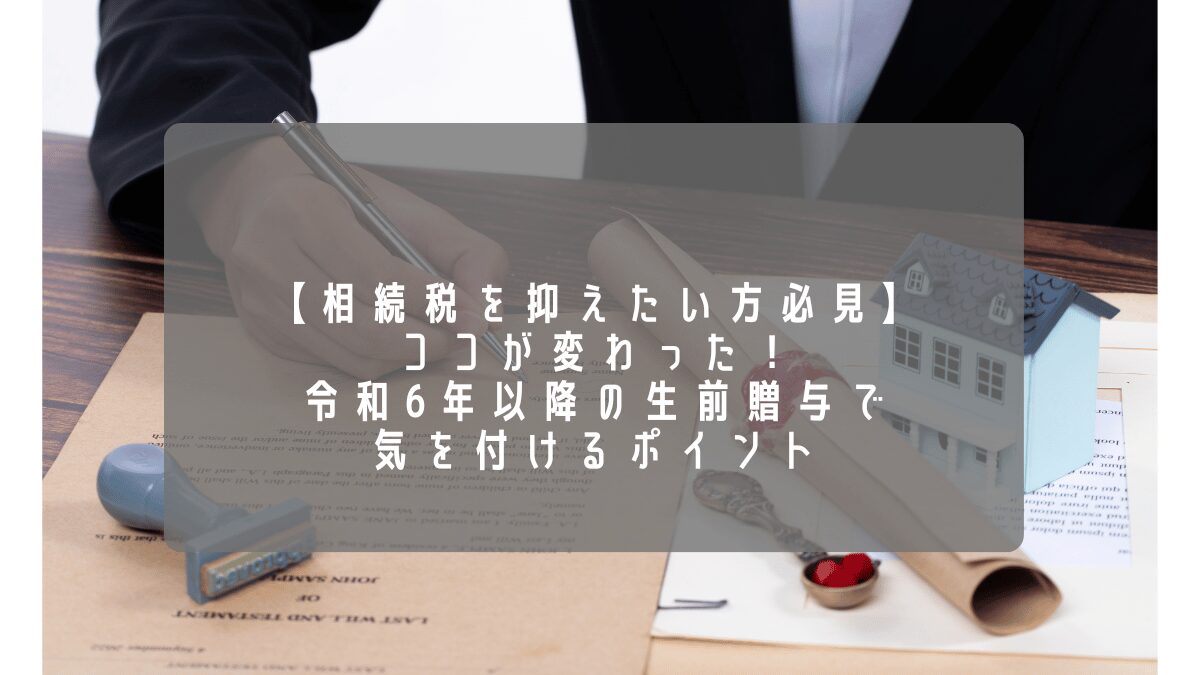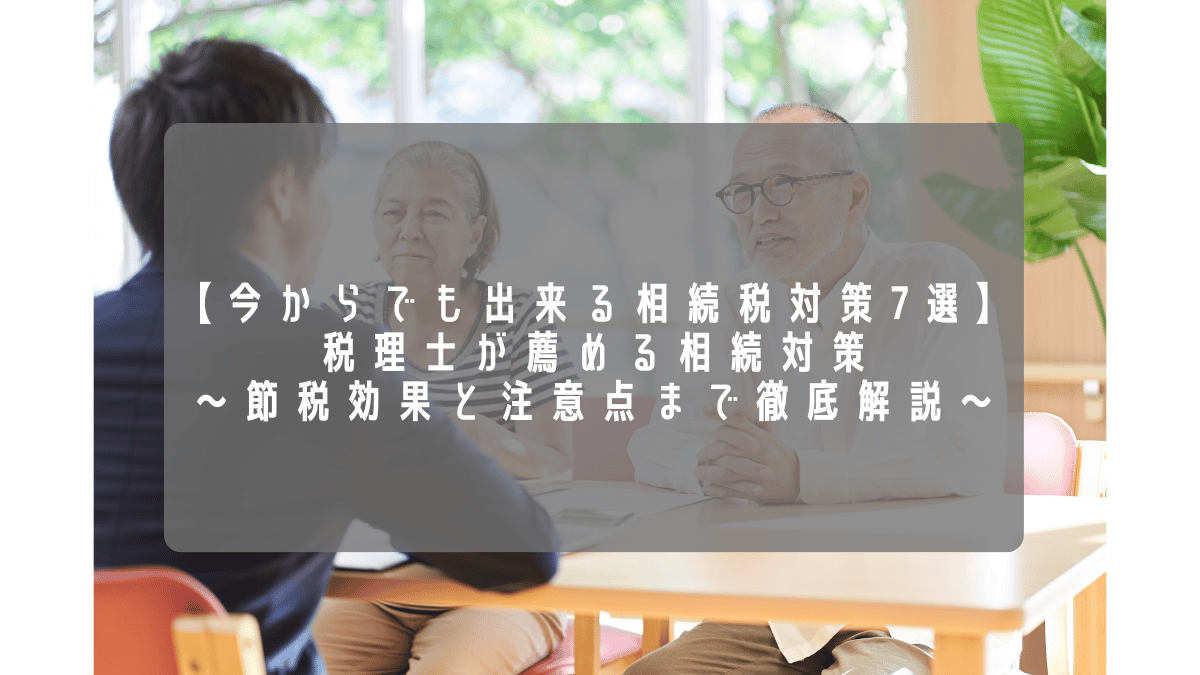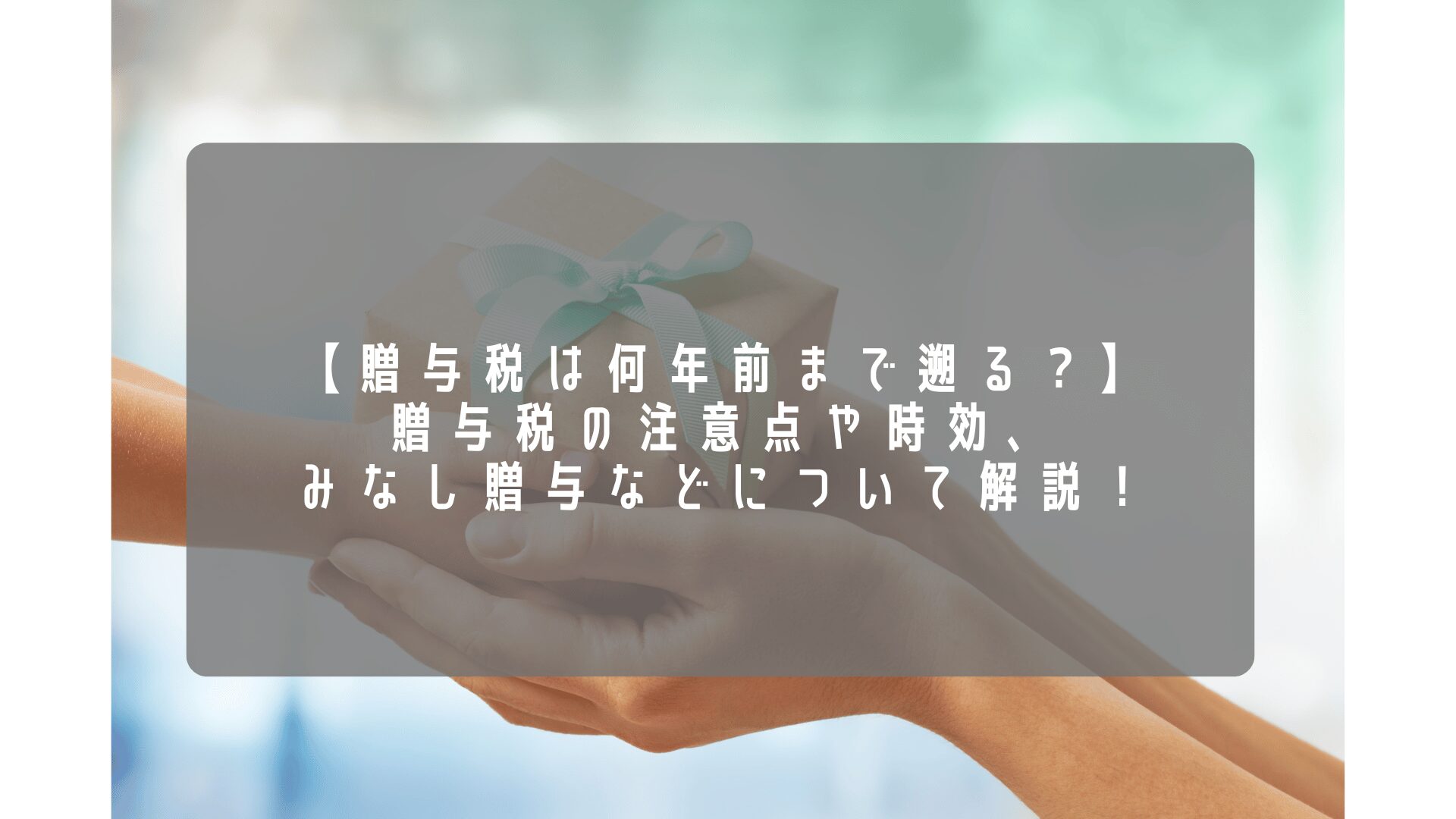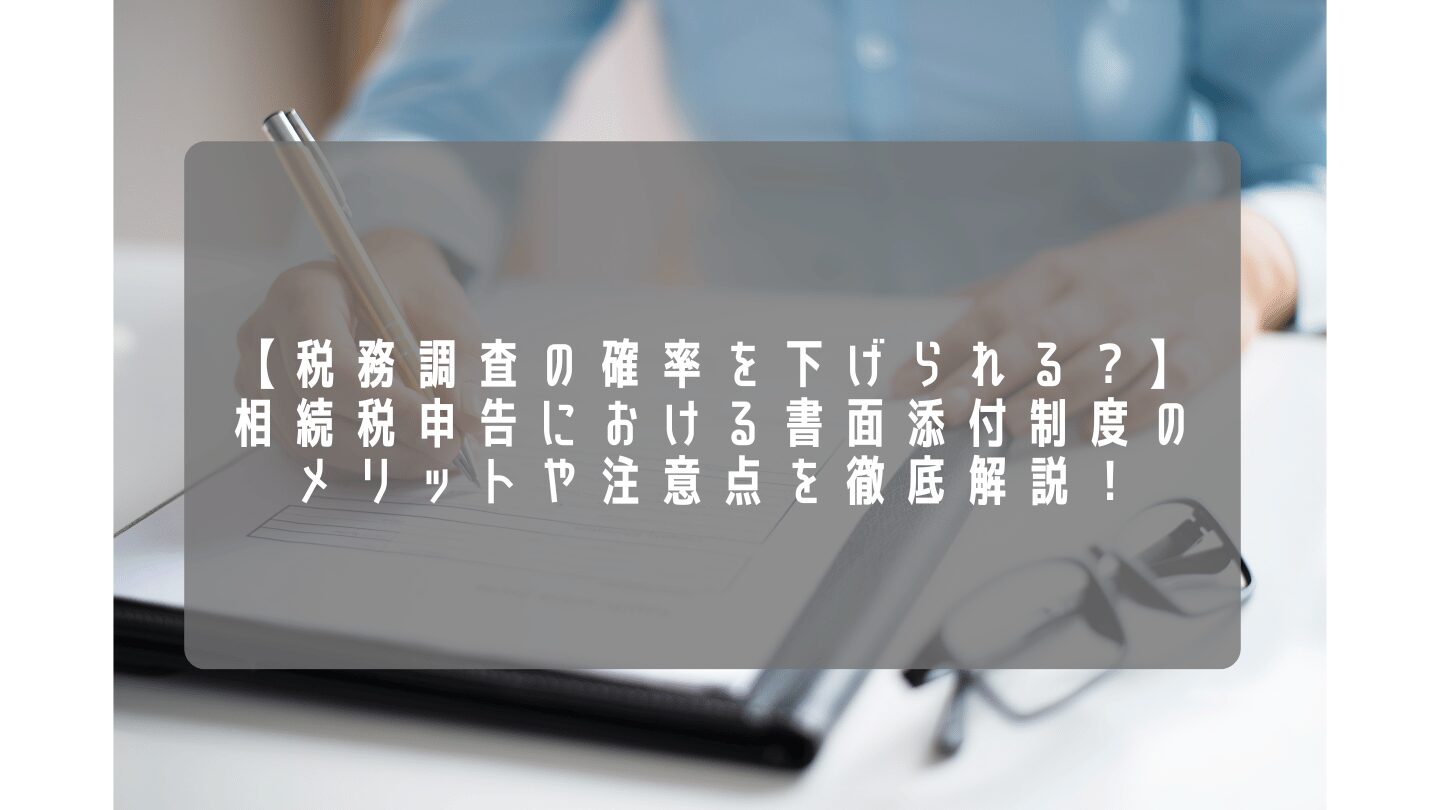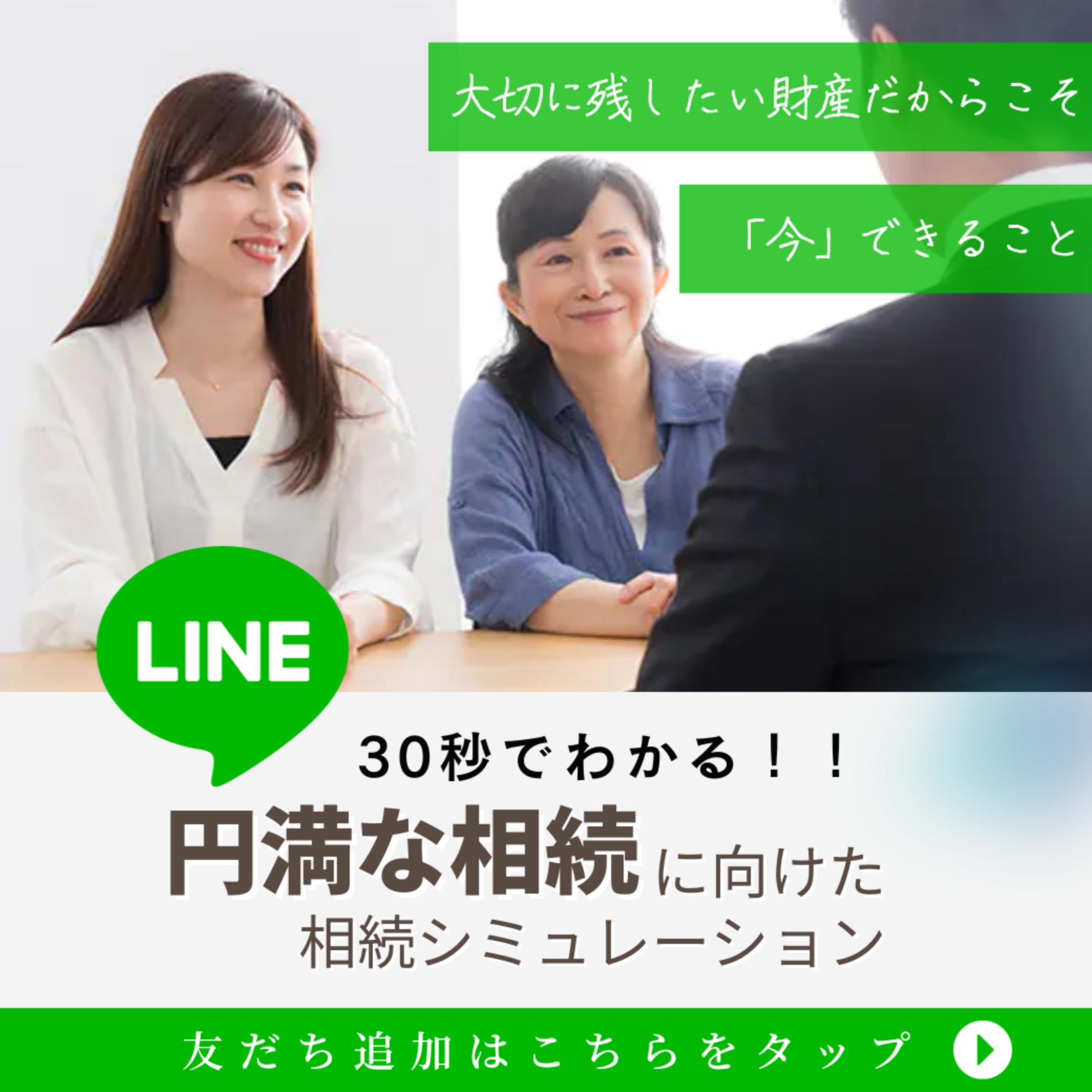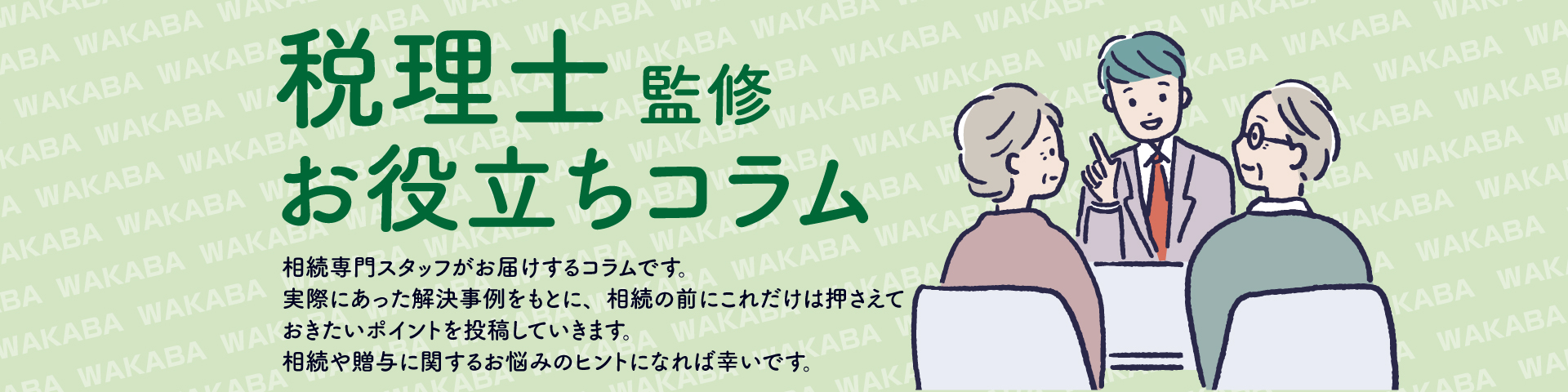
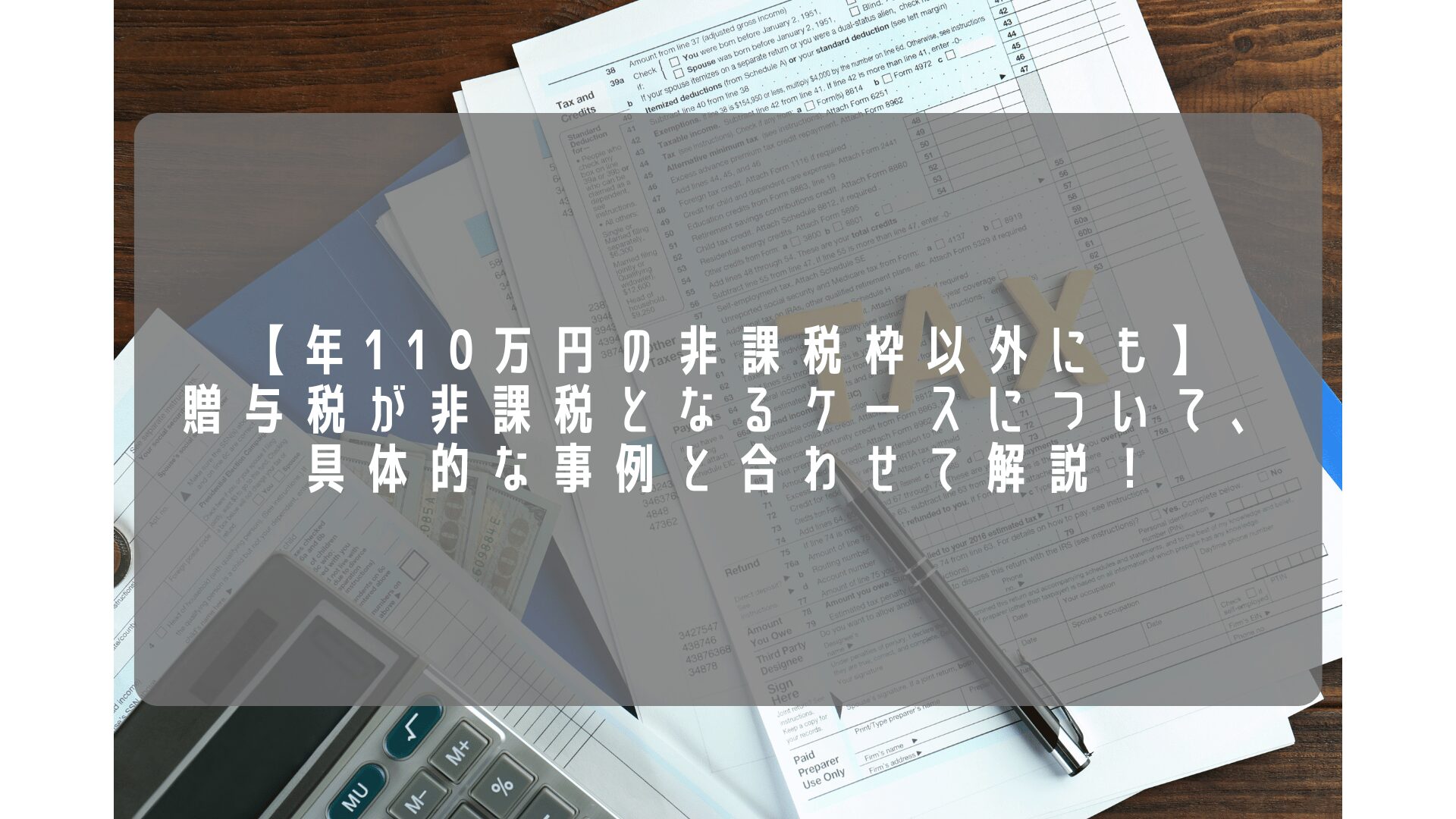
贈与税は、個人が他の個人から財産を受け取った際に課される税金です。
現金や不動産、株式など、金銭的価値のあるものが対象となります。
ただし、すべての贈与が課税されるわけではありません。
一定の条件を満たした場合に税金がかからない“非課税”となるケースが存在します。
たとえば、最もよく知られているものに、年間110万円までは贈与税がかからない「暦年課税の基礎控除」があります。
しかしそれ以外にも、教育資金や住宅取得資金など、目的に応じて非課税となる特例制度が存在します。
この記事では、基礎控除以外の非課税制度や具体的な非課税事例について紹介していきます。
上手く活用できると相続対策がより円滑に進められる場合もありますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
Contents
贈与税が非課税となるケースとは?
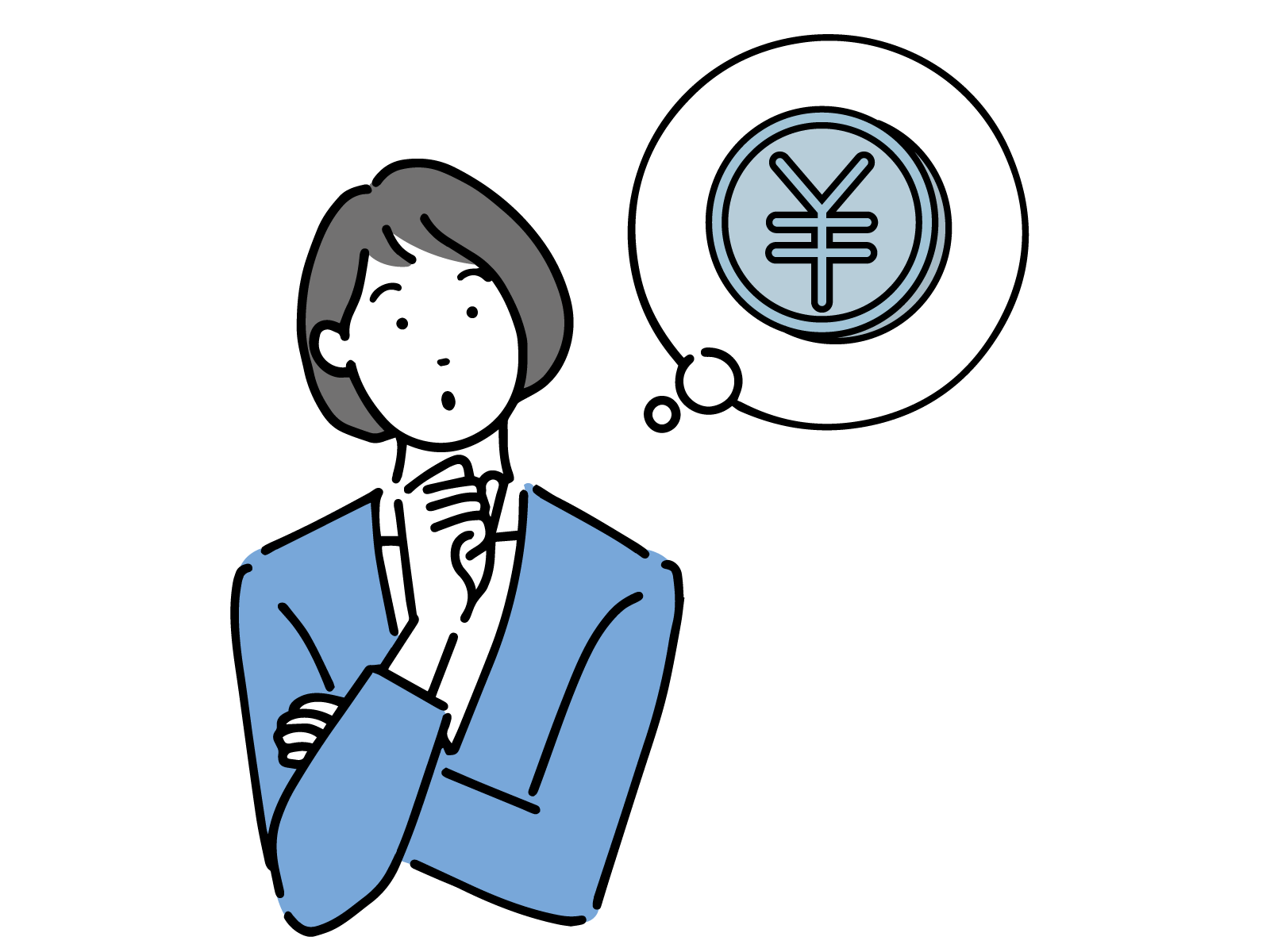
贈与税は、原則として個人が他の個人から財産をもらった場合、その全額が課税対象となります。
しかし、すべての贈与に税金がかかるわけではありません。
贈与の目的や受け取る側の状況によって、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる特例制度が多数存在します。
具体的には、以下のようなケースで非課税対象となり得ます。
●暦年課税の基礎控除額(年間110万円)以下の贈与
●相続時精算課税制度※の適用を受けた贈与
●日常生活に必要な範囲の生活費や教育費
●配偶者に対する居住用不動産の贈与
●教育資金の一括贈与
●住宅取得等資金の贈与
●結婚や子育て資金の一括贈与
●障害を持つ子どもへの扶養信託による贈与
※暦年課税と同様に年間110万円以下が非課税となります。
110万円以上となった場合は、相続が起こった際に相続税の課税財産となります。
これらの制度を正しく活用すれば、将来の相続税対策や資産移転を有利に進めることが可能です。
生活費・教育費の贈与(民法上の非課税)
扶養関係がある家族間で行われる生活費や教育費の贈与は、原則として贈与税の課税対象にはなりません。
たとえば、親が自立できない年齢の子どもの生活を支援するのは当然と考えられます。
そのため、その費用に課税するのは適切ではないとされているのです。
また、夫婦間においても、生活を共にするうえで必要となる費用については非課税とされるのが一般的です。
さらに、教育や医療にかかる費用、結婚や出産にかかる資金、子どもの学費や塾代なども、都度必要なタイミングで支払われるのであれば非課税となります。
ただし、「生活費」「教育費」としての名目があるだけでなく、実際にその用途に使われることが前提です。
趣味や投資、不動産購入など他の目的に流用された場合は課税対象となります。
また、一括で渡して貯金された場合や社会通念上不相当に高額な贈与は、課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
配偶者に対する居住用不動産の贈与
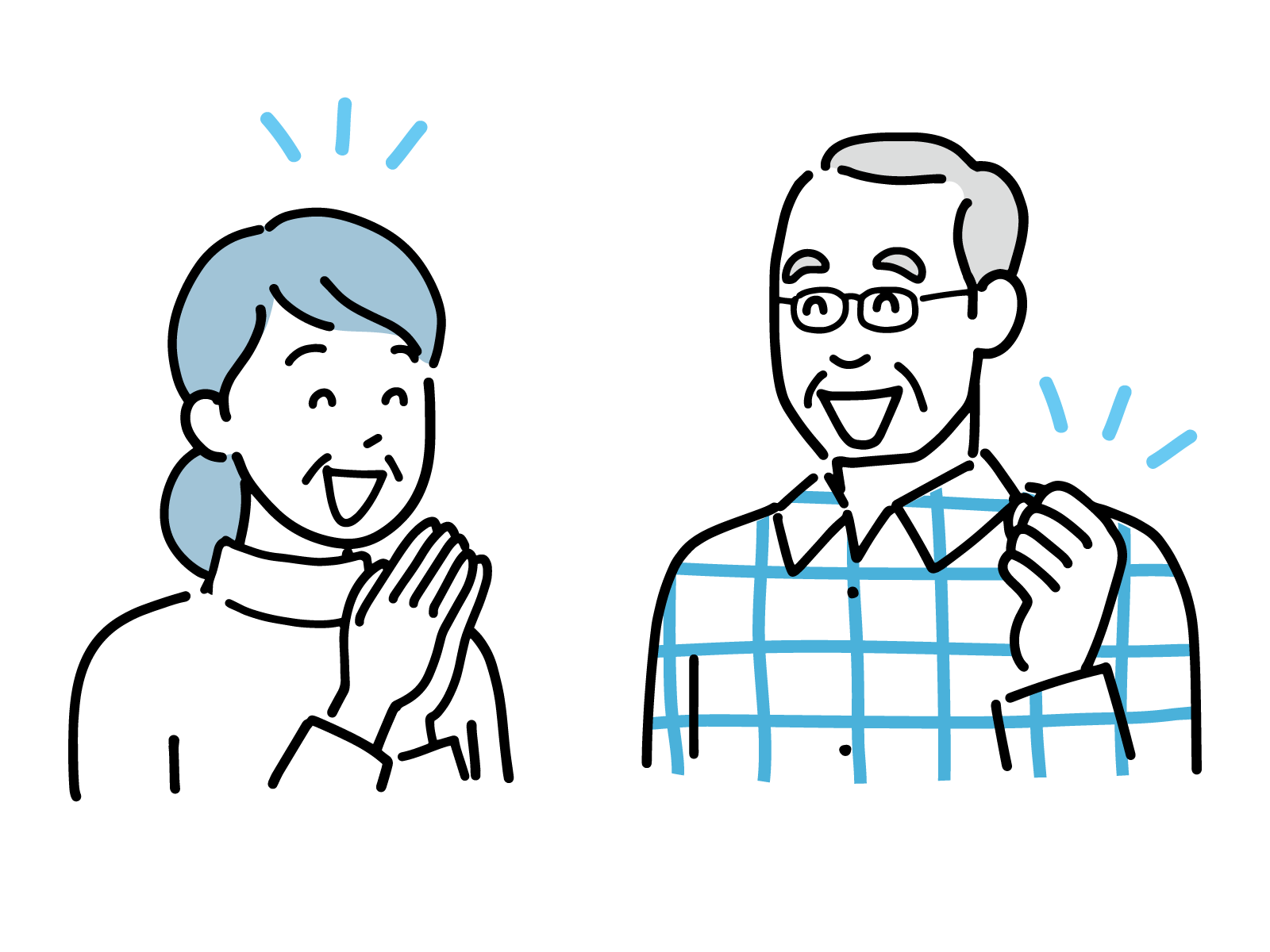
婚姻期間が20年以上の夫婦間では、配偶者に対する贈与のうち、居住用不動産またはその取得資金について、最高2,000万円までが贈与税の非課税対象となります。
これは「おしどり贈与」とも呼ばれ、暦年課税の基礎控除(110万円)と併用することも可能です。
ただし、法律上の婚姻関係にあることが要件となっており、事実婚のような形式ではこの特例は利用できません。
また、この特例は同一配偶者に対して一生に一度しか使えない点にも注意が必要です。
老後の生活基盤を整えるための贈与として、非常に有効な制度です。
教育資金の一括贈与制度
教育資金の一括贈与制度は、30歳未満の子や孫に対して、教育に関する費用を一括して贈与する際に、最大1,500万円までが非課税となる制度です。
金融機関で信託契約や専用口座を開設し、そこから支払われた学費、塾代、習い事、留学費用などが対象となります。
ただし、あくまでも教育目的に限定されており、趣味や娯楽の費用、使途が不明瞭な支出は非課税の対象外となります。
さらに、制度を利用する際は支出ごとに領収書の提出が求められ、専用信託銀行への定期的な報告が必要です。
30歳に達する時点で使い切れていない残額や不適切な使途に関しては、贈与税が課税される可能性があるため、制度の運用には十分な管理が求められます。
住宅取得等資金の一括制度
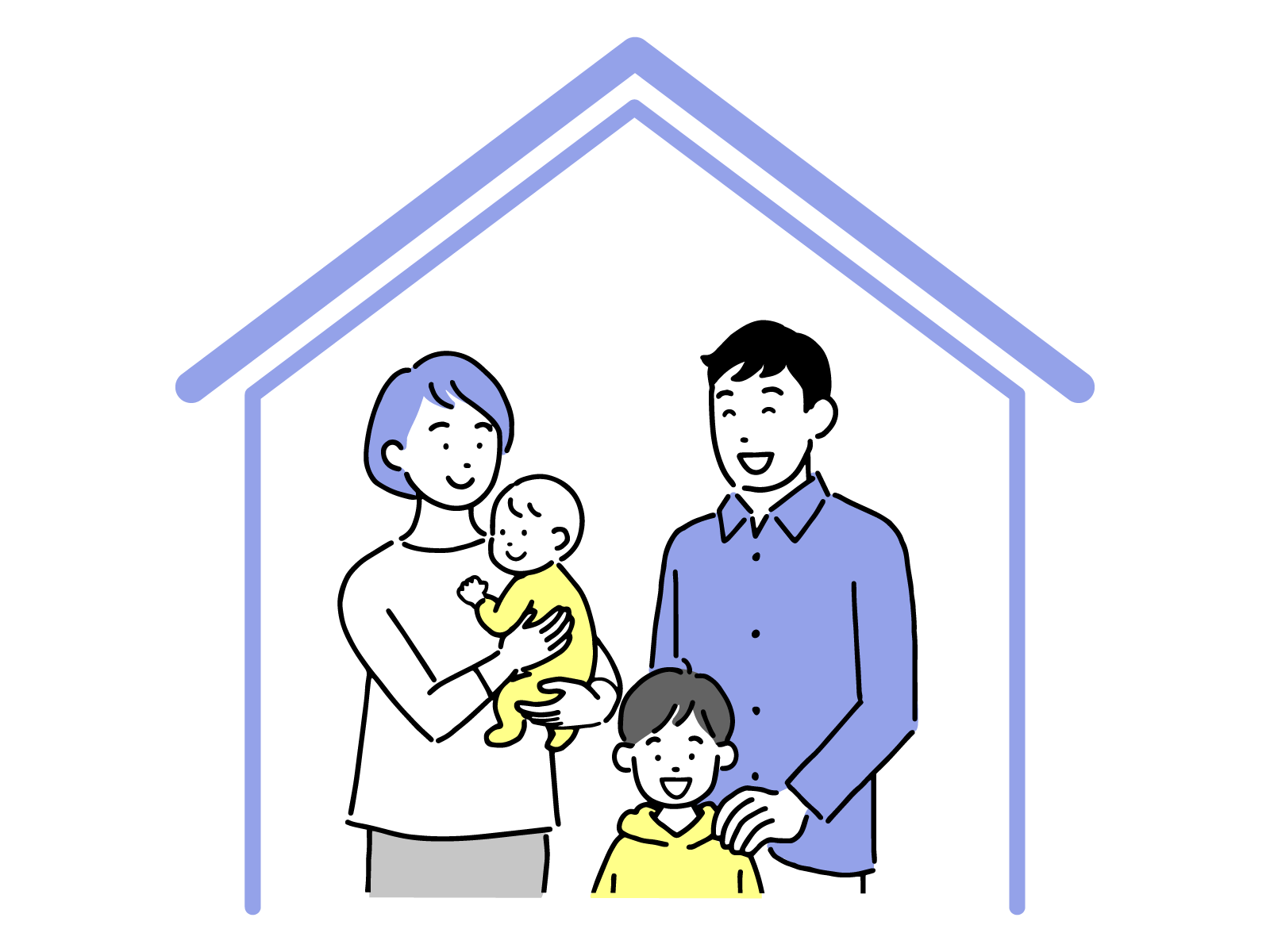
祖父母や両親から、18歳以上の子や孫へ住宅購入資金やリフォーム資金を贈与する場合、一定の条件を満たせば非課税となる制度です。
具体的には、省エネ住宅や耐震性などの基準を満たす住宅であれば最大1,000万円まで、それ以外の住宅でも最大500万円までの贈与が非課税とされます。
この制度を活用するためには、贈与を受ける人の所得が一定額以下であること、住宅の登記や居住開始の時期、床面積などの要件を満たす必要があります。
また、非課税であっても税務署への申告が必要です。
申告漏れがあると非課税の適用が受けられなくなるため、事前に要件を確認し、計画的に進めることが大切です。
結婚・子育て資金の一括贈与制度
この制度は、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や出産、育児にかかる資金を一括で贈与する場合に、最大1,000万円までが非課税となるものです(うち結婚関係費用は300万円が上限)。
信託銀行などを通じて専用の信託口座を設け、そこから支出する必要があります。
対象となる費用には、結婚式の費用、不妊治療費、産後ケア、保育園や幼稚園の費用、ベビー用品の購入費などが含まれます。
制度の利用にあたっては、各支出に対する領収書や証明書の提出が義務付けられており、使い残しや対象外の支出については贈与税が課税されます。
制度の適用期限もあるため、利用を検討する際は早めの計画が重要です。
心身障害者扶養信託制度(特別障害者非課税信託)
心身に障害を持つ家族の将来の生活費や医療・介護費を支援する目的で設けられた制度です。
特別障害者に該当する人を受益者とし、信託銀行などを通じて信託契約を結ぶことで、最大6,000万円までの贈与が非課税となります。
この制度を活用するには、特別障害者に該当する旨を証明する診断書や関係書類の提出が必要であり、信託の管理・支出にも一定の制限があります。
制度の仕組みが複雑なため、実際に利用する場合は税理士などの専門家への相談をおすすめします。
その他の贈与税がかからないケース
法的な非課税制度以外にも、慣習的・社会通念上非課税とされる贈与があります。
たとえば、結婚祝いや出産祝い、入学祝い、お年玉などは少額であり、贈与税の課税対象とされることはほとんどありません。
また、災害時の義援金や見舞金、損害賠償金なども法律で非課税とされているものに含まれます。
ただし、贈与の名目がこれらであっても、実態が単なる財産の移転であると判断されると、贈与税が課税される可能性もあります。
そのため、贈与の意図や使途、金額、頻度などについて客観的に説明できるようにしておくことが大切です。
贈与税の非課税対象とならないケース
借金を肩代わりする
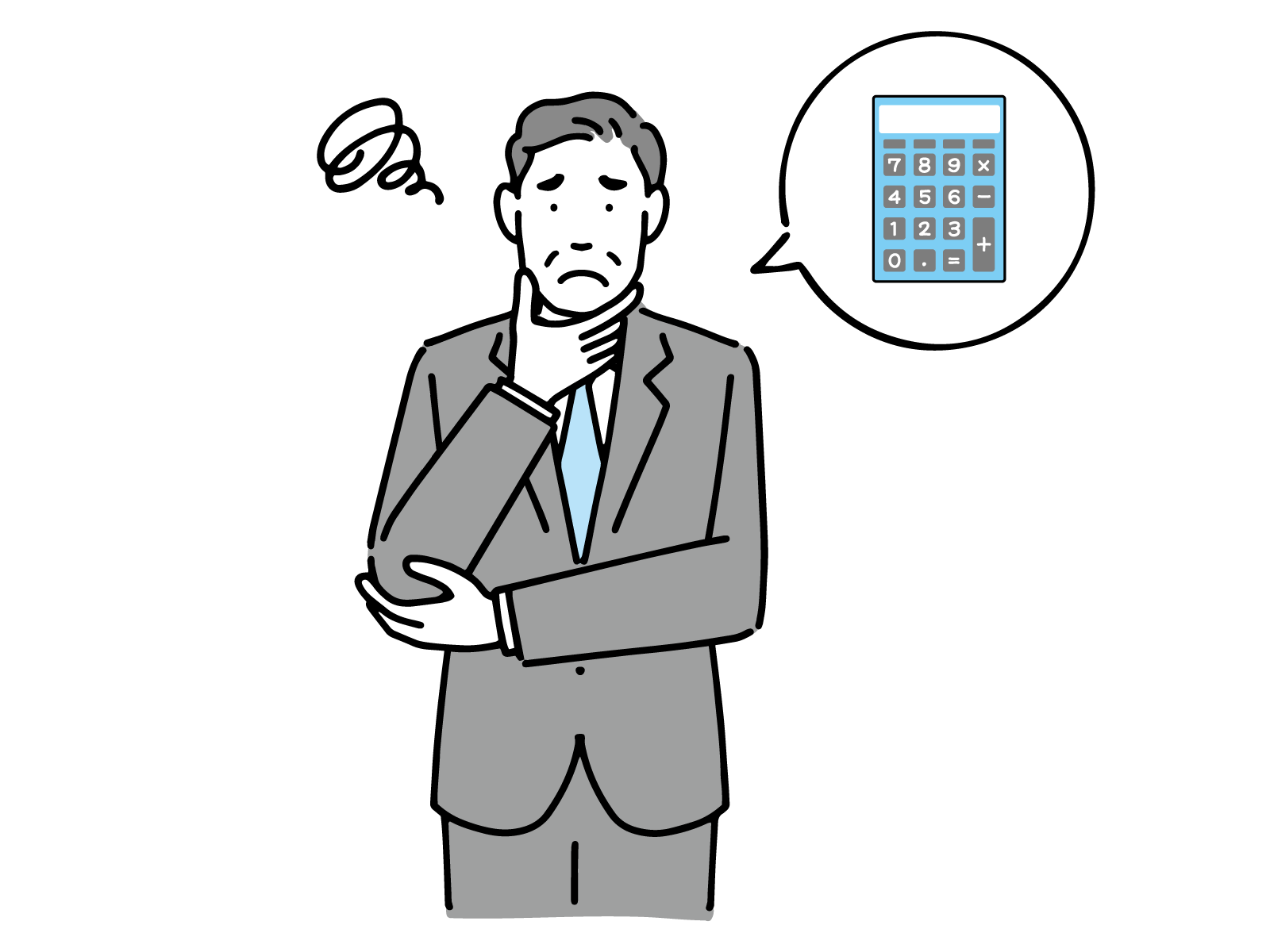
子の借金を親が代わりに返済した場合、子どもの手元に現金が残るわけではありませんが、それでも贈与税の課税対象となる可能性があります。
税法では、「いくらもらったか」ではなく、「いくら得をしたか」という経済的利益の観点で評価されるためです。
子は本来支払うべき債務が消滅したことにより、その分の負担から解放され、経済的利益を得たとみなされます。
したがって、この利益部分が贈与税の課税対象となります。
対象となるのは借金の返済に限らず、税金の滞納分、買掛金、クレジットカードローン、住宅ローンの返済など多岐にわたります。
ただし、返済能力がないことが明らかであり、かつ生活困窮者である場合などには課税対象とならない可能性もあるため、個別の状況によって判断が分かれます。
価値のあるものを格安で譲ってもらう
高額な美術品や不動産などの資産価値がある物を、相場よりも著しく低い価格で譲り受けた場合も注意が必要です。
「譲渡価格と時価との差額に相当する経済的利益を受けた」と判断されるためです。
たとえば1,000万円の価値があるものを100万円で購入した場合、差額の900万円が贈与とみなされる可能性があります。
贈与ではなく売買と主張するには、適正な契約書や実際の金銭授受の証拠など、取引の実態が伴っている必要があります。
具体的な事例の紹介
| 非課税の対象となりやすいケース | 夫が妻へ毎月15万円の生活費を振り込む 夫婦間の通常の生活費の負担として妥当な範囲であり、民法上の扶養義務に基づくため非課税となります。 |
| 子供が高齢の両親へ毎月10万円の生活費を振り込む 親が生活に困っている場合など、実態として扶養に該当すれば非課税になり得ます。 | |
| 親が障害者である40代の子への生活費15万円を毎月振り込む 自立が困難な障害のある子を扶養するための費用であれば、扶養義務の範囲内として非課税となります。 | |
| 親が子の大学の学費100万円と毎月の仕送り10万円を振り込む 進学中の子の学費や生活費は、教育費・生活費として扱われ、適切な使途であれば非課税となります。 | |
| 贈与税が非課税の対象とならない可能性があるケース例 | 本来自立できる年齢である健康な子へ毎月の生活費を振り込む 本来は経済的に自立可能である子への生活支援は「扶養義務」の範囲外と判断されることがあります。 |
| 子の高級車を購入するための費用を振り込む 車が生活に必要だったとしても、必需ではない高級車への支出は生活費と認められず、贈与税の課税対象となる可能性があります。 | |
| 親が子へ500万円を一括で渡し「自由に使っていい」と伝える 用途の特定がなく、自由に使える財産を渡した場合は、通常の贈与とみなされ課税対象となります。 | |
| 祖父母が孫に高額な現金を祝い金として一括で渡す 慣習的な範囲を超える多額の祝い金は、名目にかかわらず課税対象とされることがあります。 |
贈与税が非課税の対象となるケースの注意点
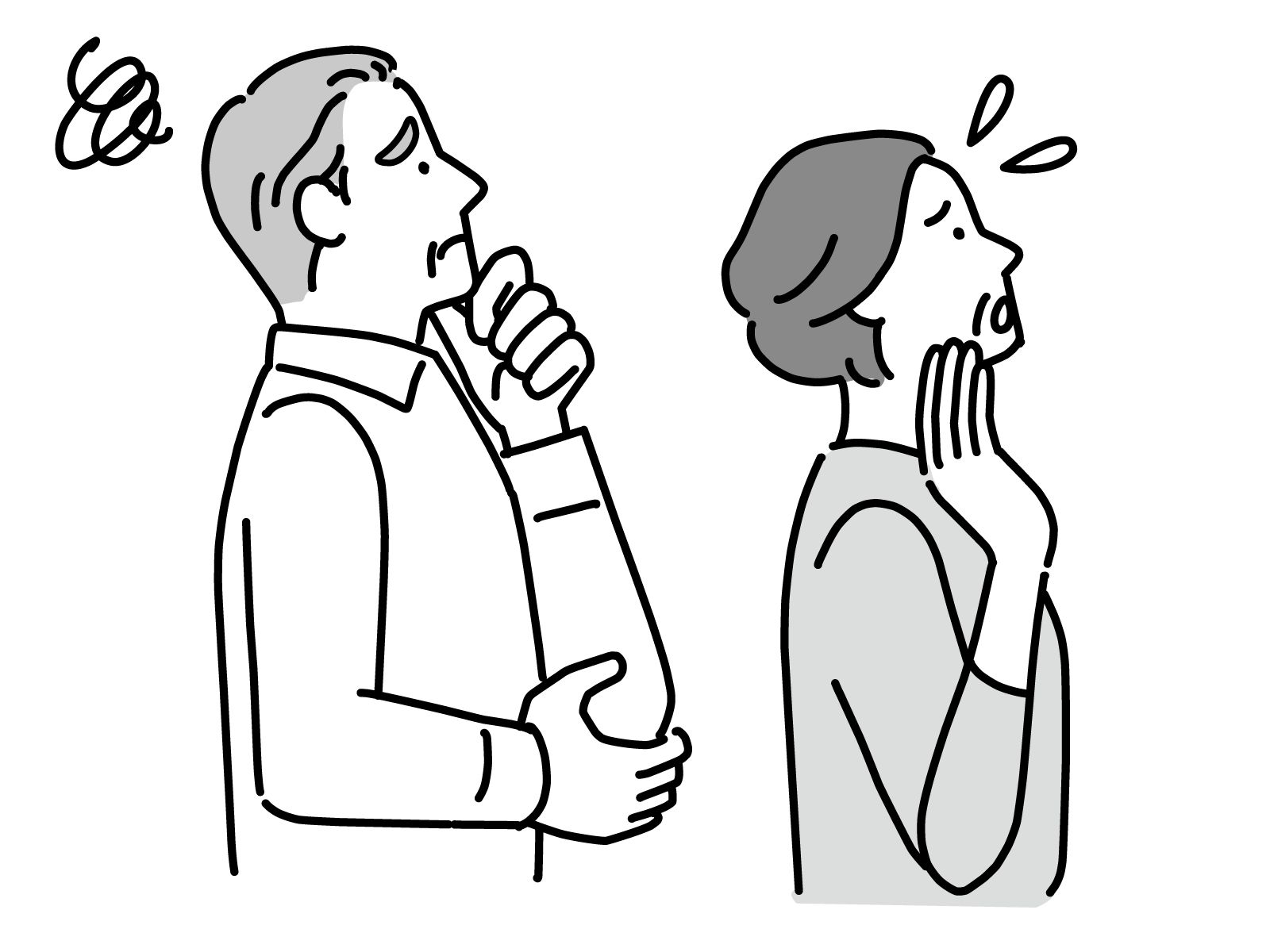
贈与税が非課税の対象となることで大きなメリットを得ることができますが、同時に注意すべき点も多くあります。
制度によっては、適用に厳格な条件や制限が設けられており、申告・証明・時期の管理を誤ると、本来非課税の対象となるべき贈与にも課税されてしまうおそれがあります。
正しく制度を活用するためには、制度の概要と条件をしっかり把握し、状況に応じて専門家に相談することも重要です。
領収書や報告書が必要なケースがある
非課税制度の利用には、支出内容を証明する書類が必要になります。
たとえば教育資金の一括贈与制度では、信託契約書や支払領収書、報告書などの提出が求められます。
結婚・子育て資金についても同様に、医療機関の明細や保育料の請求書などが必要です。
障害者扶養信託では、特別障害者認定に関する診断書や証明書の提出も必要であり、制度ごとに必要書類や手続きが異なります。
制度終了時や贈与者の死亡時には、残高の課税処理や申告も必要になるため、継続的な記録管理と専門家の関与が重要です。
名義預金に注意する
子や孫名義の預金口座に資金を移しても、実際の管理や使用権限が贈与者側にある場合は「名義預金」とされ、贈与として認められない場合があります。
※名義預金については、こちらの記事で詳しく解説しています。:https://zeimu-wakaba.com/135/
その場合、贈与とみなされず、将来的に相続財産と判断されて相続税の対象となるおそれがあります。
贈与を成立させるためには、贈与契約書の作成や名義人自身の管理意思を示すことが求められます。
正しい目的で使用する
制度の目的と異なる用途で贈与財産を使用した場合、たとえ形式上は非課税制度を利用していても、税務署による調査で課税対象と判断される可能性があります。
たとえば、教育資金として贈与された資金を旅行や投資に使った場合などが該当します。
非課税制度を利用する際は、使途を明確にし、証拠を残しておくことが非常に重要です。
まとめ

非課税制度は、単なる税金回避の手段ではなく、長期的な相続・贈与計画の一部として有効に活用することが大切です。
たとえば、子や孫の教育支援を計画的に行えば、生前贈与による資産の分散と相続税対策を両立することができます。
また、障害のある家族の将来の生活を支えるために信託制度を活用すれば、生活の安定と節税を同時に実現することも可能です。
このような制度を上手に使うには、ライフプランに応じた資金設計と、専門家との継続的な相談が欠かせません。
贈与の実施や制度の適用状況を毎年見直しながら、柔軟に計画を調整していくことが成功の鍵となります。
各制度にはそれぞれ厳格な条件や使途制限があるため、手続きの不備や誤解によって、非課税対象となるはずが課税対象となってしまうリスクもあります。
制度を正しく理解し、家族への支援と将来の相続対策の両立を目指していきましょう。
この記事を参考に、自分たちに合った制度の選択と準備を一歩ずつ進めていくことをおすすめします。
不安な点がある方は、ぜひお気軽にご相談下さい!