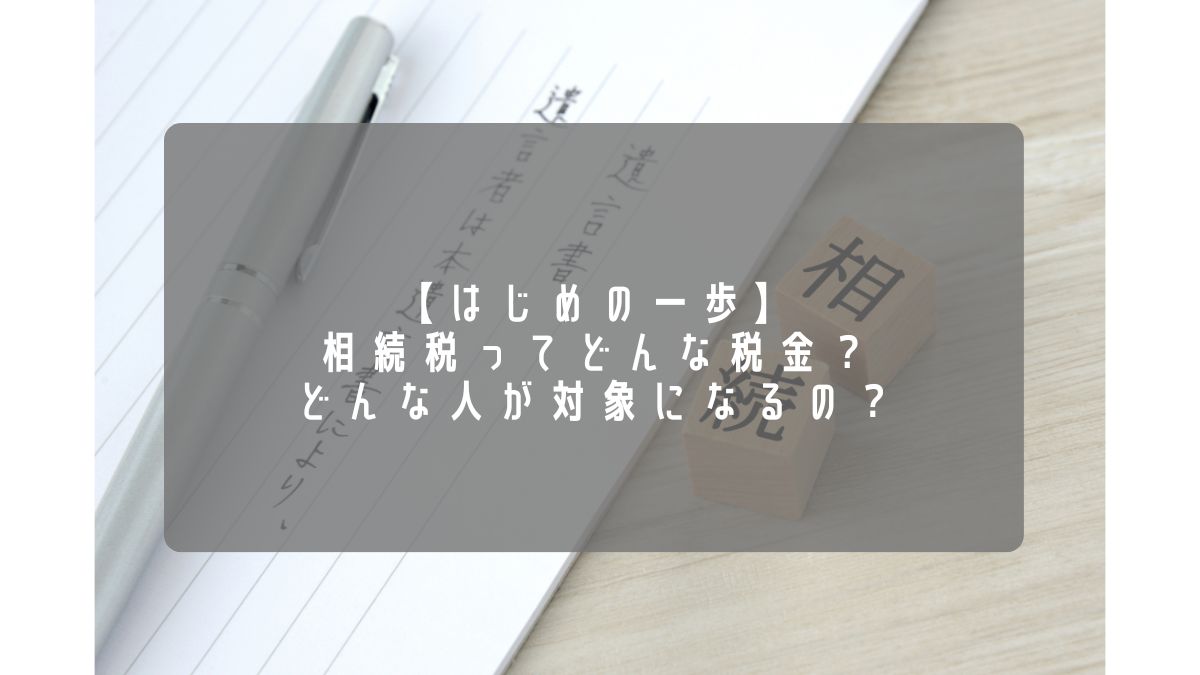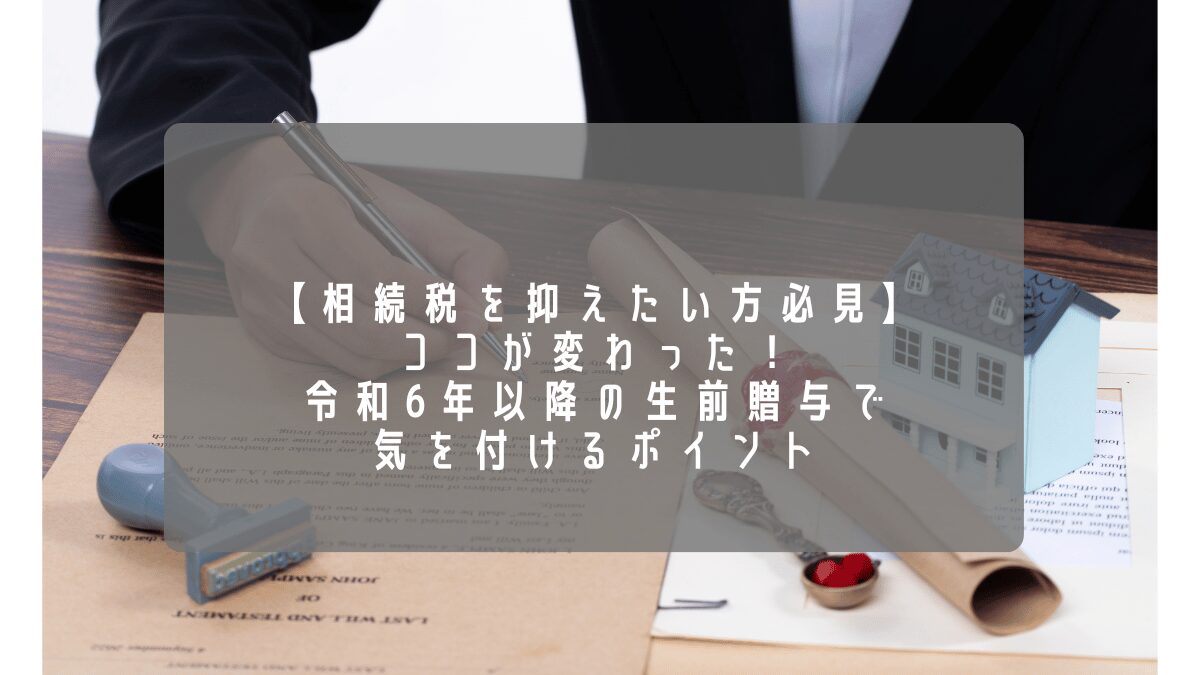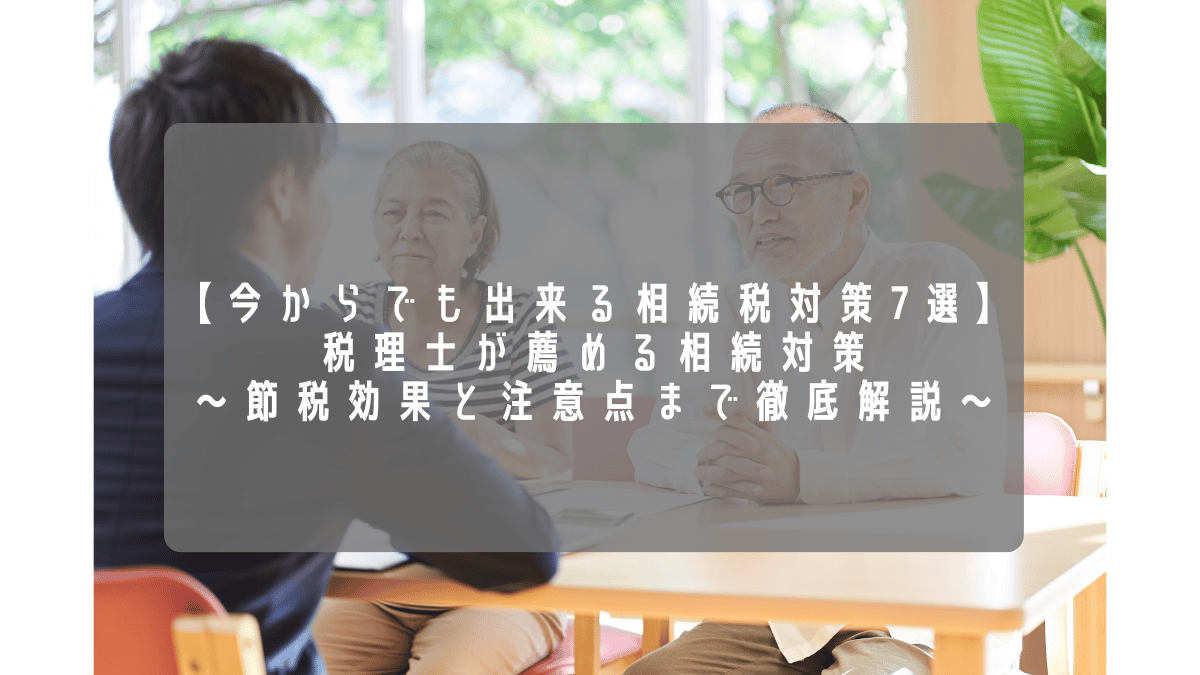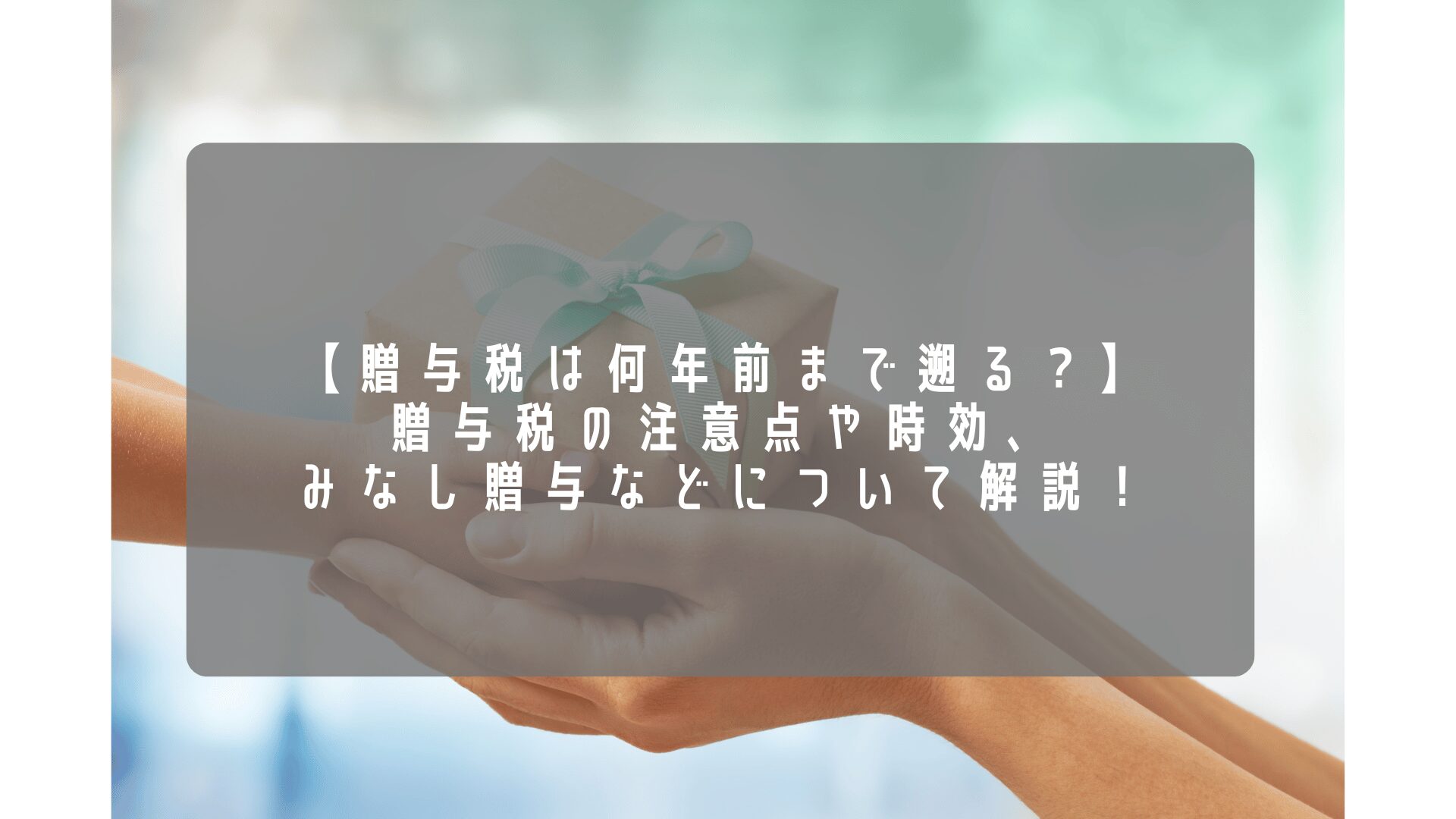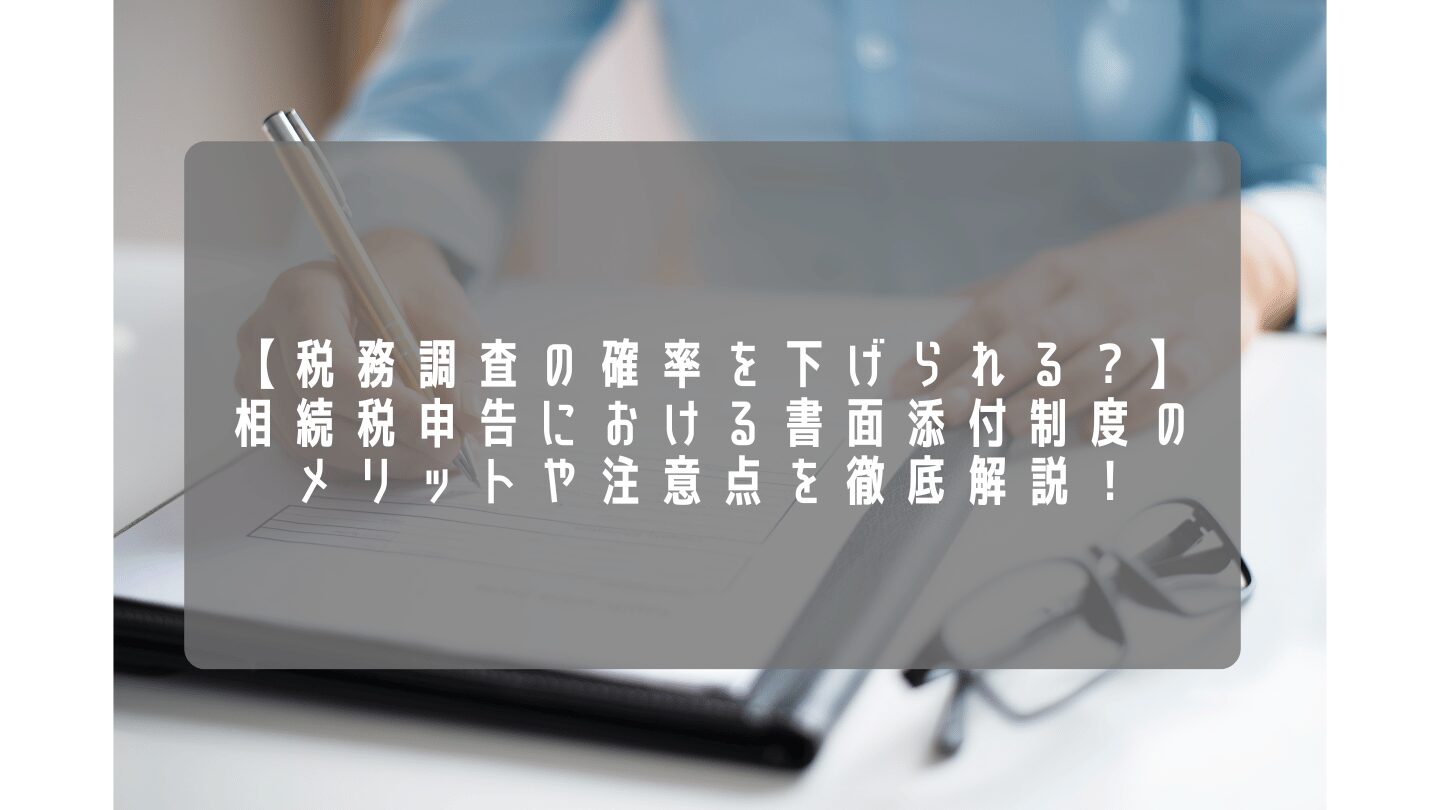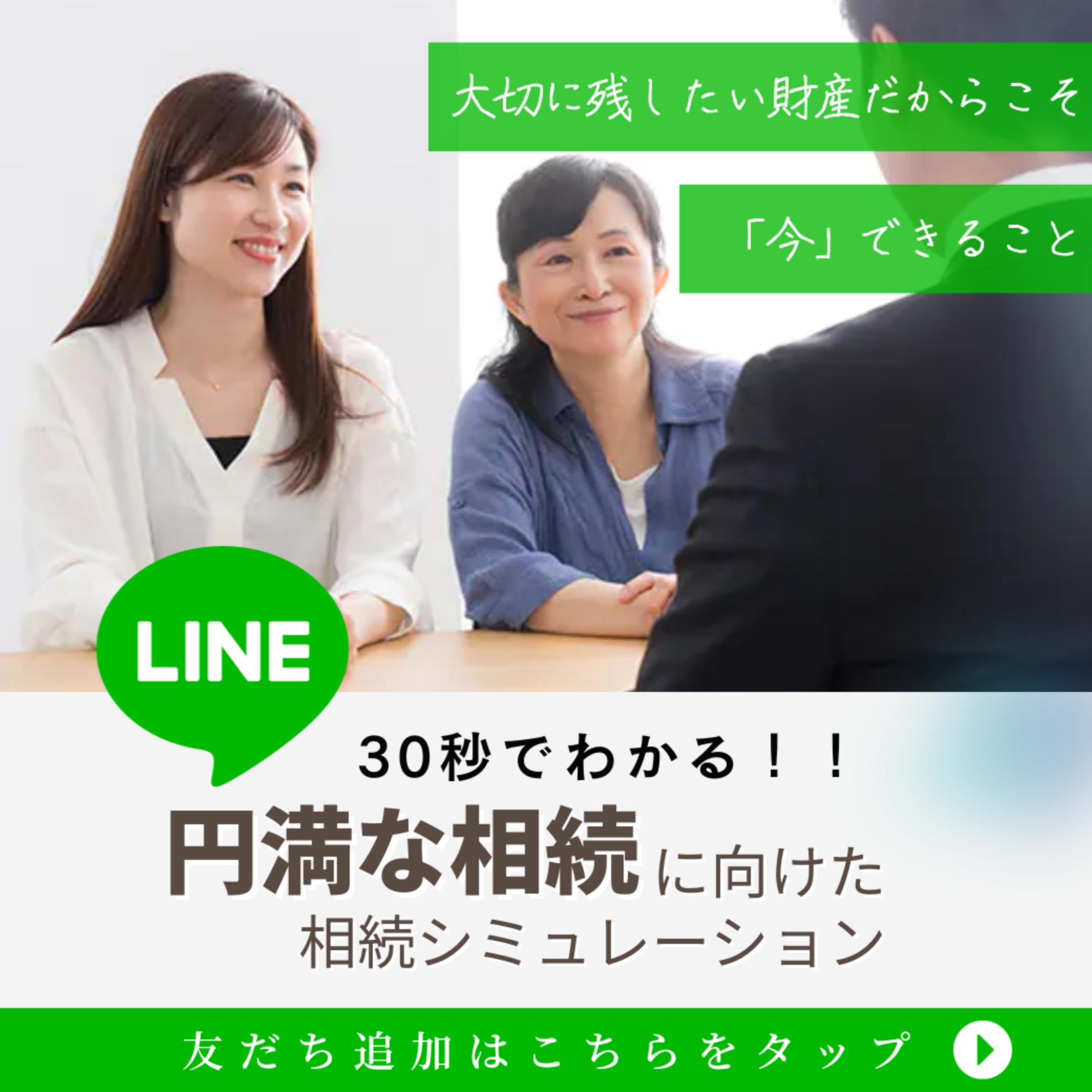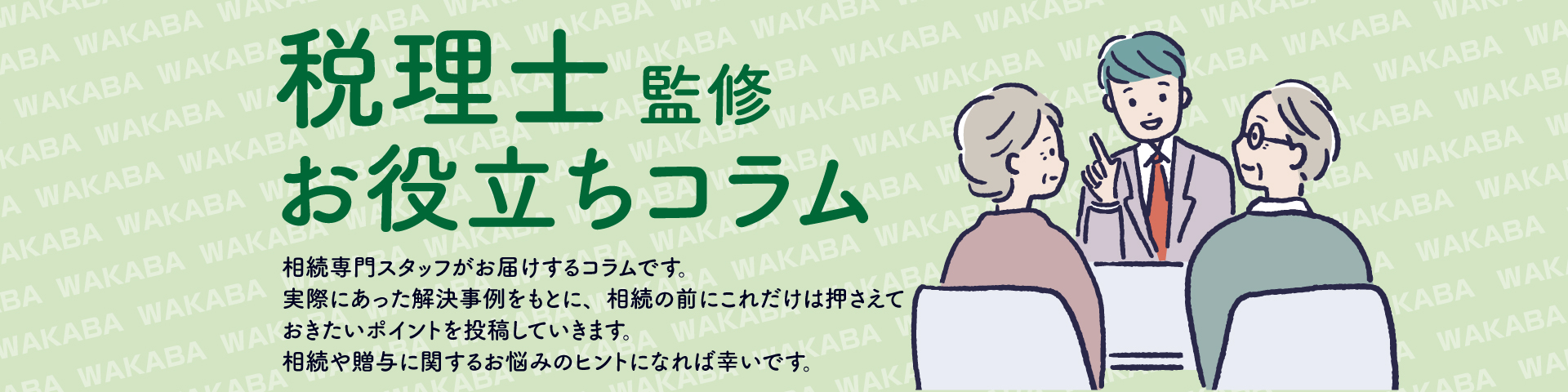
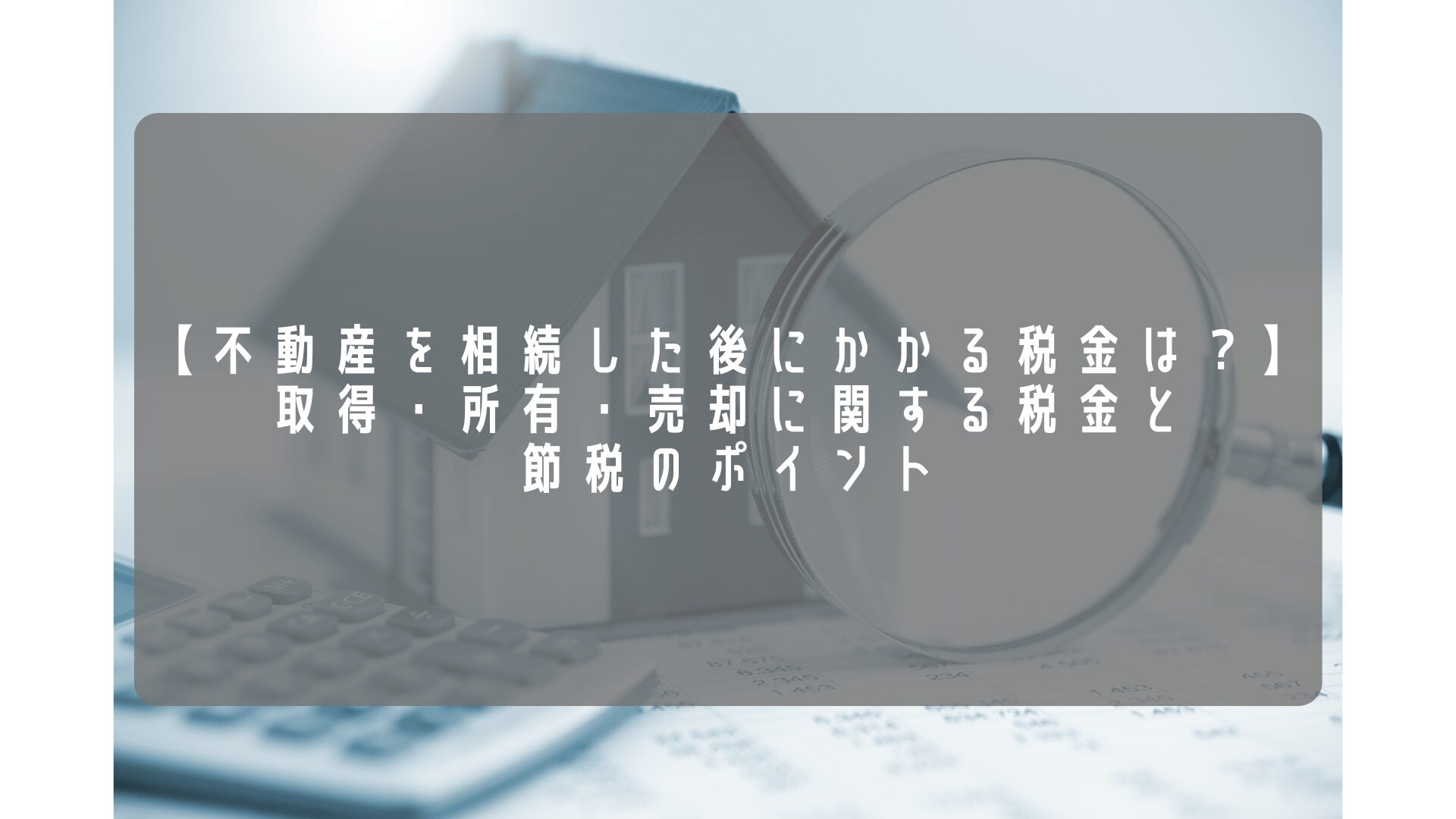
相続によって財産を取得した場合には、相続税が発生します。
相続税は定期的に課税される税金ではないため、基本的には申告と納税を終えれば一段落です。
しかし、相続財産の内容によっては、相続税以外にもさまざまな税金や手続きが必要となるケースがあります。
特に土地や建物といった不動産は、毎年の維持管理に伴う税金や、売却・活用時の税務処理が欠かせません。
本記事では、相続後に不動産を所有した場合に発生する主な税金や、節税につながる制度・特例について詳しく解説していきます。
価値が大きくなりやすい不動産は、税負担も高額になりがちです。
思わぬ負担やトラブルを避けるため、事前に正しい知識を確認しておきましょう。
Contents
相続後に発生する不動産に関する主な税金

不動産に関連する税金には、さまざまな種類があり、課税のタイミングは大きく3つに分けられます。
不動産は評価額・税額も高くなりやすく、手続きも複雑になりがちです。
「いつ・何に課税されるか」をタイミングごとに切り分けて把握すると、見落としを防げます。
①不動産の取得時:登録免許税や不動産取得税、相続税など
②不動産の所有時:固定資産税や都市計画税など
③不動産の譲渡時:譲渡所得税や住民税、印紙税など
不動産を取得した時にかかる税金
相続税
不動産に限らず、相続によって財産を取得した場合は相続税が発生します。
評価方法などは、別の記事で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。
(不動産に関する相続税の仕組みや具体的な対策方法について解説:https://zeimu-wakaba.com/102/)
土地は形状や利用区分で評価が増減します。
特例の対象かどうかで相続税額が大きく変わることもあるため、評価の条件等を必ず確認しましょう。
不動産取得税
相続によって不動産を取得した場合は、原則として不動産取得税がかかりません。
ただし、相続後の名義変更や遺産分割の方法によって課税関係が変わるため注意が必要です。
遺産分割協議が成立した後に「代償分割※」として不動産を取得するような場合には、課税対象となるケースがあります。
※(分割代償の例)相続財産である不動産を相続人Aの単独所有とする代わりに、相続人Bに現金を支払う場合など
登録免許税
不動産の所有権を相続によって移転する際には、登記が必要です。
このときに「登録免許税」が発生します。
相続登記の税率は固定資産税評価額の0.4%と、贈与や売買の2.0%と比べると低めに設定されています。
なお、令和6年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記をしない場合には過料が科される可能性があります。
登記のためには固定資産税評価証明書等が必要です。
相続関係書類(戸籍、遺産分割協議書など)も早めに準備しましょう。
不動産を所有している時にかかる税金
固定資産税
土地や建物を所有していた場合に、課税されるのが固定資産税です。
毎年1月1日時点の所有者が対象となり、たとえ使用していなくても納税義務が発生する点には注意しましょう。
市区町村の固定資産課税台帳に登録された評価額に基づき、「標準税率1.4%」が課せられます。
課税標準は言葉の通り標準的な税率であるため、自治体によってはこれを上回る税率を採用している場合もあります。
納付は年4期に分けて行うのが一般的です。
都市計画税
所有している不動産が都市計画施行地内にある場合は、固定資産税と併せて「都市計画税」が課税されます。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられる税金で、固定資産評価額の0.3%を上限に課税されます。
都市計画税の有無・税率は自治体ごとに異なるため、新たに取得した物件は所在地の自治体HPや課税明細で確認しましょう。
不動産を売却した場合の税金
所得税・住民税(譲渡所得)
相続によって取得した不動産を売却し、「譲渡所得(売却益)」が発生した場合は、所得税や住民税の対象となります。
譲渡所得は次の算式で計算され、計算の結果がプラスになれば「売却益」が生じていることとなり、その金額を基に税金が課されます。
取得費が不明な場合は、売却価額の5%を取得費として計算します。
譲渡所得 = 売却価額 −(取得費 + 譲渡費用)
●売却価額:不動産を売却して買主から受け取る金額です。年度途中に売却した場合、固定資産税の精算金も含まれます。
●取得費:購入代金や購入時の仲介手数料、登録免許税、司法書士報酬などの取得関連費用に、建物のリフォーム費用などを加えた金額です。相続では、被相続人が購入した際の金額を基に計算されますが、建物の場合は所有期間に応じた減価償却費相当額を購入価額から差し引きます。
●譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、印紙代など。
所有期間と税率
不動産の譲渡所得による税金の税率は、不動産の所有期間によって変わります。
●短期譲渡(5年以下):39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
●長期譲渡(5年超):20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
判定は譲渡した年の1月1日現在での所有期間のため、年内に取得から5年を超えても1月1日時点で5年超でなければ短期となります。
相続の場合、被相続人が取得した時点から通算して所有期間を計算できるため、長期譲渡として有利に扱えるケースが多いです。
印紙税
不動産を売買する際の契約書には、収入印紙を貼る必要があります。
印紙税は売買金額により変わるため、詳しくは国税庁のホームページを確認してみましょう。
不動産に関する確定申告
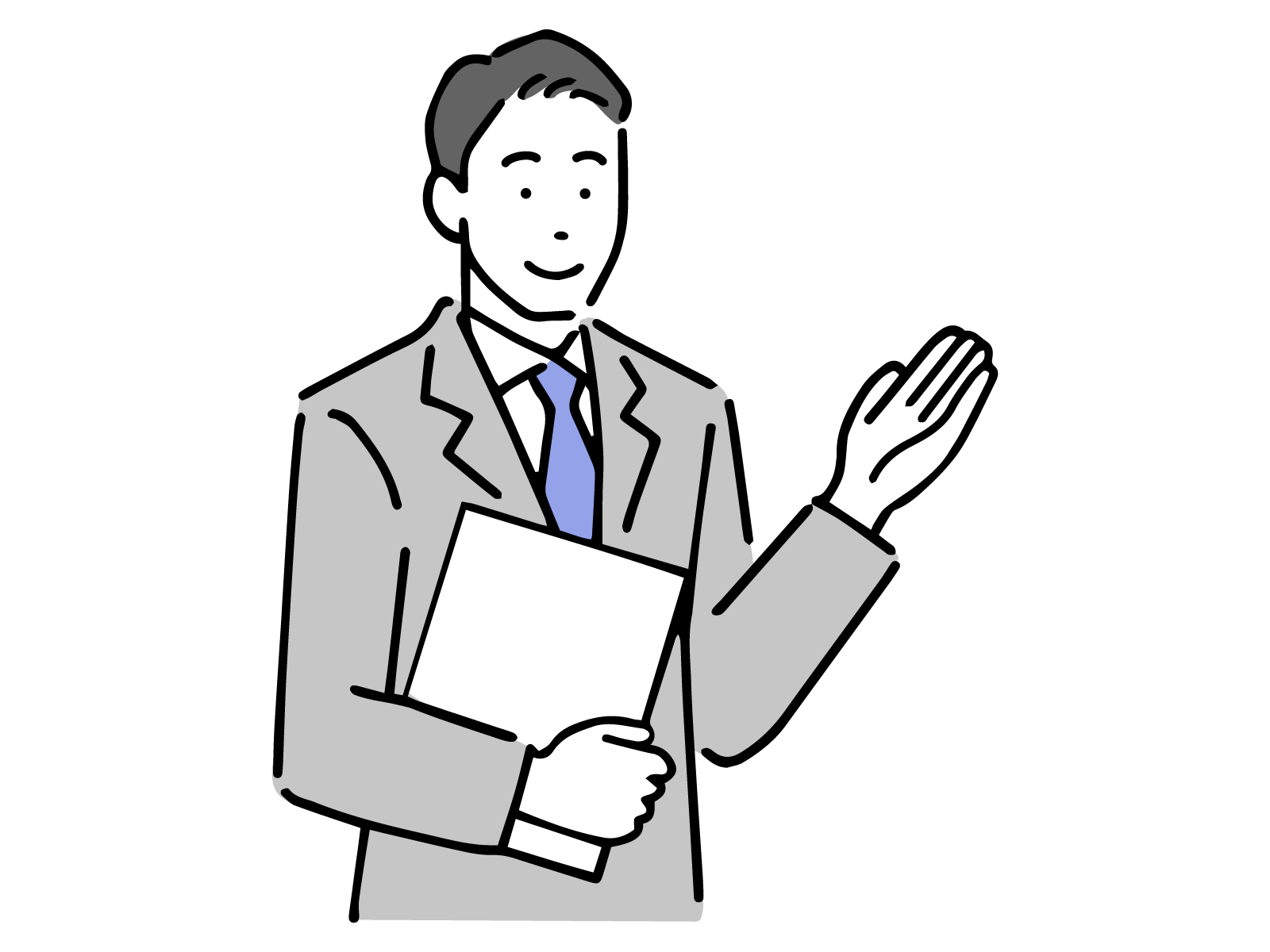
相続した不動産を売却し、譲渡所得が発生した場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
不動産売却に関する控除を活用し、税額がゼロになる場合でも確定申告は必要となりますので注意しましょう。
確定申告に必要な書類例
- 確定申告書の第一表、第二表及び第三表
- 本人確認書類の写し
- 譲渡所得の内訳書【土地・建物用】
- 不動産を売却したときの売買契約書の写し
- 譲渡費用に関連する領収書などの写し
- 不動産を購入したときの売買契約書の写し及び購入手数料などの領収書の写し
- その他、特例の活用に関する書類など
不動産に関する税金に使える特例や軽減措置
取得費加算の特例
相続税を納めた場合、相続が発生した日から3年10ヶ月以内に不動産を売却すると「取得費加算の特例」を使うことができます。
相続税の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得が圧縮され節税につながります。
ただし、相続税額や分割方法によって加算できる金額が異なるため、専門家への相談をおすすめします。
住宅用地の軽減措置
固定資産税と都市計画税は、住宅用地(居住用の建物が建っている土地)について、軽減措置が設けられています。
- 「200㎡以下部分:固定資産税1/6・都市計画税1/3」「200㎡超部分:固定資産税1/3・都市計画税2/3」に軽減
- 令和8年3月31日までに建てられた新築住宅については、一定条件を満たすことで建物の固定資産税が戸建てで3年間(マンションは5年間)半額となります。
小規模住宅用地の判定、家屋の有無・居住実態、区分所有建物の敷地按分など、実務の細則で適用可否が分かれます。
空き家となった被相続人の居住用財産の特別控除
相続で取得した空き家を一定の要件を満たして売却した場合に、最大3,000万円の特別控除が受けられる制度です。
主な要件は以下の通りです。
●昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
●区分所有建物登記がされている建物でないこと
●相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと
●相続してから譲渡するまで空き家であること
●相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
●売却価格が1億円以下であること
長期譲渡所得の軽減税率
10年以上所有していた居住用財産を売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下部分までは、通常の長期譲渡税率よりも低い軽減税率(所得税10.21%、住民税4%)が適用されます。
相続の場合は、所有期間を通算できるため、該当するケースは少なくありません。
居住用財産の特別控除
被相続人が居住用として利用していた不動産を、本人が存命中に売却する場合、「居住用財産の特別控除」を活用できます。
一定の条件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除することが可能です。
所有財産の状況によっては、生前に控除を利用して売却することが節税対策につながるケースもあります。
相続で不動産を取得する場合の節税ポイント
事前に購入価格がわかる書類を確認しておく
購入価額が不明な場合は、取得費を売却価額の5%として計算します。
ただし、売却価額の5%では、実際の取得価格を下回ってしまうケースも少なくありません。
そのため、被相続人になる人が不動産を所有している場合は、生前に資料の保管場所や購入金額などを確認しておきましょう。
損益通算を利用する
不動産の売却損は、原則として、他の所得と相殺する損益通算ができません。
ただし、同一年における不動産売却同士の損益は通算することができます。
複数の不動産売却を検討している場合は、同一年に売却したほうがよいかどうか、売却前に検討しておくとよいでしょう。
ただし、特例等で例外的に扱いが変わる制度もあるため、事前の確認は必須です。
不動産を賃貸物件として活用する
相続した不動産を賃貸に出すことで、家賃収入を得ることができます。
利益には所得税(不動産所得)と住民税が課税され、必要経費(固定資産税、管理費、修繕費、減価償却費、ローン利息など)を差し引いた後の所得が課税対象です。
賃貸物件として活用することで、「青色申告控除が可能」「家族に給与を支払うことで所得分散ができる」「修繕費や減価償却費を計上して税額を圧縮」などの節税対策を行うことが可能となります。
ただし、空き家リスクなどの問題もあるため、事前にしっかり検討を行いましょう。
まとめ

不動産を相続した後には、相続税以外にもさまざまな税金が関わってきます。
固定資産税や都市計画税は毎年の負担となり、売却すれば譲渡所得税が発生します。
さらに、不動産を賃貸に出した場合も所得税の申告が必要です。
ですが、不動産に関わるさまざまな税金も、あらかじめ知っておくことで余裕を持つことができます。
また、特例や軽減措置を上手に活用することで、税負担を大きく減らすことも可能です。
不動産を相続する際は、「保有」「売却」「賃貸」といった選択肢を検討すると同時に、税金のシミュレーションも行いましょう。
計算やシミュレーションに不安がある場合は、専門家への相談がおすすめです。
わかば税務会計事務所では不動産と相続に強い専門家が、最適な選択肢を見つけるサポートを行います。
ぜひ、お気軽にご相談ください!